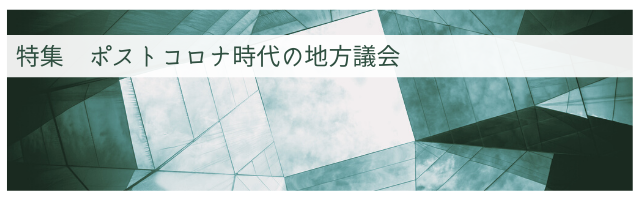近畿大学法学部教授 辻 陽
今年6月、『地方議員は必要か─3万2千人の大アンケート』(文春新書、以下「本書」と記す)が刊行された。これは、昨年1月から3月にかけて全国の地方議員に対しNHK取材班が126項目にわたるアンケートを実施し集計・分析したものであり、約6割、2万人近くの議員から回答が寄せられたという。
本稿では、このアンケートでの質問と結果について、理想の議員像・議会像という二つの側面に着目して解釈を行う。そして、自治体の人口規模によって政党・会派の役割に違いがあることを論じた上で、議会の種別によりアンケートの回答内容に違いがある点に注目し、本書が望ましいとする議会像が規模の小さな自治体議会にのみ当てはまることを明らかにする。
「議員」と「議会」
いうまでもなく、議会を構成するのは議員であるが、議会と議員とは完全に一致するものではない。議員にはそれぞれ、年齢、性別、経歴、自治体での居住歴といった、いわゆる社会的属性がある。また、政治的信念に沿って政党に所属する、あるいは地域の代表としての役目を果たすといった違いも議員間にはあるだろう。そして、これら社会的属性や政党所属の有無などといった特性と、議員活動との間には、一定の関係性が認められるだろう。
だが、議員選挙など個人の議員活動として完結するものと、そうではなく他のアクターとの兼ね合いも絡み合いながら運営されていく議会活動とは、分けて考えるべきであろう。つまり、どのような議会運営がなされるかについては、議会内での多数派のつくり方や、少数派の取り扱い方、あるいは首長との関係などを考慮に入れる必要があり、個々の議員に焦点を当てるだけでは、あるべき議会像は見いだせないだろう。
そこで、本書について、「議員」に注目した議論なのか、「議会」に注目した議論なのかという側面に着目しながら、検討してみよう。そうすれば、本書の主張もよりクリアになると思われる。
アンケート項目
本書の冒頭に、議員に対して送った設問が記載されている。簡単にまとめると、(1)初立候補・初当選時の年齢、(2)議員を志した年代、(3)議員になるきっかけ、(4)過去の経歴・職歴、(5)家族の理解の得やすさ、(6)有権者アピールのための活動内容、(7)政治的態度決定の際の自身や支持者・政党などの意見の重要度、(8)各種選挙活動の重要度、(9)議員活動のやりがい、(10)議員活動を行ううえでの考え方、(11)議員のなり手不足対策、(12)地方議会・議員についての雑感、(13)氏名、(14)性別、(15)生年月日、(16)出身地と選挙区が同一か否か、(17)所属政党・団体について、質問がなされている(かっこ内の数字はそれぞれ、問いの番号に対応する。以下同じ)。なお、(10)については、選挙、議員、所属議会そして議員・議会活動等についてのスタンスについて、YesかNoで回答する設問になっている。
(12)は自由記述による回答が求められており、(13)〜(15)は議員個人のIDにかかわる部分であるため、それ以外の項目についてここで検討しよう。(1)〜(6)及び(8)、(16)については、議員になるためにどのように選挙活動を進めたか、あるいはどのような社会的属性をもつ人が議員に選ばれてくるかといった、住民の代表たる「議員」そのものに焦点を当てた材料を提供してくれる。それに対して(7)、(9)、(11)そして(17)は、住民との接点に関する項目もあるものの、議会活動や政党など「議会」のあり方が問われたものだといえよう。そして(10)では、「議員」としてのスタンスと「議会」のあり方に対するスタンスの双方が問われている。
このように、本書のアンケート項目には、個々の「議員」の実態を明らかにしようとするものと、「議会」活動の実態を探る質問とが混在していることがうかがえる。