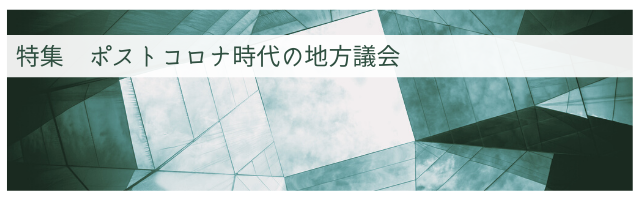緊急事態下にこそ「議事機関」は
続いて、『コロナ禍持久戦に備えよ』と題して、廣瀬先生による基調提起がありました。
まず、「緊急事態宣言は4月以降発令されたが、地方議会にとっては定例会の狭間の時期だったこともあり、ある意味対応しやすい時期であったのでは」としました。そして、国の補正予算で決まったコロナ禍対策が全国同じように実施されたこともあり、「あまり政策に差が出なかった」のも事実である、と指摘しました。
さらに、自治体において何かを実行するのは執行機関の役割であるけれども、コロナ禍においてはその「執行部の応急対応の足をひっぱらないようにという『配慮』が議会側に働いた」と推測しました。感染症の流行によって、人が集まって議論すること、言わば「議会の本質」に制約がかかったというわけです。
しかし国から財源が来るとしても、自治体としての単独事業も行うわけであり、議事機関による「大きな意思決定」は不可欠です。廣瀬先生は、「専決処分に委ねるべきでないなら、どのように審議、議決していくべきなのか、またその活動について市民にどのようにコミュニケーションをとるのか、個々の議員がそれぞれのチャネルを活かすことも大事であり、緊急事態下の『議事機関』の位置づけを改めて考えるときである」、としました。
感染症対応のための、議会BCPの見直し・オンラインツールの活用
議会版BCP(業務継続計画)については、大津市議会における議会初のBCP策定以後、一定の広がりをもって策定されてきたといえます。しかしそれは震災や水害など、主に自然災害を想定して作られたものがほとんどでした。これについて、廣瀬先生は、「『感染症対応』という事態は文言として入っていても、実態として想定していないことによる不十分さ、例えば、感染症流行により、物理的に人が集まれない事態をどう想定するのか」などが今後の課題であると指摘されました。BCPを未だもたない議会では、まず策定を視野に入れるべきであり、また、これまでのBCPに加えるべきことの洗い出しが必須となります。
「人が集まれない事態」にどう対処するのか、という意味では、議会におけるオンラインツールの活用が急速に注目を集めているとともに、活用が進んでいます。令和2年4月30日総務省自治行政局行政課長通知「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」において、委員会ならばオンライン活用が法的にも可能とされたところです。全国を見ても、取手市議会では、実際的な段取り、打合せ、論点確認などに活用、武蔵野市議会では執行部と議会のコミュニケーションに活用しているとのことです。
「持続する危機」という事態に議会はどう立ち向かえばよいのか?
基調提起を締めくくるにあたり、「『応急』で乗り切る段階は過ぎたが『解決』はまだまったく見えていない。『危機』は当分の間ずっと続いていく。その時に議会はどのように活動し何を実現することが求められているのか?」と会場に問いかけました。
廣瀬先生が掲げたのは、まず、「議事機関としての仕事を行う」ということです。感染症のためにリアルに参集することができなかったとしても、実効性のある審議を実現することは出来ます。それは例えばオンラインでの「審議」を有効に行うということです。
次に指摘したのは、「市民とのコミュニケーションの経路を確保し続ける」ということです。オンライン活用の芽が出て来たことで、それをうまく軌道に乗せれば、「従来よりも有効な活動さえあり得るかも知れない」としました。従来、仕事や子育てなど多忙により報告会に直接参集できなかった層が、オンライン導入により、かえって参加しやすくなるというメリットも様々なところで指摘されているところです。さらに議会報告会において、自治体内の感染症の状況認識や説明、自治体の対応策の内容と根拠、市民に何が求められるかなどがわかりやすく示される場になれば、「リスクコミュニケーションの場としての議会が機能する」ようになる、と指摘しました。
そして、議会での政策議論により、「自治体としての個別の情勢を反映する」ということについても求めました。ウィルスの感染拡大状況や経済社会への影響などは地域ごとに異なります。執行機関は、国等からの情報の把握とそれらを実施への落とし込むことは得意ですが、事務事業や制度の枠組みの外にある市民生活の実体把握は、多様な議員の集合体である議会が本来的に得意とするところです。機関としての議会が、自治体全体の有効な「政策資源」を集約できるかが、今問われている、としました。その際には、自治体としての政策的持続性の確保を検証すること、つまり応急的に乗り切れば何とかなるというフェーズはもう過ぎたということを認識するべきでしょう。今回の感染拡大により、今年度の徴収率、来年度の税収に大きなマイナス要素が生じることは必須であり、財政の不確実性が今まで以上に高まっているなか、例えば、単独事業のために、今年度で財政調整基金を使い切ってしまったら来年度の財源確保に不安が生じることとなります。「少なくとも数年間にわたって持続することのできる対応策をもちつづける必要がある」と廣瀬先生も指摘しました。
そして、「合議体がいま、ここにあることの意義を示していこう」、と呼びかけました。