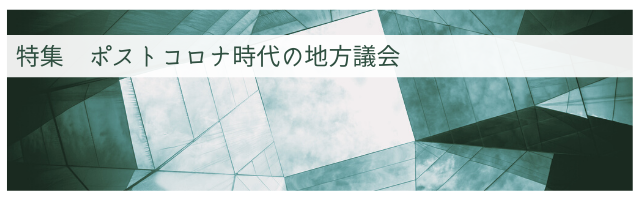【総務省自治行政局課長による「新型コロナウイルス感染症対策に係わる地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」((2020年4月30日付))の読み方】ス感染症対策に係わる地方公共団
「新型コロナウイル体における議会の委員会の開催方法について」((2020年4月30日付))が総務省自治行政局行政課長名で通知された。委員会出席は不要不急にはあたらないこと、新型コロナウイルス感染拡大によって議員の参集が難しい場合に条例や会議規則等の改正によってオンラインによる開議は可能であること、また、本会議は自治法上不可であることも通知されている。基本的には同意する(江藤 2020ab)。
ただし、2つの留意点を確認したい。1つは、委員会でのウェブ議会の活用が可能であれば、それは今回の新型コロナウイルス感染症の危機状況だけではなく、通常状況でも可能である。通知では「新型コロナウイルス感染症対策のため」と限定している(報道でも「通知は新型コロナウイルスに限定した措置」ということ)。しかし、公開原則を踏まえつつ危機状況では可能とすることを会議規則等で規定することも可能だと思われる。
もう1つは、本会議でのウェブ活用の是非についてである。筆者は、自治体による法令の自主解釈権を尊重しているが、「神学論争」は避けたい。自治法113条、115条、116条を解釈するのに説得的な根拠がない、あるいは薄い場合、自主解釈権だけで地域経営を行うことは、危なすぎる(裁判の可能性(前述))。説得的な根拠を示したうえで、法律改正を目指すべきである。
なお、複数の自治体から問い合わせがあったことで今回通知が出されたとのことである(『朝日新聞』2020年5月2日)。問い合わせもいいが、それぞれの議会、そして培ってきた議会間ネットワーク(議会事務局を含む)で考えることが必要である。危機状況において、総務省に「お伺い」する姿勢を問いたい。
ここまで今回の新型コロナウィルス感染症を念頭に置いて議論を進めた。しかし、今後、より感染力や致死率の高い感染症のパンデミックも想定される。また、壊滅的な自然災害も同様である。その場合、ここで提起したウェブ議会を挿入することになる。ただし、壊滅的な破壊が生じた場合、専決処分の可能性もある。ウェブ議会の対応、専決処分の限定・承認の流れについては議会版BCPなどで規定することになる。ともかく、危機状況にウェブ議会の活用に脚光が浴びた。自治を進めるためにどのような活用が考えられるか、冷静に判断したい。
危機状況下の定足数
危機状況を踏まえて、定足数の改正を考えよう。
本会議・委員会でも、定足数を充足して会議を進め(会派等で調整して、出席しない議員はネット中継で「観戦」)、表決や自ら発言する場合に議席に着座して参加することは運用で可能である。衆議院では、2020年4月10日以降(常会)の本会議と委員会では、会派の判断でよいことになっているが、定足数を確保しつつ採決以外では離席を認め、離席議員は議員会館等で中継を観て、採決時には議場に集まるようにした(6)。
同様な運用は地方議会でも行われている。静岡市議会の臨時会において(5月20~22日)、「議員の半数は別室のモニターで審議を見守り、採決の時だけ議場に入った」(「地方議会が「ノー密」審議、日程短縮や議員数制限…「住民の声届かぬ」懸念も」『読売新聞(オンライン)』2020年6月1日)
ただし、この運用は会派による議会運営が強い大規模議会では可能であるが、会派数が多かったり、政策会派とは呼べない場合には、困難である。
そこで、議事(開議)定足数を3分の1以上・議決(表決)定足数を2分の1以上にすることを議論してよい(自治法113の改正)。議決(表決)定足数を従来通り2分の1以上としていることには注意していただきたい。なお、国会では、「総議員の3分の1以上」が開議・表決定足数である(憲法56)。
かつて定足数を下げる提案があった際、筆者は「いま緊急に議論する意味があるのか。むしろ、全員出席することが前提である。出席しないことを善とするメッセージを送るべきではない」と述べたことがある。危機状況での議会運営として今後検討する必要もある。もちろん、定足数を下げても、議員の欠席を是認することではない。
危機状況下の選挙制度
議員も首長もその任期の終了前には、新たな選挙が行われる。危機状況であっても、そうである。感染拡大下の選挙では、開かれた選挙運動を模索する必要がある。投票日(期日前投票も含めて)には、投票用紙、鉛筆等の消毒、投票所の喚起等の準備が必要である。同時に、集会等の開催も抑制され、握手はできないといった選挙運動にも影響が出ている。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の対象地域で行われた市区長選挙では、「60%で投票率最低に」なった(4月7日から25日まで)。投票率は一般に低下しているが(下げ止まりの傾向もみられる)、選挙戦となった15の選挙のうち11で、「投票率が前回を下回り、全体の60%にあたる9つの選挙では過去最低となった」(NHKニュース(2020年5月27日)、NEWS WEB(2020年5月27日5時39分))。下げ幅が最も大きく、前回から25ポイント余り下げた選挙もあった(富山県魚津市長選挙、4月19日)。また、岡山県倉敷市長選挙では前回と比べて11ポイント余り下げ、25.7%と低くなっている(4月26日)。ここまで急激なのは、やはり個人演説会、集会、握手といった「三密」が自粛によって作動できなかったことがその理由であろう。ネットを活用した政策競争が必要だ。公開討論会もZoom等の活用などで進める必要もある。
なお、選挙にも例外はある。災害などにより投票日に投票ができない、さらに別の日に投票を行う必要があることは公職選挙法に規定されている(繰延投票、公選法57①)。また、大震災にあたって、例外的に臨時特例法が制定されれば、延期が可能となる。阪神淡路大震災の場合「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙日程等の臨時特例に関する法律」、東日本大震災の場合「平成23年東北地方太平洋沖地震にともなう地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」に基づいて延期された地方選挙もある。
新型コロナウイルスの感染拡大にともない公明党は「地方選挙の延期を可能とする議員立法の検討に入った」(『朝日新聞』2020年4月10日付)。ただし、「選挙は民主主義の基本であり予定通り行う考え」もある(同、岸田文雄自民党政調会長)。
筆者は、行政機能が壊滅的打撃を受けていない以上、選挙日程は通常通り行うべきだと考えている。任期はまずもって民主主義の基本だからである。その上で、公平な選挙戦が可能になるさまざまな取り組みを模索すべきである。選挙運動の自粛等だけでは、新人は政策を打ち出す機会が制限され現職有利になる。
なお、現時点では行政機能が壊滅的打撃を受けていないとはいえ、そうなる場合も想定できる。しかも、国会が閉会中であれば、「臨時特例法」は制定できない。厳格な規定をおいた上で(たとえば、新型コロナウイルスに対応した特措法での非常事態宣言の特定地域に指定され長期に及ぶ可能性がある等の条件を付して)、特例法ではなく一般法に例外規定を挿入することも慎重に検討する時期に来ているかもしれない(今後、郵送投票や電子投票の議論も考慮することになる)。
〔参考文献〕 ※詳しい参考文献は、江藤(2020ab)参照
江藤俊昭(2011)「議会の政策法務――住民代表性や合議体という特性から考える」北村喜宣・山口道昭ほか編『自治体政策法務』有斐閣
江藤俊昭(2019)「『平成』の地方議会改革――2つの<議会の政策法務>から考える」『自治体法務研究』2019年冬号
江藤俊昭(2020ab)「議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(上)(下)」『議員NAVI』2020年5月10日、25日号
吉田利宏(2020)「4月30日行政課長通知を読み解く」『議員NAVI』2020年5月9日
***
全国市議会議長会(2018)『要望書』
全国町村議会議長会(2018)『議会の機能強化及び多様な人材を確保するための環境整備に関する重点要望』
全国都道府県議会議長会(2020)「今後の地方議会・議員のあり方に関する決議-地方議会が直面する喫緊の課題への対応-」
【資料1:早稲田大学マニフェスト研究所「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書(案) ver2 」】
オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書(案)
今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、相当数の議員が隔離された場 合においても、急を要する感染症対策議案の審議、議決が求められる事態が、 現実のものとして想定されている。
定足数を満たす人数の議員が議場(招集場所)に参集出来ない状態でも、議案審議、表決などの議会運営方法が確立されていなければ、首長の専決処分を漫然と許すこととなり、議会不要論が増幅することは想像に難くない。
また、少子高齢化社会が到来する中で、育児や介護で容易に外出できない議員でも職責が果たせるよう、自宅から議案審議、表決に参画できる手段が、議員の多様性確保の観点からも求められよう。
世界的にも昨今の情報通信技術の発展とともに、既に英国議会ではオンライ ン議会を実用化している。
しかしながら我が国においては、地方自治法第113条及び第116条第1 項における「出席」の概念は、現に議場にいることと解されているため、オン ライン会議による本会議運営は現行法上困難とされている。
一方で、総務省は令和2年4月30日付総行第117号で、委員会運営については地方議会における意思決定によってオンライン化は可能との見解を発出 したが、本会議でのオンライン化ができなければ議会運営上の利点は限られる。
また、議会の意思形成過程である委員会審議においてオンライン化の有用性 を認識しながら、本会議における導入を否定するところに合理性はない。よって、国においては、非常時には地方議会の判断で、本会議運営をオンライン会議などの手段による遠隔審議・議決を可能とする、下記の主旨で地方自 治法を改正するよう強く要請する。
記
1 地方議会における本会議の開催が、情報通信技術による仮想空間での議会審議への参加、表決の意思表示によっても可能となるよう、議事堂への参集または議場への出席が困難な場合には、会議規則により参集場所または出席場所の複数指定や変更ができる旨を地方自治法において明文化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
〇〇議会議長 〇〇 〇〇
衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長
内 閣 総理大 臣
総務大 臣
【資料2:全国都道府県議会議長会(2020)「今後の地方議会・議員のあり方に関する決議-地方議会が直面する喫緊の課題への対応-」】
本会議及び委員会をオンライン会議により開催できるようにするとともに、議会のICT化への取組を支援すること【地方自治法改正事項含む】
新型コロナウイルス感染症や近年全国各地で頻発する大規模災害(地震、豪雨等)を巡る情勢、女性議員の出産・育児と議会活動の両立が求められている状況等に鑑み、迅速かつ柔軟な本会議及び委員会のあり方が求められている。こうしたことから、本会議及び委員会をオンライン会議により開催できるよう具体的に検討していくことが必要である。このため、地方自治法の定足数の規定や、表決のあり方を含めた運営方法等について検討の上、必要な制度改正を行うこと。
また、上記開催を実現する会議システムや通信環境の構築、議会と住民との双方向でやりとりができるオンライン会議システムの導入等、議会のICT化への取組について技術的・財政的に支援を行うこと。
【資料3:第32次地方制度調査会第39回専門小委員会「2040 年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために 必要な地方行政体制のあり方等に関する答申(案)」(2020年6月4日)】
第5 地方議会〔中略〕
3 今後の検討の方向性〔中略〕
今後生じる変化・課題に対応した持続可能な地域社会の実現に当たっては、住民の多様な意見を反映しながら合意形成を行う場となる議会の役割は一層重要になることから、議会制度や議会運営のあり方、議員に求められる役割及び多様な層の住民の参画について、今後とも幅広く検討を進めていく必要がある。その際、議会運営や住民参加の取組等におけるデジタル化への対応や団体規模に応じた議会のあり方についての新たな選択肢の提 示等も含めて引き続き検討すべきである。
(※下線部は引用者注、議会におけるウェブの活用が議論され、追加された箇所)
【追記1】本稿は、副題(サブタイトル:地方分権一括法施行20年の節目に)にもある通り、住民自治を進める法改正の課題を探るために執筆していた。第2回定例会(6月議会)での危機状況での本会議でのウェブ活用の改正をめぐる意見書決議を行う議会も想定される。そこで、危機状況を切り離して先行して筆者なりの考え方をまとめている。本文から明確なように、ウェブ議会を肯定的に評価しているわけではない。通常状況でも活用できることの限定、危機状況での活用を議論したかった。
【追記2】新型コロナウイルス感染拡大に伴う危機状況において、先駆的な議会でも悩んでいる。通常の議会運営を作動させることが、まずもって重要である。「三密」を避ける議会運営も模索されている。非公式・打ち合わせではメールも使えれば、ウェブも活用できる。合理的効率的議会運営を目指してほしい。折しも、総務省において「通知」が出された。短期間での発病・重症化の速度・致死率の高さなどが新型コロナウィルスを越える感染症拡大も想定される。その時の対応を探りたかった。自然災害も含めて、どこまで合議体としての議会を作動させることができるか、不可能な場合専決処分(筆者は通常での作動は極めて否定的)をどう位置づけるかを議論したかった。日々刻々と変化する社会において、筆者も歩きながら、あるいは走りながら現実に向き合っている。「江藤議会改革論」からの照射ではあるが、不十分性は承知している。議論の中で変更する場合もあることを踏まえて、暫定的な提起としたい。
(1)危機状況の「危機」を冷静に判断し、「住民自治の根幹」としての議会を作動させること、その際通常状況下で培ってきた「議会からの政策サイクル」が有効であることを指摘している。議会活動は、「不要不急」ではないことも強調している。なお、危機状況では常に執行機関がいるのは異常だということも改めて確認した。そもそも議会は議員同士の集合体(執行機関を呼ばないことが第一義的)である。執行機関を呼ばないで審議すればよい。質問は目立つが、将来への個人的・会派の提言である。質問は重要であるが、危機状況では優先順位からすれば上位ではない。もちろん、危機状況下では議会としての提言は執行機関の施策を充実・豊富化する意味で重要である。
(2)第32次地制調の動向とは別に、議員立法によって町村の長および議員の公営選挙の制度化(条例に基づき、供託金制度を導入し選挙候補者のポスター作製や街宣車にかかる経費を公費で負担する)が議員立法で提出されている(6月2日衆議院、8日参議院通過)。町村のみ公営選挙ははずされていた。この改正にあたって大きな役割を果たした自由民主党「選挙制度調査会」にも注目しておきたい。
(3)通常状況での法改正も同時に考える必要がある。別途検討したい(全国市議会議長会(2018)、全国町村議会議長会(2018)、全国都道府県議会議長会(2020)、参照)。
(4)筆者は、議会の政策法務として、議会への政策法務(議会基本条例等議会に関する政策法務)、議会による政策法務(議案審査、議員・委員会提案条例の政策能力としての政策法務)、とともに議会からの政策法務(各省庁や国会に対する意見書提出による法律改正を行う政策法務)を提唱している(江藤 2011,2019)。本小論は、その中の「議会からの政策法務」に該当する。もちろん前二者の政策法務を作動させつつの提案となる。
(5)国会においては、まさにオンライン化が必要だと思われる(議事堂の換気状況は格段によいとのことではあるが)。ただし、憲法上の定足数の出席を「議場にいる」ことを想定しているために、憲法が足枷となっているという議論もある「オンライン化 腰重い国会―憲法理由?一部議員提案も議論進まず―」『朝日新聞』2020年5月13日)。危機状況での国会運営の活用もあるが、閉会中に臨時会を招集せざるを得ないことを想定すれば、国家にウェブ議会の活用の議論を進める必要があると思われる。
(6)この「出席制限」には、議員の出席は責務という理由から反対意見もあった。参議院の本会議では、席を離すことで全議員が出席する方針を確認している(『朝日新聞』2020年4月10日付)。