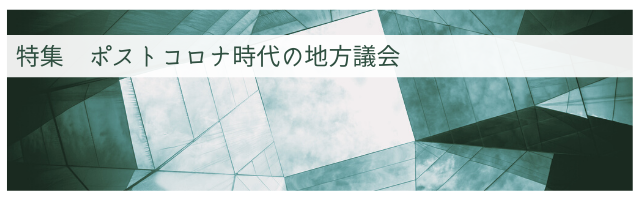ウェブ議会活用の視点と可能性
(1)暫定的な提案
ウェブ議会の活用及びそれを可能とする法制度を考えたい。筆者の立場(結論)を最初に明記しておこう。
①危機状況での活用
危機を冷静に判断することが肝要である。そのうえで、議場に定足数の人数が参集できない、あるいは定足数は満たしてもその残りの議員が参集できないといった場合には、ウェブ議会の開催を可能とすることが必要である。委員会等はもとより本会議開催をウェブで可能とすることは必要である。本会議をウェブで行うことは法改正を必要とする。
ただし、ウェブ議会開催が可能となっていても、ウェブ議会すらも開催できる状態ではないということも起こりうる(議員の多くが被害に遭う、致死率の高い感染症が急激に拡大する、など)。いたずらに危機をあおって、本年3月議会のような「傍聴や一般質問の中止」といった冷静さを欠く判断をするべきではない。ウェブ議会も作動できないような「緊急事態」には、専決処分を作動させることになる。その条件を日ごろから確認しておく必要がある。なお、首長等をできるだけ応召しないことは言うまでもない。
②通常状況での活用
議会は、「公開と討議」の場である。危機状況においても、できるだけ議場(青空議会、出張議会を含めて)で開催することが前提である。とはいえ、条例や会議規則で設定されている会議(委員会等)でも、日ごろ行われる下準備等については、メールで行われることもあり、そのウェブ版としての活用はすぐにでも可能である。委員会等をウェブによって行うには、条例や会議規則に規定する以前に、その根拠を示さなければならない。
なお、たとえば委員会等の定足数を満たし開議されていても、産休・育児・介護等で欠席している議員の意見を聞くためにウェブを活用することは可能である。本会議でも同様である。ただし、定足数に加えたり、表決権を与えることは、現行法でも委員会等での可能性を探ることはできるとしても、本会議では困難である。また、議員のなり手不足解消の観点からも、産休・育児・介護等で欠席する可能性の高い、特に若年層の議員を増加させるには、法改正も今後必要かもしれない。そういった提案を筆者は否定はしないし応援はするが、まずもって運用で行い、法改正としては危機状況におけるウェブ本会議の活用から始めるのが運動論として妥当だと考えている。広範な賛同を得て改正に至るには時間がかかるだろうという意味だけなので、可能だという議論に正当性があれば意見を変更する場合もある。
【現行法におけるウェブ議会の射程と法改正の課題】
■現行法解釈の視点
自治体による法令解釈権は尊重したい。「議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。」(北海道栗山町議会基本条例25②)といった条文が、議会基本条例に規定されることはまれではない。自主解釈権を大いに活用したい。
なお、地方自治法を想定しつつ「禁止されていないものは自由にやっていいのか」という問いに、総務省自治行政局行政課長は「具体的には、個別に考えなければいけませんけれども、一般論としてはそういうことになります。」(第29次地方制度調査会第11回専門小委員会)と答えている。総務省が解釈権を有しているわけではないが、本稿と同様の視点である。この解釈は新しい時代に即したものであり、大いに歓迎すべきである。国会も両院の規則があり、自立権は当然有している(多数派尊重の民主主義の制限)。地方議会も会議規則を設けているのは、同様である(条例制定改廃の直接請求の対象からは除外)。
ただし、自治法等による法律の縛りはある。ウェブ本会議は争点となるであろう。
■現行法ではウェブ本会議は困難
危機状況に限定したとしても、本会議をウェブで開催することは現行法とバッティングする可能性がある。ウェブ本会議を可能とするためには、法律にウェブ議会活用を明記、担保することが必要である(地方制度調査会答申等による規範解釈の変更も可能であるが、法改正が順当だと思われる)。
① 現行法下においてウェブ活用は、委員会等の可能性はあるが、本会議ではできない。委員会等は組織内会議であり、それぞれの議会に設置運用が委ねられている。本会議である。なお、総務省行政課長からの通知では、新型コロナという危機状況に限定して委員会等で可能としていた(後述)。少し広く解釈して、危機状況における委員会での活用からまず進めたい。
② 本会議は、現行法上、議場を前提にして設計されている(青空議会等は可能)。たとえば現行法の定足数(出席)(自治法113)、公開原則(自治法115)、表決(自治法116)はウェブ議会を想定していない。かりに出席、表決の場をクリアーしたとしても公開には問題がある。時代による規範の変更は、法律改正が順当である。
③ 表決の瑕疵が住民訴訟等で裁判になった場合(予算等の議会の議決は自治体の重要事項)、現時点ではウェブ議会で勝訴する保証はない(社会的価値の変更を促すのは、まずもって法律改正が必要である。とりわけ、総務省から「技術的な助言」であれ「通知」が出された中にあっても勝訴する保証は希薄である)。
(2)ウェブ議会を考える射程
次に通常状況での活用を検討する。テレワークやオンライン会議の広がりは、日本社会を大きく変えることになる。今回の危機状況の中で、急速にオンライン会議の実践が行われ、可能性が広がっているのはよいことである。ただし、議会においては、その特徴を踏まえた活用を「冷静に」考える必要がある。
なお、以下でいう「議場」は、ウェブを活用した仮想空間としての議場ではなく、議事堂を構成する議場(青空議会を含めて物理的空間を有する場)である。ウェブ議会を考えるうえでの射程を確認しておきたい。
①合議体という特性を生かした活用の可能性
トップダウンで物事を決めるのではなく、議決権限を行使する合議体を充実させるという観点からウェブ議会の活用を考える。合議体には、ウェブ議会が適合することをまず論証することが必要だろう。「公開と討議」を、その存在意義とする議会に、ウェブ議会の推進力として単なる「時代」といった抽象的なものを設定して納得するのではなく、住民自治を進める際にどのような活用が可能かを考える必要がある。
②通常状況と危機状況との活用
危機状況で本格的に議論の俎上にのぼってきたが、通常状況下でもウェブ議会は活用できると思われる。逆に、通常状況での活用が危機状況でも生きる。
③部分的活用と全面的活用
「部分的活用と全面的活用」の意味は、委員会等での活用と本会議での活用という意味ではなく、委員会においても産休・育休・介護休で欠席せざるを得ない議員の参加を促すことを想定している。日本の国会でも行われているような、定足数を確保しつつ別の場所から議会をウェブで確認しつつ、自分の質問や表決の際には議場に参集するということも想定できる。会議規則等の変更はなく、運用で可能である。それに対して、定足数を確保して委員会等を開催しつつ、別の場所からの委員の出席を可能とするには会議規則で規定する必要がある。とりわけ、平成の大合併で広域化した自治体において、公聴会や参考人制度の実施を、ウェブ議会を活用して行うことは日常的に進めたい。
(3)ウェブ議会の留意点
筆者は危機状況におけるウェブ本会議を可能とする法改正を提案している(5)。早稲田大学マニフェスト研究所は同様に法律改正の「意見書」提出運動を展開している(後掲資料参照)。また、全国都道府県議会議長会も同様な趣旨で法律改正要請を決議している。筆者の結論を再確認したい。
① 議会内会議をウェブで実施することは会議規則等で規定すれば可能である。また、非公式・準公式な会議(打合せ)ならばまったく問題ない。ただし、ウェブ議会のメリットを示さなければならない。
② 危機状況において本会議でもウェブ活用を可能とすることについては賛同する。ただし、現行自治法下では適法とは断言できない。意見書等により改正を促す。委員会等と同様、ウェブ本会議のメリットを示すことが必要である。
③ 部分的な活用は大いに賛同する。その場合、いくつかの活用の仕方が想定される。議場での定足数を満たしている場合で、議場に参集できずウェブを介してしか意見を述べることができない議員の意見を聞く際、これは休会中であれば問題ない。ただし、議事録には掲載されないので、掲載のルールを制度化する必要がある(それぞれの議会の会議規則等に明記)。議場での定足数を満たしていない場合、委員会等ではウェブを活用することで成立させることはできる(条例・会議規則等の改正によって)。