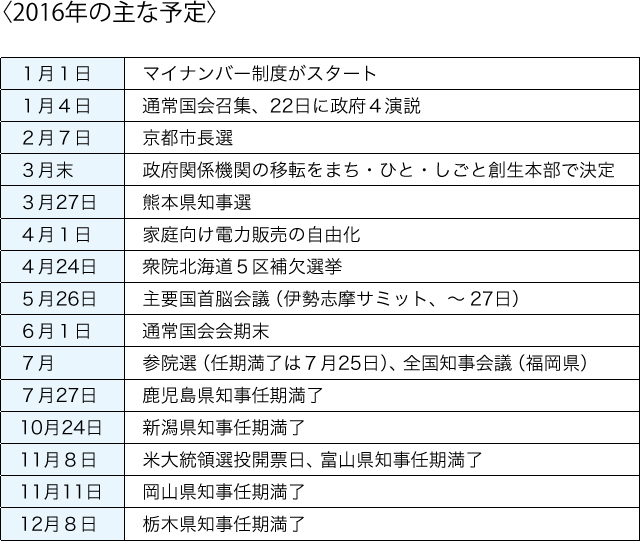一般社団法人共同通信社編集委員兼論説委員 諏訪雄三
今年夏の参院選に向け国会論争が早くもヒートアップしている。国会では与野党が甘利明経済再生相の辞任に加え、デフレ脱却や雇用の改善などアベノミクスの成果、環太平洋連携協定(TPP)対策の在り方、安全保障法制の強行採決の是非、憲法改正を含むこの国の未来を中心に議論している。
「アベノミクスの効果を津々浦々に」として安倍晋三政権が訴えてきた「地方創生」は本格実施の年である。ところが参院選に向けては、派手なアピールは感じられない。2014年12月の衆院選、2015年4月の統一地方選のときとは違う。地方向けの参院選の旗印は「地方創生」ではなく、「一億総活躍」に取って代わった観さえある。地方創生を中心に今年の地方政策の見通しを分析したい。
総合戦略で横展開
まず地方創生の動きを振り返っておこう。地方創生は2014年5月に増田寛也元総務相ら日本創成会議が、半数の市町村が「消滅可能性都市」になると発表した直後から、安倍政権の最重要課題に浮上した。第2次改造内閣が発足した2014年9月以降、首相がトップの「まち・ひと・しごと創生本部」を設置、石破茂氏を地方創生担当大臣に任命した。
「地方創生は日本創生だ」、「人口減少は静かな有事だ」、「これに失敗すれば、国が危ういという危機感がある」といった石破担当相の物々しい物言いもあって、政策は浸透した。2014年11月に「まち・ひと・しごと創生法」を成立させ、12月には「50年後に1億人程度の人口維持を目指す」という長期ビジョンと2020年を目標とした総合戦略をつくっている。
都道府県や市町村は2016年3月末までに、それぞれ総合戦略をつくることになる。例えば、沖縄県は2015年9月、総合戦略として「人口増加計画(改定版)」を作成した。2025年をピークに減少に転じる人口を出生率のアップ、移住者の増加によって139万人だった2010年の人口を2050年には160万人、2100年には200万人にまで引き上げようという内容だ。
もちろん、沖縄県のように人口増加を見込んでいる自治体は数えるほど。北海道根室市の場合は、2010年の人口2万9,000人がこのままでは2060年には1万2,000人にまで減ると想定、減少対策によって1万5,000人にとどめる目標を立てる。多くの自治体が根室市と同様に人口減少をどう抑えるかが最大の課題となる。
総合戦略の作成は、将来の人口を推計した上で長期計画を立てることだけに「人口減少が自分の自治体でも確実に起き、そのインパクトが大きいことを知る」という作業だ。先駆的な自治体では当然、減少を意識して政策を立てていたが、これをすべての自治体に認識してもらう点では意義があるだろう。
地域の活性化策が失敗してきた原因として安倍政権は、地域特性を考慮しない「全国一律」の手法などを総合戦略の中で挙げている。そう分析しながらも全自治体に横並びで総合戦略の作成を迫った上で、他の自治体で成功した施策のいわば横展開を迫ることが地方創生の姿である。ある意味では自己矛盾がある政策の展開ともいえる。