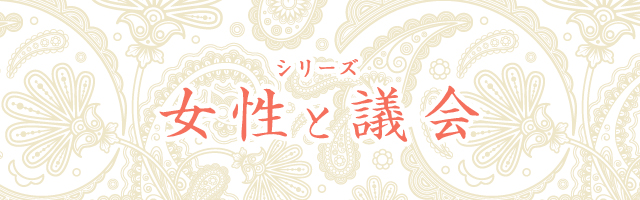おわりに──「立候補公式」試論
さて、再び、そのポリンピック…。ワールドカフェで直接議員等と対話をしながら、また、パネル・ディスカッションを聴きながら、改めて強く認識したことがある。女性議員の多くは、もともと政治家になることを志していたわけではない、“結果として”今、議員の立場にあるのだ、と(40)。では、その結果にはどんな要因が働いているのか。これに答えんとして、閉会挨拶時に前のめりで披露したのが「立候補公式」なるものである。「公式」と呼ぶにはあまりに雑すぎる代物ではあるが、図らずも多くの出席者に共感いただいたこともあり、ここに(若干の加筆修正を試みた上で)掲載することで、本稿の締めとしたい。
【立候補公式】
「S×P+O-C>0」のとき、人は立候補しようとする
S. ソーシャル:(議員になる前の)社会課題解決志向度と実践度
P. ポテンシャル:議員の可能性(or/and民の限界)への認識度
O. オポチュニティ:きっかけ、推す声、仲間、経歴 等
C. コスト:周囲の理解、直接費用、機会費用、将来不安 等
筆者作成
(1) ただし、地方議会については小論をものしたことがある。参照、「議会ウオッチのススメ─モノサシ批判に応える」Voters №22(2014年)、及び、「(仮)地方議会論再考」出原政雄=竹島博之=長谷川一年編『(仮)原理から考える政治学』法律文化社(2015年4月刊行予定)。
(2) 2014年10月末時点では、長崎、島根、石川の3県で実施されている。本キャラバンの趣旨を石川版のチラシから確認しておこう。「生活に直結した課題に取り組む地方議会で、いま少数の女性議員はどんな活動をしているでしょうか。その奮闘ぶりを聞き、なぜ女性議員が必要か、どうしたら増やせるか、ご一緒に考えましょう」。
(3) ちなみに、第1位(したがってキャラバン第1弾)の長崎は、筆者の出生地である。これまた縁?
(4) “ポリ”主催の“コン”パ。参加者は、主に議員と学生である。ねらいとしては、飾らないノミニケーションを通じて、若者と政治(家)との距離を縮めること。2013年5月に開始し、本稿執筆時点で計7回、延べ約200名の参加を得ている。H県議はほぼ皆勤賞である。
(5) 正直にいえば、かの市川房枝の名を冠するほどの団体であるということから、また、後述する「女性会議」での経験もあって、女性と政治センターは「女性」に固執されるものと(甚だ勝手ながら)予想していた。
(6) 執筆陣のうち4名(住田啓子氏、井上温子氏、大河巳渡子氏、久保公子氏)はポリンピック登壇者でもある。
(7) 「島根レポート 5月11〜12日 若者と女性の手で政治をよくしよう」女性展望Vol.669(2014年)16〜18頁。
(8) 「市民部門」最優秀賞。参照、http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/award/。
(9) 「日本女性会議2014札幌」のウェブサイトによれば、「男女共同参画に関する国内最大級のイベント」である。そのねらいは、「男女共同参画社会の実現に向けて課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流促進や情報ネットワーク化を図ること」にある。参照、http://www.joseikaigi2014sapporo.com/。
(10) もっとも、筆者はマニフェスト自体を否定するものではない。ブームが去った今でもなお、その意義、特に、政策の優先順位付け及び検証可能性の担保といった機能を高く評価している。
(11) 候補者個人もマニフェストを掲げることはあるが、ここでは話を政党に絞る。
(12) 当時筆者は、これを「是々非々投票」と命名する程度で、具体的な制度設計まで詰めて考えていなかった。後に、鈴木健による「伝播委任投票システム」なる構想を知る。基本的な問題関心は近いものの、その精緻さは比べるべくもない。同『なめらかな社会とその敵』勁草書房(2013年)第7章を参照されたい。
(13) 正確にいえば、その前に、筆者の主宰する「行政学ゼミ」生(3・4年)に話を振った。本ゼミのモットーは、「政治行政や地域社会の抱える課題を解決するべく、単に机上で本から学ぶ(=座学)だけではなく、自ら動く(=実践)」である。しかも、時は、歴史に残るであろう総選挙の直前。筆者には「(政治行政を学ぶ)学生が動かなくてどうする!?」との強い思いがあった。が、ゼミ生からは何の反応もなく…。こういう事情もあって、1年生を(筆者には珍しく?)多少強引に誘ったのである。
(14) いうまでもなく、学生にとっては、こういったフィールドワーク自体が大きな学びとなった。特に、調査対象者に繰り返し断られ、心が折れ(そうになっ)た経験は、大きな糧となったようである。
(15) 回答数は783件。
(16) A~Eの分野とは、経済対策、社会保障、子育て・教育、地域活性化、外交・安保、行財政、である。
(17) なお、アンケートでは政党自体への支持も問うている。回答者の38.4%は民主党支持、自民党支持は27.6%。それでも「外交・安保」分野の政策には、これほどまでの開きが見られるのである。
(18) 退屈極まりない(?)データ入力・集計作業は、1年生にとっては初めての夏休みを随分とつぶすこととなった。
(19) 行政学ゼミは、ほぼ毎年、大学祭において研究室公開という名のカフェを開く。その中で、学生(ゼミ生に限らない)による社会貢献活動等の発表をすることがここ10年ほど恒例となっており、ポリもその常連である。
(20) 前回の反省を踏まえ、今回は(「一本釣り」はやめて)ひとまず次のような意向確認を行った。設問は「今度の参議院選挙、『ポリレンジャー』が復活するとしたら、どう思いますか?」、選択肢は「⒈ 中心メンバーとして活動したい ⒉ 誰かがやるなら手伝ってもいい ⒊ 特に関心ない ⒋ その他」。すると、約100名中3名が「⒈ 中心メンバーとして活動したい」と名乗り出たのである。ちなみに、選択肢「⒉」を選んだ者は20名ほどであった(その多くは、当日限りの調査ボランティアとして参加)。
(21) 当時、メンバーが作成した企画書から。
(22) 参院選への関心度、投票意向、棄権理由などを問い、不在者投票の認知度が低いこと、住民票を移していないため現在の居住地に選挙権がない学生が多いこと等が分かった。
(23) ただし、最優先する政策分野を問う質問を追加するなど多少の改良は加えている。なお、調査地点も1か所増やし、結果的に、回答数も901件と昨年を上回った。
(24) ポリとしては初めて「ワールドカフェ」を取り入れた。これは、カフェのようにリラックスした雰囲気の下、お題(テーマ)もメンバーも替えながら対話を繰り返すワークショップ方式である。その後、ポリでは、後述する「女性会議」はじめ、様々な場面で活用することとなる。
(25) 参照、前掲注(19)。
(26) いうまでもなく、あくまでその時点での、我々から見た一方的な見方である。今となってはむしろ、総じて謝意と敬意の方が強い。
(27) 当初案は「ぼくらが“政治のおばちゃん”についてけないワケ」であった。しかし、無用の反発を受けるおそれがある(そしてそれは決して本意ではない)こと、我々の射程は(狭義の)「政治」にとどまらないこと、表現自体がいくらか品を欠くこと等から、あえてぼかすこととした。
(28) その他、男女共同参画関係行政職員と島根県内の地方議員も調査対象に含めている。
(29) 詳細は「日本女性会議第4分科会【資料】」。参照、http://poliranger.wix.com/poliranger#!untitled/c1gf3。
(30) ここでは、「女性は立候補しにくい」、「女性は選挙で勝ちにくい」、「有権者は男性議員を好みがちである」という見解に肯定的な回答を「社会」に原因を求める見方として、他方、「そもそも議員になりたい女性が少ない」、「有権者は投票に当たり性別を重視していない」とする見解をその逆として捉えている。
(31) 以下の一文から拝借した文言である。「ジェンダー概念を『知っている者』から『知らない者』へと啓蒙、啓発する、そうした『キヅカセ・オシエ・ソダテル』活動にばかり偏っていてよいのか」(山口智美=斉藤正美=荻上チキ『社会運動の戸惑い─フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』勁草書房(2012年)334頁)。なお、この著書と出会ったのは女性会議の後であった。専門家によるかかる指摘に、改めて意を強くしたところである。
(32) 詳細は、日本女性会議2011松江実行委員会「日本女性会議2011松江大会報告書」(2012年)。
(33) お題は、以下の5つ。①第Ⅰ部について何でも…、②「女性の政治参画」は遅れているか?、③女性議員は増えた方がよい?、④“運動”はやりすぎ?、⑤若者“に”に何を求める? 若者“は”何を求める?。
(34) 2013年度の活動概要については、さしあたり新藤正春(ポリ代表)の小論「若者と政治を近づけたい!」(選挙2014年9月号)を参照されたい。
(35) 松江市長のマニフェスト(2009年選挙時)を評価したもの。中間時点(2012年12月総選挙の日!)では、市長を招いての公開討論会も実施した。参照、ポリレンジャー「松江市政の通信簿─市長のマニフェスト検証」(2013年)。
(36) ドイツからの留学生マルコが抱いた日本の選挙(運動)への違和感から生まれた座談会。若者を中心に、彼我の選挙や政治教育等について議論した。参照、「投票率の向上に向けて大学生が討論」Voters №5(2013年)53頁。
(37) 2013年参院選時、中学3年生を対象に実施したもの。可能な限りリアリティを追求した。すなわち、まさしく選挙期間中に、実際の候補者・公約を材料として、選管から拝借したホンモノの投票箱や記載台を用いて、実施したのである。結果、中学生の政治に対する関心は顕著に向上した。参照、「ポリレンジャー2013年度活動報告」(2014年)2〜20頁。
(38) 先述した「マニフェスト大賞」は「通信簿」に対するものであったが、それも含めて活動全般については、「平成25年度 明るい選挙推進優良活動賞」も受賞したところである。
(39) 参照、前掲注(4)。
(40) このことは必ずしも女性に限られないようである。ある調査によれば、議員の9割以上は「以前から議員になりたかった」わけではない。動機・きっかけで最も多かった回答は、「自分の住んでいる町村をよくしたかった」(61.4%)であった。参照、今後の町村議会のあり方と自治制度に関する研究会「町村議会議員の実態調査と意識」(2013年)。