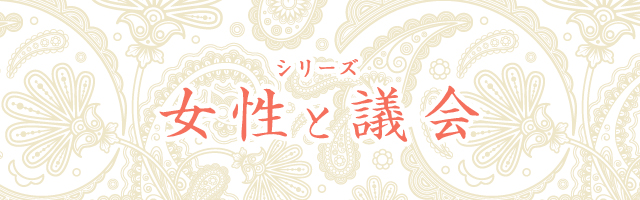ポリ誕生 ──「政策別アンケート」からの出発
日本政治史上初の本格的な政権交代をもたらした2009年夏の総選挙。ポリが生まれるのはその直前である。当時、筆者には、ブーム真っただ中の「マニフェスト(型選挙)」に対する疑念(10)があった。端的に、政策への支持と投票先とのズレである。通常政党(11)は、マニフェストの中に、様々な政策を比較的詳しく記す。が、よほど熱烈なファンでもない限り、その“全て”を支持するということはないであろう。つまり、A政策についてはX党だが、B政策はY党の方がよい、といった立場が一般的ではないか。しかし、投票は特定の政党に対してしかできない。マニフェストは、その意味において、読めば読むほど悩ましくなるものなのである。結果として、「政権」選択と個別政策への支持の間にもズレが生じる。こういった限界を何とかできないか。単純に発想すれば、一つひとつの政策を(も)問うような選挙制度(12)があればよいであろうが、そのような制度が一朝一夕にでき上がるわけもない。
そこで次善策として考案したのが、政策別の有権者の支持を問う「出口(でのアンケート)調査」である。これを「政策別アンケート」という。さっそく1年生のSに“半ば強引に”(13)声をかけ、彼とその仲間5名ほどをランチに誘った。ここに初代レンジャーがほぼ確定することとなる。その後、彼らは(たびたび「あのランチ、高くついたわぁ~」とグチりながらも)、選挙管理委員会との交渉、調査ボランティアの募集、チラシづくり、説明会の開催、マスコミ対応など、時間も経験もない中、精力的に準備を進め、投票日当日(8月30日)、松江市内3か所での出口調査をなし遂げたのである(14)。
結果を一瞥してみよう(15)。メインの問いは「分野(以下のA~E)(16)別に、あなたが最も良い政策を提示していると思う党に○をしてください」である。例えば、「子育て・教育」。民主党の目玉施策であった「子ども手当」の影響であろうか、その支持率は35.8%、自民党17.7%のほぼ倍であった。他方、「外交・安保」を見ると、自民党の政策に対する支持が圧倒的に多い。民主15.1%、自民45.3%と、実に3倍もの差があるのである。後知恵ながら、島根の有権者は、この分野での後の迷走ぶりを予想していたともいえよう(17)。ともあれ、先述した「ズレ」は見事に裏付けられたのである。こういった学生たちの試みは、マスコミ等からの注目度も比較的高く、「若者と政治」をめぐる状況に多少なりとも一石を投じることができたというも強弁ではあるまい。
だが、初代ポリは間もなく自然消滅する。主たる要因は、(筆者の指導不足を除けば)2つ。第1に、勧誘が強引であったせいか、あるいは負担が想定以上だった(18)ためか、メンバーのモチベーションが持続しなかったこと。
 「出口調査(政策別アンケート)」の様子(2009年8月30日)
「出口調査(政策別アンケート)」の様子(2009年8月30日)
 「若者と政治について考える対話イベント in 淞風祭」の様子(2010年10月9日)
「若者と政治について考える対話イベント in 淞風祭」の様子(2010年10月9日)
第2に、調査結果の報告会を予定していた「淞風祭」(島大の学園祭)(19)が新型インフルエンザの影響で急きょ中止になったこと。学生自らの内発性と、節目節目での目に見える成果の重要性を改めて痛感した次第である。しかし、それでも…。
2010年7月の参院選まであと1か月と迫った頃、再び(別の)島大生が立ち上がる(20)。いわく「あれだけ関心の高かった昨年の総選挙でも、20代の投票率は僅か49.45%と、半分にも満たないほどの低さだった…。これからの社会を担っていく若者がこういう状況であることは、やはり問題だ!! この状況を(自ら若者である)私たちの手で少しでも改善し、若者の政治参加を進めるべきだ!」(21)。ここに2代目ポリレンジャーが誕生することとなる。
最初に行ったのは、「選挙」に関する島大生の意識調査(22)である。その後、投票日当日(2010年7月11日)には、前年と同じく(23)「政策別アンケート」を実施。そして10月には、(この年は無事開かれた)大学祭の中で、「若者と政治について考える対話イベント in 淞風祭」を催した。この会は、二部構成となっており、第Ⅰ部では「政策別アンケート」の結果報告を、第Ⅱ部では、「若者と政治」について考えるワークショップを行った(24)。そこでは、参院選で苦杯を喫したI議員(現島根県議)と学生との激論(?)も見られ、大いに盛り上がったところである。
「女性会議」顚末記──「素人」からの提起
女性会議との接点が生まれるのは、その直後である。ポリイベント後に我が行政学ゼミの「カフェ」(25)に立ち寄られたK松江市議(女性)から、「翌年10月に女性会議がここ松江で開かれる。『女性の政治参画』に関する分科会も設けられる予定である。ポリで担ってみないか」と誘われたのであった。その場では回答を保留し、後日メンバーに相談。異を唱える者もいたが、「政治参加」という点ではポリのミッションとも共通していること、(これほどまでの大舞台、「度胸試し」も含め)我々にとっての学びも大きかろう、ということから、引き受けることとした。
とはいえ、全員素人。今のままの知識量ではとても分科会の運営などできそうにもない。そのため、書物を手にとったり、関連講座に出かけたり、女性議員にインタビューしたり、メンバー間でディベートしたり、それなりに勉強を重ねた。当初の企画案でも、こういった取組を通じて「社会化」されていく学生の姿を1年間追い、分科会当日には、かかるプロセスの記録と「成長」したレンジャーによる政策提言をお披露目する、としていた。
しかし、これは途中で大幅に変更される。いわば「社会化」を断念するのである。主たる理由は2つ。ひとつは、「しょせんは素人、付け焼き刃の知識で、わざわざ全国から集う『玄人』たちを満足させられるのであろうか」との迷いをなかなか払拭し得なかったこと。今ひとつは、女性会議自体に対する不満ないし疑問である(26)。会議の運営の仕方に首をかしげたくなることもしばしばであったし、加えて、学生たちは、様々な場面でその無知さ加減や経験不足等を(半ば一方的に)責められていた。これが、(女性の「政治参画」推進も含め)「フェミニズム」のあり方そのものへの疑念へとつながっていくのである。
それを決定的にしたのは、ある情報であった。「『おーいお茶』(という「伊藤園」の商品)を、女性蔑視に当たるとして糾弾している人がいる」というのである。一同、ひどく驚がく。理由は分からなくもないが、あまりに過剰な対応ではないか…。我々の違和感はピークに達し、士気の低下も著しかった。けれども他方で、大きな気づきがもたらされたのもこのときである。まさしく、このような感覚の「ズレ」や「上から目線」的な態度こそ問題なのではないか、だとすれば、我々はむしろ「素人」ぶりをウリにすべきではないか、と。そして間もなく、企画内容も腹も決まる。
主題「女性の政治参画」に添える副タイトルは「世代間“等”ギャップに向き合う」とし、キャッチコピーには(やや挑戦的な?)「ぼくらが“ついてけない”ワケ」(27)を選んだ。爾後、活動の重点は、上記のズレを検証するためのアンケート調査に移る。メインの対象は、「女性」問題に熱心な「玄人」と関心の薄い「素人」(28)。前者にはこの女性会議運営委員会委員を、後者には島大生を選んだ。以下、調査結果のごく一部を紹介しておこう(29)。
まずは、先の「おーいお茶」について。この商品を糾弾する姿勢に「ついてけない」学生は75%にも上った。他方、女性会議関係者の半数以上は特に違和感を覚えていない。次に、「なぜ女性議員は少ないのか」、その理由を問うてみた。全体的に、女性会議関係者は有権者の意識など社会の側にその原因を求める傾向が強いが、学生はさほどでもない(30)。また、議員のあるべき男女割合については、女性会議関係者のほぼ9割が「5:5」と回答したのに対して、学生でそう考えているのはほぼ半数であった。
このようにして、女性会議関係者と学生との間には一定のギャップがあることが明らかとなった。もちろん、これ自体は善しあしとは関係ない。なるほど無関心や無知があるとすればそれは克服すべき課題ではあろう。けれども、そのことを頭ごなしにとがめ、正しいことを「キヅカセ・オシエ・ソダテル」(31)といった姿勢では、若者(でなくとも…)は“ひく”ばかりである。まずは、その差異をしっかりと受け止め、関心や立場等を超えて互いに理解し合おうとすることが重要ではないか。
そして我々は、かかる認識から分科会プログラムを改めて検討し、次のような構成にすることとした(32)。第Ⅰ部は、上記調査結果のプレゼンである。ねらいは、ギャップの事実を参加者(=いわば「玄人」)と共有することにある。第Ⅱ部は、ワールドカフェ(33)。若者と玄人とが同じテーブルで、フラットかつフランクに対話する場を創出するためである。結果はどうであったか。直接いただいた声やアンケートなどを頼りにする限り、それなりに好評を得たようである。正直、一同ビビリながら臨んだ会であったので、感慨ひとしおであった。
その後、ポリは活動の幅を広げていく(34)。例えば、「松江市政の通信簿」(35)、「マルコの“投票”見聞録」(36)、「模擬投票 in 松徳学院」(37)など。こういった「実績」(38)と「ポリコン」(39)なる場があって、H県議との「縁」が結ばれ、「ポリンピック」へと結実したわけである。