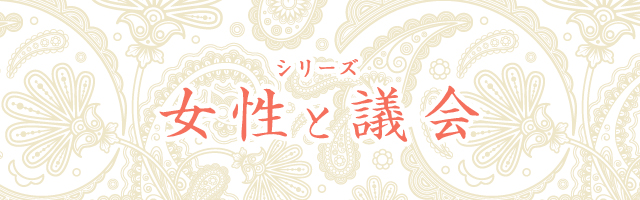女性議員が少ない理由と背景
女性議員の割合については、国会で10.8%(衆議院8.1%、参議院16.1%、2014年9月24日現在)、地方議会で11.6%(都道府県議会8.8%、市区議会13.6%、町村議会8.7%、2013年3月31日現在)にとどまっている。山形県は、全国的に見ても地方議会における女性議員の割合が低く、県議会4.5%、市議会12.0%、町村議会6.6%となっている。
このようなことから、筆者は、山形県において、なぜ女性議員が少ないのかの理由と背景について探るため、2009年に山形県内の政党支部の幹部を対象にしたヒアリング調査及び山形県内の女性地方議員を対象にした郵送アンケート調査を実施した。
その結果によると、女性議員が少ない理由と背景としては、次の点が挙げられる。
女性議員が少ない理由
⒈ 配偶者との関係:性別役割分担意識が強く、女性に立候補を要請しても配偶者が反対する。
⒉ 親の世代との関係:同居しているしゅうと・しゅうとめが、嫁の立候補に反対する。
⒊ 就業環境との関係:夫の所得水準が低いことや3世代同居率が高いことから、子どもを同居する親に預けての共働きが多いが、正社員や管理職ではなくパートなどで働くことがよしとされる。
政党支部の幹部、女性議員の双方から、政党による女性議員の増加方針や数値目標の明文化、クオータ制や比例名簿登載順の男女交互化については否定的な意見が大半であった。
一方、女性議員が多い理由と背景を探るため、女性議員の割合が高い神奈川県の鎌倉市議会と大磯町議会の女性議員を対象にしたヒアリング調査も実施した。その結果によると、女性議員の割合が高い背景としては、住民の自発的な活動が盛んで問題意識が高い、女性の立候補を妨げない風土がある、教育水準が高い、首都圏であることが指摘できる。女性議員が多い理由で重要なのは地域活動への主婦層を中心とした女性の積極的参加で、女性議員の増加に寄与するようである。鎌倉市議会・大磯町議会の女性議員の支持母体としては、自治会・町内会、住民運動の有志、PTAが多く挙げられた。
地方議会の女性議員を増やすための戦略
地方議会議員の多くは無所属であり、このことからは政党による数値目標の明文化やクオータ制などは女性議員を増やすための方策とは直接的にはなり得ない。政党支部の幹部ヒアリング、女性議員へのアンケート調査、鎌倉市議会・大磯町議会の女性議員のヒアリングの結果等から見ると、むしろ、地域社会における人々の意識の改革(女性の立候補を妨げない、むしろ助長するような文化への改革)を進めながら、自治会や町内会、PTA活動などの地域活動への女性の積極的参加により地域社会で支持を得て選挙で当選していくことが、地道ではあるが、有効な戦略であろう。
女性議員の増加を促進する選挙制度としては、大選挙区で選挙区定数が多い場合や全国で単一の政党名簿を用いる制度が挙げられるが(金子、2010:156)、地方議員には無所属が多いことから、単一の政党名簿を用いる制度はなじまない。最近進んでいる地方議会の議員定数の削減は、選挙区定数を少なくし、女性の選出を妨げる方向に働く。
なお、鎌倉市議会・大磯町議会の女性議員のヒアリングの中では、議員報酬が少ないと常勤職を持っている男性が挑戦するには難しいため、女性が出やすいかもしれないとの声が聞かれた。神奈川県の市町村会議員調査を用いて、議員報酬の低い選挙区の方が女性の当選率が高いと分析し、議員報酬が少ないと女性が選挙に出やすいとする研究もある(大山、2007:17)。
まとめると、地方議会において女性議員を増やすための戦略は、以下のようになる。
女性議員を増やすための3つの戦略
戦略① 女性が地方議会議員選挙に立候補するのを妨げない、むしろ促進するような地域の文化を醸成していくこと。とりわけ、女性の立候補を後押しするように家族の考え方を変えていくこと。
戦略② 女性が自治会・町内会、PTAなどの地域活動に積極的に参加し、信頼を得ていくこと。
戦略③ 地方議会の議員定数を増やすこと。
これらの3点が挙げられるが、どれも実現に時間がかかるものであり、これらの戦略を進めていけば地方議会の女性議員は徐々に増えていくであろうが、急増するというわけにはいかないだろうと思われる。
⑴ 調査対象は2011年11月末現在の全国933町村の全町村議会議員1万1,687人であり、調査の方法は各町村議会を通じて調査票を各議員に配布し、調査票に記入後、全国町村議会議長会まで無記名で郵送提出してもらう自計方式であった。調査員調査ではないが、各町村議会を通じて調査票を配布していることから、調査票は調査対象たる全ての町村議会議員の手元に渡ったものと考えられる。調査の実施期間は2011年11月28日から12月28日までの1か月間であり、有効回収の調査票は6,696通、有効回収率は57.3%であった。
⑵ 母集団である全国の町村議会議員について男女別・年齢別に全数調査している町村議会実態調査の結果と、町村議会議員意識調査の結果を比較したところ、母集団の属性と回収された調査票から見た回答者の属性の間に大きな偏りは認められなかった。
■参考文献
◇大山七穂(2007)「女性の政治参画を促進、阻害する構造・制度的要因:神奈川県市町村議会議員調査から」東海大学紀要文学部88、1~26頁
◇金子優子(2010)「日本の地方議会に女性議員がなぜ少ないのか─山形県内の地方議会についての一考察─」年報政治学2010-Ⅱジェンダーと政治過程、151~173頁
◇金子優子(2013)「町村議会議員の現状」全国町村議会議長会 今後の町村議会のあり方と自治制度に関する研究会『町村議会議員の活動実態と意識~町村議会議員意識調査結果をふまえて~』6~18頁
◇Norris, Pippa(1993) Conclusion: Comparing Legislative Recruitment, Lovenduski, Joni and Norris, Pippa eds., Gender and Party Politics, London, Sage