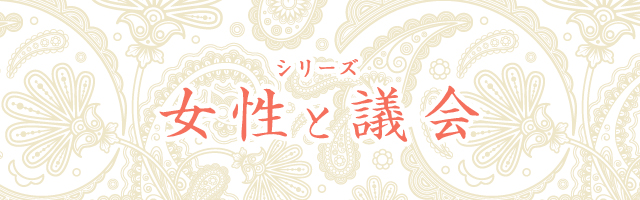なぜ日本では女性の政治進出が困難なのか
(1) 社会的な困難
日本において女性の政治進出が困難であることについては、いくつかの理由が挙げられる。戦前の日本家庭においては、男性が夫として父として、支配的な立場をとってきた。女性の役割は補助的なものに限定され、家庭の外の公共的な場においては男性が代表するのが当然だとされてきた。政治という公共性が強い場において、このことは最も当てはまったといえる。今もなお、女性の政治進出にとって最大の壁のひとつは家族による反対である。
このような家父長的な支配は戦後民主主義によっても完全に払拭することができなかった。高度成長経済期においても、男性は「企業戦士」として外で働くのに対して、女性はその留守を受け持ったために、戦後民主主義教育を受けた世代においてさえ、この面における明確な変革は生まれなかった。そうした傾向は、例えばPTAにおいて、日常の活動の多くは母親によって担われているにもかかわらず、ことPTA会長となると、当然のように男性が選ばれていることに表れている。PTA会長は地域の名士であり、政治家への登竜門にもなっている。
大都市部においては、PTA会長の約半数あるいはそれ以上は女性である。これは、上記のような状況は不条理であるという考えが広がっていることが考えられる。図1で見たように、大都市部や都市部において女性の政治進出が進んでいるのは、それを阻む社会的な困難が都市化によって除去されつつあることを物語っているであろう。東京や大阪の周辺都市においては女性議員が25%あるいは30%を占めることは珍しくなく、神奈川県大磯町や大阪府島本町のように半数を占める例も現れている。このように女性議員の比率が増えていけば、議会内の影響力は大きくなり、また彼女たちの背後にいる有権者のことを考えればセクハラ差別やじも飛ばすことができなくなる。
女性の社会的活動が限定されていることは、女性にとって高等教育は不要だという考えにつながる。女性が男性と同じ比率で高等教育を受けることができるようになるのは1990年代後半になってからである。しかも、女性の職業生活は結婚、育児によって中断され、十分なキャリアを得ることができなかった。その結果、女性は政治家になるための経歴や資金、組織、人脈を得る機会を失っていたことが、政治進出を阻まれてきた大きな理由である。
これに比べて欧米では、女性は転職のために繰り返し高等教育を受け直し、高等教育の比率は男性よりもはるかに高い。社会進出においてもより意欲的であり、社会も女性を積極的に受け入れている。政治進出のための準備のレベルはかなり高いのである。
(2)選挙区制度の問題
社会的な意識、構造とともに、女性の政治進出にとって障害になっているのが選挙区制度である。地盤・カバン・看板という通例の選挙の要素から見ると、ただでさえ弱い立場にある女性にとって、利益と人脈のネットワークが張りめぐらされた小選挙区選挙は不利である。小選挙区制を基本とする英米などの諸国において女性議員が他の欧米諸国と比べて少ない理由のひとつはここにある。対照的に、比例選挙を中心にしている北欧やドイツにおける女性議員の比率は高い。全国政党については、候補者を選定する委員会のメンバーの多くが男性によって占められていることも、立候補を困難にしている。女性議員を増やそうとするのであれば、まずそのメンバー構成を変えるべきである。
小選挙区選挙が女性の政治進出を困難にしているもうひとつの例が都道府県議会である。ここでは、都市部においては複数の議席があるものの、非都市部においては小選挙区がほとんどである。これらの選挙区においては都市化が進んでいないこととも相まって、女性の政治進出が極めて困難である。そのことは、都道府県議会における女性議員の数の少なさに如実に表れている。
女性の政治進出が必要な理由
なぜ、女性の政治進出が必要であるのか。その理由のひとつは、女性議員が少ないことは民主主義の原則にかなっていないからである。男女によって政治意識に違いがある。新聞等の世論調査で男女別に集計している場合、公共事業や平和・戦争に関する政策については性別によって大きな差がある。それにもかかわらず、政治的決定の場にいる男女の数に大きな開きがあるということは女性の意見が反映されていないということであり、民主主義の観点から不十分だということになる。
また、前述のように、女性が特有の視点から政治観を形成しているということであれば、男性が圧倒的に多い議会では、有権者の約半数である女性の視点を欠いた議論や決定形成が行われるということになる。これは女性だけではなく、男性にとっても、討論からより優れた結論、政策を見いだすことができる機会を失っていることを意味するであろう。
2つ目の理由は、女性の政治的視点が歴史的にますます重要になっていることにある。政治学者のスザンヌ・バーガーは現代政治を3つのタイプに分けて考察している。第1が「ハイ・ポリティックス」であり、理念やイデオロギーが政治を支配する場合である。第2次世界大戦後の冷戦を背景にした左右、保守革新による対立の政治がこれに当たる。第2が「インタレスト・ポリティックス」である。第2次世界大戦後の復興から高度経済成長期において、その延長として低成長期においても少ない財源をめぐって、利益や利権をめぐる政治が展開した。そして第3が「ライブリー・ポリティックス」である。これは高度成長経済による環境汚染や政治腐敗などの経験を経て、物質的な繁栄よりも生命・生活・人生あるいは精神的な価値を重視する政治である。こうした価値観に常に身近に接してきたのは男性よりも女性であろう⑶。
女性の政治進出が必要であるのは、今、議論が必要とされているこの「ライブリー・ポリティックス」の主役として女性が期待されているからである。実際に、地方議会に登場した女性の多くが取り組んだのは環境・福祉問題であった。しかし、それにとどまらず、建設(まちづくり)や防災、そして究極的には予算編成の分野においても女性の視点が重要な意味を持っていることが明らかになっている。
先進国を中心に、同じような「ライブリー・ポリティックス」の課題を抱えているがゆえに、世界中で女性議員が支持され増加していると考えられる。それを考えると、日本の政策形成は重要な視点、機会を欠いているということになるであろう。