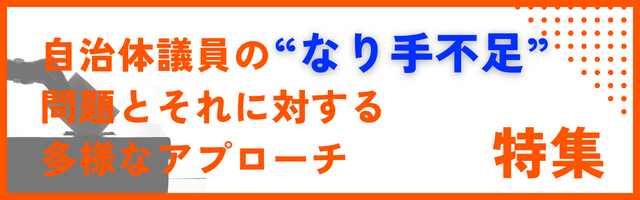大正大学社会共生学部公共政策学科教授 江藤俊昭
|
【目次】(青字が今回の掲載部分) 1 選挙に行かない、選挙に行けない現実──民主主義を「ゆでガエル」に しないために 2 政治の劣化のデメリット 3 議員のなり手不足の要因 4 議員のなり手不足の打開の方途 5 正攻法の豊富化のもう一歩:選挙を意識する 6 なり手不足解消の特効薬:政治分野における男女共同参画推進法 7 選挙を活性化させる新たな自治の動き 8 なり手不足解消の方途の誤解 9 選挙制度への着目──地方政治の劣化の解消法のもう一歩 |
8 なり手不足解消の方途の誤解
なり手不足解消の正攻法を解説してきた。ぜひ、これに基づき議論を巻き起こし、実践していただきたい。しかし、なり手不足解消の方途の誤解も散見される。議論の拡散を防止するために、誤解を是正したい。
誤解1:議員報酬を増額すれば……
議員報酬の増額は、議員のなり手不足解消につながる道の一つだ。とりわけコロナ禍の時期に住民への説明を怠って報酬増額を行えば、当然、住民から批判を浴びる。議員報酬は住民自治を進める議会の条件なので、議員の活動量と内容を説明することが前提となる。住民に十分な説明をせずに増額の報酬条例を改正した自治体の中には、住民が元に戻す条例案を直接請求し、それを議会が否決すると、選挙で多くの新人が当選する結果となったところもある。
住民の納得が弱い議会では、報酬を上げられないか、増額したとしても住民の理解を得ることはできず、なり手不足解消の持続的な解消策にはならない。
なお、年齢別に報酬額を区分する議会もある(若年層に手厚く)。「役務の対価」という報酬の性格との整合性が問われる(監査請求への対応)。また、ある年齢に達すれば報酬額が下がることに違和感はないか。次善の策としては理解できるが、慎重な議論が必要だろう。
誤解2:定数削減をすれば……
定数削減をすれば無投票にはならないのではないか、という思考(算数的思考)がある。定数の原則や、立候補要因を議論しない安易な提案には唖然(あぜん)とする。前者については、討議できる人数を、そして後者については、前述した「ならない要因」と「なれない要因」を踏まえることを提案してきた。
少なくとも定数削減の負の連鎖を意識してもらいたい。定数削減は、当選ラインを引き上げる。集落ごとに議員を出せず、集落の世話役の高齢化による集落間調整が作動しない状況では、立候補したくても当選ラインに達しないことも多い。定数削減が無投票を促進する負の連鎖に注意すべきだ。
誤解3:夜間議会にすれば……
夜間議会によって会社員の議員を増加させるという議論がある。確かに、アメリカ合衆国の市町村では夜間開催議会が多い。日本の自治体の権限・活動量は、アメリカ合衆国の市町村とは比較にならないほど多い。その監視と政策提言が議会には求められている。夜間議会を時々開催する意味はある。しかし、住?が日常的に昼に仕事をして、議員として夜間、行政活動の監視や政策提言をするのは非常に困難である。夜間の活動だけではなく、昼間も調査や質問等の準備で多大な時間を要する。夜間開催で、したがってほとんど夜間の活動で議会の役割を果たせるのだろうか。
なお、夜間議会にして無報酬とする主張もある。ボランティアで議会・議員、そして行政を監視する意欲的な住?がいることは承知しているし、意義ある活動であると考えているが、それを議員一般に広げることは無理があるのではないだろうか。
誤解4:住民総会にすれば……
無投票当選によって議会が成立しないのだから(正確には「成立しない」わけではない)、議会に代えて住民総会にすればよい、という意見も聞かれる。住民総会は、間接民主制よりも住民総会を含めた直接民主制の方がベターだという理念に基づいているのだろう。ぜひ具体的に設計していただきたい。住民総会とした場合、個々バラバラな住民をまとめ上げるためには理事会等が必要で、それに正統性を付与するには、選挙などによる選出が必要になる。議会と類似組織になる。とりわけ、二元制の下での住民総会には、首長との政策競争を行うための強固な理事会等が不可欠とならざるを得ない。住民総会をバラ色で描くのはやめよう。
なお、住民総会を否定的に評価し、今後の議会の二つのモデルを提案した、総務省「町村議会のあり方に関する研究会報告書」(2018年)は、住民自治にとって大きな問題を含んでいる。現行制度とともに条例制定によって可能となる「集中専門型」と「多数参画型」という新たな二つの議会が提案された。それぞれに「不可分のパッケージ」の要素が列挙されている。このパッケージという発想は、自治体の自律性を阻害し分権改革に逆行する。また、どちらを採用しても議会の監視・政策提言力を弱体化させる。集中専門型は首長との癒着か恒常的な対立を内包させ、多数参画型はパートタイム的な役割を担う議員を生み出すからだ。
多くの批判を浴び、この二つのモデルは沈静化しているが、第32次地方制度調査会答申に再浮上の萌芽(ほうが)が読み取れる。注意したい。