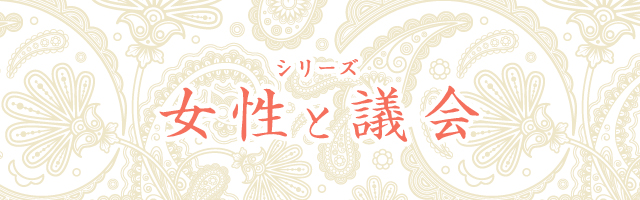はじめに──言い訳?
あらかじめ告白しておこう。筆者は、「女性と議会」研究の専門家でもなければ、ジェンダー論や男女共同参画等に詳しいわけでもない(1)。専門は行政学である。斯学の門をたたいた頃は、NPM(New Public Management)と呼ばれる行革の教義・ツールを(どちらかといえば批判的に)研究していた。その後、関心はNPO、ボランティア、まちづくり等に広がるも、「女性」に関する研究実績はない。そんな門外漢がなぜ、本特集の末席を汚すことになったのか。ここは出雲の地、人知を超えた「縁」とでもいいたいところではあるが、確からしい要因ないし経緯がないわけではない。迂遠ではあるが、その解説をもって、筆者に与えられた任を果たすこととしたい。
ポリンピック──その最初の「縁」
当初、編集部から示されたタイトル案は「若者や女性の政治参加~全国キャラバン、ポリンピックを共催して~(仮)」であった。ここからは2つのことが読み取れよう。ひとつは、女性のみならず「若者」(の政治参加)も射程に含まれていたこと。今ひとつは、筆者(たち)が「ポリンピック」なるものを「共催」していたであろうこと。まずは簡潔に補足しておく。
ポリンピック(「ポリティクス(政治)」+「オリンピック」)とは、公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター(以下「女性と政治センター」という)主催イベント「女性を議会へ!全国キャラバン─2015統一地方選を前に」(2)の一環として、2014年5月に実施されたものである。ここ島根は、女性議員の数ワースト2位ということで全国キャラバン第2弾の地に選ばれた(3)。そして、現地の「共催」団体として白羽の矢が立てられたのが、筆者が顧問を務める島根大学の学生団体、「ポリレンジャー〜若者の手で政治をよくし隊!〜」(以下「ポリ」という)である。
最初の依頼は、かねて女性と政治センターと縁のあったH島根県議(女性)から、「ポリコン」(4)の場にて、であった。そのときは、おおむね次のように回答した。「女性議員を増やすという目的のため“だけ”ならば協力し難い。しかし、若者も含めてその政治参加を促す会として開くことができるのであれば、我々のミッションにも沿うしコラボできるかもしれない」と。これに対し、女性と政治センターの反応は、“意外にも”(5)極めて寛容であった。若者をターゲットに含める(したがって、ごく単純にいえば「女性(議員)」への訴求力は半分に弱まる)ことに同意された上、プログラムの中身についても相当程度学生に任せてもらえたのである。ポリ発案の「ポリンピック!─女性×若者×政治=?」なる珍妙なイベント名こそ、その懐の深さを物語っているといえようか。
ポリンピック自体についてはすでに、本誌Vol.45・46(6)や女性と政治センター発行の「女性展望」(7)で比較的詳しい報告がなされているところである。そこで本稿では、ポリンピックの“前史”を扱うこととする。換言すれば、H県議との「縁」を掘り下げる。本人の認識は定かではないが、そこには大きく2つの背景があったとみられる。ひとつは、(顧問としてはやや手前みそながら)ポリの「実績」である。ただの「飲み仲間」であったとすれば、H県議も我々を女性と政治センターに推されることはなかったであろう。直前にポリが「第8回マニフェスト大賞」を受賞(8)していたことも多少は影響したのかもしれない。2つは、「日本女性会議2011松江」(以下「女性会議」という)(9)へのコミットである。かつてポリは、「女性の政治参画」なるテーマをおよそ1年間追いかけたことがあった。以下、ポリの軌跡をたどりつつ、敷えんする。