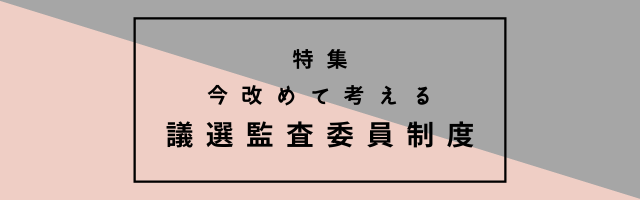住民自治を進める改革の弁証法
議選監査委員と議会との連携によるそれぞれのパワーアップの相乗効果の理論と実践を紹介してきた。この進展を誰が予想したであろうか。議選監査委員をめぐる議論では、理念や制度に関する議論がほとんどで、議会と監査委員のそれぞれのパワーアップの実践を踏まえた議論は皆無だった。筆者は、議選監査委員をめぐる制度改革に関わってきた。その一つは、筆者も委員であった第29次地方制度調査会における議論である。答申直前まで議選監査委員の廃止が提案され、その方向で舵(かじ)が切られていた。もう一つは、議選監査委員の選択制を書き込んだ第31次地方制度調査会答申を踏まえて提案された地方自治法改正をめぐる議論である。それについて筆者は、参議院総務委員会参考人として意見陳述している。議選監査委員廃止反対、選択制反対の立場から意見を述べている。
本特集でも紹介されている議会と議選監査委員の連携を念頭に置きつつも、主に制度論から反対を主張していた。総務委員会に参考人として出席した際に、ある委員から「監視を監査委員と議会とが違う視点から行えばよいのではないか」との質問があった。時間がないということで、それについての意見陳述ができなかったのは残念であった。まさに、本特集でも確認したように、議会と監査委員とでは、役割も対象権限も異なる。それぞれのパワーアップとともに、連携による相乗効果が重要である。その実践が始まり、本特集ではその状況を「議選監査委員の新時代の息吹」として捉えている。こうした連携により自治力のアップが生まれている。
議選監査委員については、議員の身分を残したまま執行機関に入っているからといった制度の仕組みから、あるいは公認会計士・弁護士などを増やした方がいいといった「専門性信仰」から廃止の声も広がっている。変則な制度であっても、本来は議会に設置すべき組織であること、変則は、議選監査委員だけではないことも考慮すべきである。また、専門性といっても特定の専門家であり、行政にたけているとは必ずしもいえない。ともかく、議会の監視以外を監査は行う。議会はそれを活用して行政をチェックすることになる。その武器を放棄することには、慎重に議論するべきである。安易な廃止は、理論上できないことはないとはいえ、復活はできない。議選監査委員の新時代の息吹を感じて自治を考えていただきたい。
*筆者たちは、実践を踏まえて議会と議選監査委員の連携の意義を紹介してきた。廃止した自治体の現状についての調査・報告は別途検討したい。
【附記】 本稿は、江藤俊昭・目黒章三郎・川上文浩・子籠敏人ほか「今改めて考える議選監査委員の意義と使命①~⑫」地方財務2023年1月号~12月号での筆者担当部分の一部を修正・加筆し再構成した部分もある。
|
|