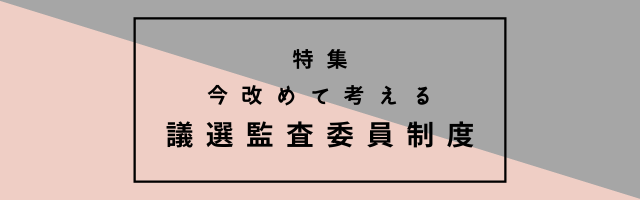監査と議会との新たな関係の原則
11(+1)のポイントの豊富化を踏まえて、監査と議会との新たな関係の原則のバージョンアップを図っておこう。なお、監査委員と監査委員事務局との協働も重要である。議会事務局、行政委員会事務局などの議論とも通底する。
(1)監査委員(議選監査委員)と議会との連携の日常化を
監査は、不正を暴くというより、不正を回避するためという目的を持つことが重要である。そこで、監査委員を「行政のかかりつけ医」と位置付けたのは、川上文浩・可児市議会議員である(川上文浩「今改めて考える議選監査委員の意義と使命⑤」地方財務2023年5月号)。定期監査は健康診断である。行政の健康管理をするとともに、病巣が発見されればそれを治療するように指導する、というものである。
付加すれば、監査は行政だけではなく、議会も対象となる。正確には「議会と行政のかかりつけ医」である。そして、議選監査委員が「かかりつけ医」になることで、自治体経営に政治的視点を挿入することができる。
要するに、監査委員(議選監査委員)と議会との連携の日常化を目指すことになる。それにより相乗効果を図る。
(2)議会による監査請求の意義ともう一つの手法
本特集では、議会による監査請求は、議会の権限として重要なことを指摘している。複数回請求を行っている議会もある(例えば、1998年、2000年、2015年(2回)(鎌倉市))。ただし、議会による監査請求は「天地を揺るがす一大事」という意識を議員も監査委員も行政も払拭できていないこともある。そこで、議会による監査請求とまではいかなくても、議会が議選監査委員に要請して行政監査を提案できるようなシステムの提案もある(「申合せ」などに基づく)。その際、「監査委員が出す情報の基準」についても考慮する必要がある。
議選監査委員の活動を縛る「守秘義務」を限定:情報公開時代の広い「守秘義務」の範囲の違和感
議選監査委員と議会との連携の模索と豊富化が始まっている。その活動を縛る「守秘義務」の範囲と打開策を確認したい。守秘義務を拡大解釈すると、議員活動が制限され、議選監査委員の議員としての活動が萎縮することもある。プライバシー侵害や政争の具となる事項は守秘義務に該当するが(個別の財政援助団体、出資団体等監査)、それ以外は守秘義務の範囲外だ(ポイント7)。
その具体化を図る施策が模索されている。守秘義務の限定を踏まえて、実践的に議選監査委員と議会との連携を充実させる手法である。議会の中には、監査の意義が理解できず、守秘義務幻想に陥っている議選監査委員もいる。その払拭のためにも、「施策の模索」を再確認することが順当であろう。議選監査委員は、識見監査委員や監査委員事務局との相談を通じて守秘義務の範囲を確認し、自らの役割を果たす試みもある。この手法をまずもって実践していただきたい。
(1)議選監査委員と議会との連携の豊富化
予算決算委員会において、議選監査委員が決算審査報告を行い、質疑応答・意見交換をしたり、定例会ごとに監査報告と監査所見を行い情報共有を図っている議会がある。議選監査委員の指摘・要望事項、意見を、常任委員会の所管事務調査に連動させている(可児市議会)。そして、正副委員長会議では、常任委員会の所管事務調査の事案について情報共有、意見交換を行っている(川上・前掲「今改めて考える議選監査委員の意義と使命⑤」)。
また、議選監査委員が監査委員定期監査報告書と決算審査意見書についての報告会を開催している(西脇市議会)。各議員からの質疑に議選監査委員が答弁している。質疑は事前通告制をとっているが、再質疑や他議員からの関連質疑も行っている。代表監査委員には議選監査委員が答弁することの了承を得ている。なお、監査事務局長は、サポートとして同席している(林晴信「今改めて考える議選監査委員の意義と使命⑧」地方財務2023年8月号)。
(2)議選監査委員による一般質問の実践
議選監査委員が議員として一般質問する際の留意点である。議選監査委員在職期間だけでなく、辞めた後も一般質問を躊躇(ちゅうちょ)する議員がいる。本末転倒である。西脇市では、事前に監査事務局と相談し、問題ないことを確認してから行うことを義務付けている(林・前掲「今改めて考える議選監査委員の意義と使命⑧」)。なお、2018年から現時点(2025年2月2日確認)まで議選監査委員の一般質問の内容に問題があって取りやめたことはない。
守秘義務を限定する原則を明確にしてルール化する必要がある。それでも、躊躇する議員はいるだろう。その場合、監査委員事務局や代表監査委員と相談の上、報告や質問を行うことにすれば踏み出せるであろう。