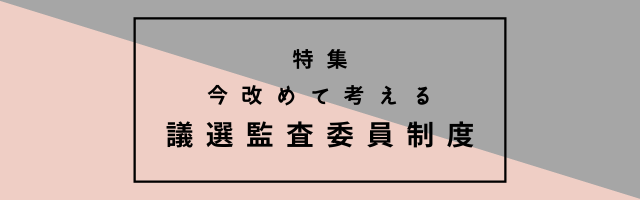(3)議選監査委員の本末転倒の従来型理解とその打開策
議選監査委員が一般質問をできなければ、議員になる意義はない。また、守秘義務を広くとれば議員活動はできない。プライバシー侵害や政争の具(及び財政援助団体の詳細な経営動向)は守秘義務の対象だが、それ以外は対象外となる(情報公開の対象)。議選監査委員が消極的な活動をする大きな要因の一つが、広く守秘義務をとることだ。
【ポイント6】議選監査委員は、上がりの役職でもなければ、議員の役割を果たせない役職でもない。
【ポイント7】守秘義務を広くとっては、議員活動はできない(その限定が不可欠)。
(4)議選監査委員の誤解
独立性・専門性・中立性の欠如を議選監査委員批判に活用されるが、識見監査委員についても独立性・専門性・中立性から問題にされるべきである。また、二元制という地方政府形態にあって、「矛盾」があるのではないかという単純な批判から議選監査委員を廃止する自治体もある。変則は、議選監査委員だけではないこと、歴史的産物であることを踏まえて慎重に議論すべきであろう。
【ポイント8】独立性・専門性・中立性が問題なのは議選監査委員だけではない。
【ポイント9】二元制からの変則は議選監査委員だけではない:現行制度の意味を確認しよう。
|
|
(5)議選監査委員と議会との新たな連携の充実手法
監査機能を充実させるための、同意基準や条件整備の充実が必要である。とりわけ、監査委員の定数が2人の場合、議選監査委員を存続させて3人とするなど充実を図る。また、監査専門委員を採用する必要がある。議会事務局とは異なり、むしろ独立性・専門性・中立性を強化するには、監査委員事務局、監査専門委員の共同設置も必要である(議会事務局の共同設置は、議会事務局は「根なし草」になり議会力をダウンさせる)。
【ポイント10】監査委員の同意基準の明確化、監査委員の増員、専門委員の設置、監査委員事務局の増員等。
【ポイント11】監査委員・監査委員事務局の共同設置(外部の視点の重要性:議会事務局の共同設置は自治に反する(法律上の「共同設置」はどこかの自治体議会に属する))。
〈11のポイント+1(一部事務組合・広域連合の監査)〉
一部事務組合・広域連合の議会改革と監査委員改革は、当該自治体の議会改革と監査委員改革を参考に進める必要がある。