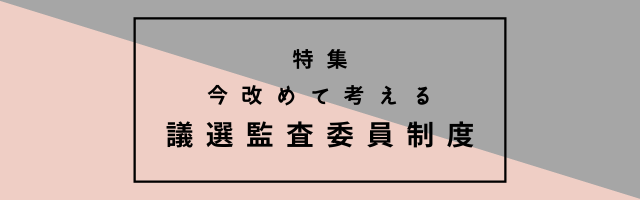監査委員の役割・選出基準をルール化する
江藤:私は議選監査委員の役割や選出の仕方などの重要なことは、自治基本条例や議会基本条例に書き込むことが大事だと思っています。そういった動きはありますか。
川上:何らかの形で条例化又は既存条例の改正をできないか思考中です。ただ、整理していくと、行政に関わることを議会基本条例にどう表現して載せるかという問題があり、越権行為とならないように条文を考えていますが、まだ公表には至っていません。議選監査委員を出す場合として何ができるか、ということは載せられるのかもしれないと思っています。案は全部でき上がっているので、市長と相談して公表する予定にしています。議選監査委員は、市長が一本釣りするところもあるんですね。当市の場合は、議会推薦をもって議選監査委員を市長が議会に上程するということになっていますが、他の選出方法をとっている自治体もあるので、やはり条文は必要だと思っています。
子籠:議選監査委員として自分たちの議会から誰を推挙していくかということが問われます。選出の仕方などを内規などで担保する考え方をしっかり持てたらいいとは思います。どこに書くかについては、議会ごとのカラーもあるので、申合せとするとか、基準をつくるとか、いろいろな方法があると思います。
江藤:しっかりした人に議選監査委員になってほしいというメッセージとして、自治基本条例や議会基本条例に入れていくというのは大事なことかと思います。
子籠:一方、法改正もあり、監査基準も定めることとなり、その中に監査計画についても規定して、計画に沿って監査を実行していくことになりました。この改正を現場に生かすためにも、監査委員や監査委員事務局で、その中に考え方や役割、取り組むべきことについて明文化しておくことによって、誰がやることになってもその役割をしっかり担ってもらうことができるという担保になると思います。当市は、そういった意識が高く、先ほど紹介した監査計画の基本方針にも、事務局職員の研修やスキルアップについて記載したり、そのための視察や研修も独自で取り組み始めています。そうすることで、今後誰が担当することになっても、考えが統一され、未来を担保できると考えています。その形をつくっておくことも、自分がいる間にやるべきことだと思っています。
江藤:監査委員の基本条例みたいなものですね。
日本の地方自治の特徴は二元制だけでなく、行政委員会委員の多元制なども大事ですよね。こちらは軽視されていますが、基本的なルールとして入れ込むべき課題だと思います。そういうことも今後考慮する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
川上:当市は明確な内部統制はありませんが、課ごとに規則、規程、マニュアル等を作成して実際の業務に適用しています。監査がこれだけ活発になると内部統制は必要だと執行部が思い始めているようです。