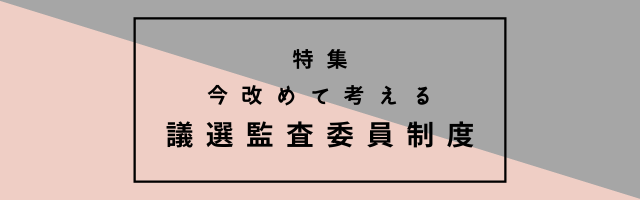川上文浩 可児市議会議員/ローカル・マニフェスト推進連盟共同代表 .
子籠敏人 あきる野市議会議員/ローカル・マニフェスト推進連盟共同代表
江藤俊昭(以下、江藤):今回の特集は、議選監査委員と議会がその相乗効果で双方パワーアップを図ることができるというものです。本日は、そのポイントや今後の展望について、特集執筆者のお二人にそれぞれの取組を踏まえながらお聞きしたいと思います。
まず、お二人が議選監査委員になられた背景についてお話しいただけますか。
川上文浩(以下、川上):地方自治法の改正によって、議選監査委員の設置は条例によるということに変わりました。議選監査を廃止するも存続するも、その自治体で決めなさいということで、可児市議会では、議論した上で議選監査委員を残すことになりました。当市は10万人規模の市ですが、監査委員は2人とも非常勤で、監査委員事務局は3人、常勤の監査員は存在していません。議員は頻繁に市役所に足を運んでいますし、予算決算を含めた行政情報について熟知していますから、行政的な監査の面はやはり議員が請け負った方がよいのではないかということになりました。
現在の監査は、監査委員事務局が、大まかな会計監査を常勤職員の職務として行った上で、定期監査をしっかりと2人の監査委員が、事前資料に目を通しながらやっていくという仕組みになっていますが、私が就いた当初は、まだ監査の仕組みや方向性が示されていませんでした。監査目標も当時は事務局がつくっており、監査委員はあまり関わっていなかったものを、計画も含めて監査委員が積極的に関わって決めるという今の形になっていったことがそのスタートになります。 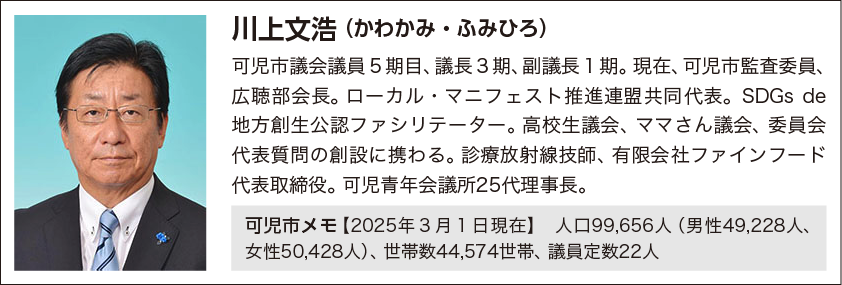
江藤:議選監査委員が選択制となった中で、議論してそういう形に落ち着いたというお話をいただきました。おそらく、そのほかにも議会力というか、議会が役割を変えてきたということもあるかと思います。その辺りについては、また後でお話を伺いたいと思います。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。