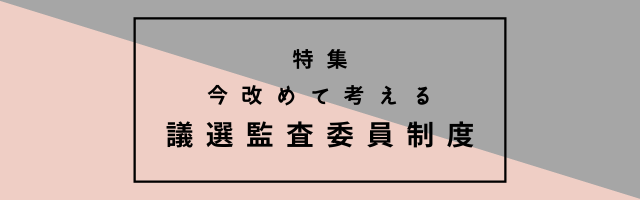|
|
争点としての議選監査員の浮上
(1)評判の悪い議選監査委員──従来の議選をめぐる争点
従来から議選監査委員をめぐる議論は多かった。専門性・独立性・中立性に欠けるといった身分・能力(属性)にかかわることから、1年任期で交代、「上がりのポスト」、一般質問ができない(しない)といった運営上の問題まで……。すこぶる評判が悪かった。しかし、識見監査委員でも、行政にたけていないという意味で、首長による任命(監査委員事務局も同様)によって行政に厳しく対応できない可能性があるなど議論すべき論点はある。すでに指摘した議選監査委員をめぐる運営上の問題は、議選監査委員の意味が理解できていない議会・議員に原因がある。議選監査委員の運営上の問題は、その制度とは無関係である。
なお、議員の身分を残したままという変則制度であるが(最終回に振り返る)、根本は議員である。議員の役割を放棄してはならない。
従来、属性や運営上の問題から評判が悪い議選監査委員制度であるがゆえに、廃止の議論は時に浮上する。第29次地方制度調査会の議論の対象の一つが、議選監査委員の位置付け、より正確にいえば廃止の議論であった。答申直前まで廃止を議論していたが、全国都道府県議会議長会・全国市議会議長会・全国町村議会議長会などが強力に異議を唱えることで、議論は振出しに戻っていた。
その後、2017年の地方自治法改正において、「ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」との規定が設けられ、これを根拠に議選監査委員を廃止する議会も登場している。結論を先取りすれば、議選監査委員には従来問題はあったが、それだからといって安易に廃止することは、議会力や監査力を弱体化させる。どのような活用ができるかをまずもって考えていただきたい。大幅な改革(例えば、監査権限、実地検査権の議会への付与など)は、その後の課題である。