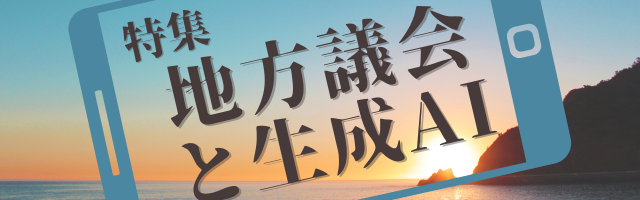2 地域はよくなってきたか?
2014年に「まち・ひと・しごと創生法」(以下「地方創生法」という)が施行され10年が経過した。この間、地方自治体では総合戦略を作成し、国から様々な補助金や交付金を受け政策を実施してきた。また、近年では新型コロナウイルスの猛威により地域の経済対策等を中心に多額の税金を投入してきた。地方創生法施行から10年が経過した現在、あなたの地域は10年前と比較して、どこがよくなっただろうか? 地域の課題だった案件はどの程度解消されてきているだろうか? 地域の未来には明るい兆しが見えてきているだろうか? おそらく、多くの分野で課題が解決できたり、あるいは、その方向へ向かう途中であることだろう。反面、10年前より状況が悪くなった課題や新たな問題が発生しているケースも少なくないのではないか。地域全体が衰退しているところもある。
税金を何にどれだけ使用するのかを決めている議会に対し、行政は議会が決めてくれたことしか執行できない。すなわち、議会の審議力・議決力が地域の未来をつくっているといっても過言ではない(ここで、まちづくりは首長ほか行政の役割と思い込んでいる議員がいたら、その思い込みは改めていただきたい)。
筆者は、地方自治体関係者から次のような地域課題を聞くことが多い。皆さんの地域に該当するような項目はあるだろうか?
・買物をする場所が少なくなっている(なくなった)
・公共交通が縮小・廃止している
・近所にあった診療所(病院)がなくなった
・ハローワークの有効求人倍率は高いが従事者がいない
・高校を卒業し大学や就職で地域外へ出たら戻ってこない
・空き家が増えている
・休耕田が増えている
・一人暮らしの高齢者が増えている
・認知症患者が増えている
・消防団員、民生委員、保護司などのなり手不足
・自治会役員のなり手不足
・地元の祭りやイベントの形骸化
・小中高校等の統廃合
・上下水道の維持管理(公共施設の維持管理・統合)
・地元産業の後継者不足
次に、役所課題について尋ねると、以下のようなテーマが多かった。
・若手職員が辞めていく
・休職者の増加
・早期退職希望者が多い
・管理職のなり手不足
・公務員希望者の減少
・職員に余裕のない職場
・なくならない事務処理ミス
・明らかに職員数が足りない
・縦割り組織
・プレイヤーのままの管理職
・頑張っているのに成果が出ない政策
・絵に描いた餅状態の総合計画
・職員研修を重ねても育たない人材
・打ち破れない慣例
・人事担当者しか知らない人材育成基本方針
これらに共通することは、今までの議会の中で何かしらの議案に出てきている(予算や計画等に含まれている)事案ということだ。議会は行政のチェック機関というのであれば、これらについて、今までの議会では「どのような議論があり、どのような議決をしてきた」のだろうか?
3 どこに課題があるか?
筆者は、議会の審議力・議決力の向上に問題意識を持っている。それは、一般的な地方議会では独自の情報を入手する環境を整えていないという点だ。通常は、行政側から提出された資料を基に行政側の説明を聴き、それに対して議員が質問をする。そこには、議会として独自に集めた情報や熟議の上に出てきた問題意識などは入らず、最終日の本会議(議決)へと進んでいく。いわば、行政のさじ加減での情報の下で議会は議案チェックを“させられている”といってよい。
もちろん、個々の議員や会派では、住民のところへ出向いて意見集約をしたり、先進地視察等へ行き学習してきた情報などを議論に加えている事例も多くあるだろう。しかし、議決機関としての議会としては環境整備をしていない議会が大半だ。また、地方議員を専業として活動する議員でも「情報収集や住民の意見集約をどのようにすればよいか」、「情報を集めたはいいが、そこから何が読み取れるのか? どのような点が問題だといえるのか(問題発見力)」等のスキルを身につけるには時間がかかるという課題がある。