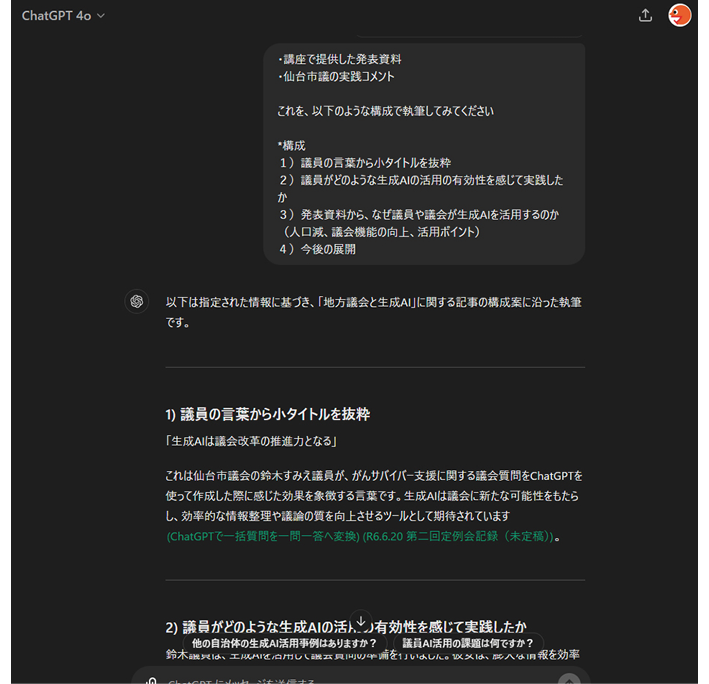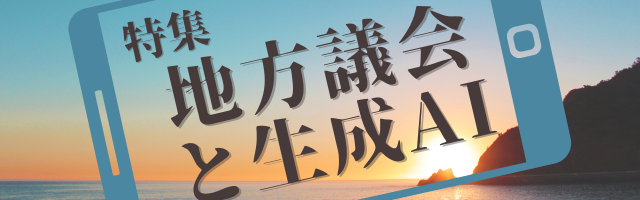生成AIの議会での活用は、まだ始まったばかりであり、今後の展開に大きな可能性が広がっている。
8月の講座に参加した福島県飯舘村の横山秀人議員は、従来の質問づくりの際、「もっと違った視点からも提案できるのではないか?」と考えていた。早速、講座で学んだ内容を活用し、作成した質問についてChatGPTに「各項目の提案について、違った視点から提案してください」と指示したところ、有意義な結果が得られたという。
「ChatGTPは、月20ドルで働いてくれる、私の優秀な政策秘書。そう思えば、何でも相談したり、調査依頼することができる。政治活動に、劇的な変化をもたらした」と評した。
大村市の村崎浩史議員は、全編で生成AIを活用して一般質問を作成し、準備時間は従来の5分の1に。最後に生成AIに関する質問をし、「実は今日の質問は全て生成AIでつくった」と明かして、議会と市側のさらなるAI活用を求めた。
相模原市の阿部善博議員は、議会と市側が「同じ土俵で議論するために、AIを積極的に活用したい」という狙いで、橋の架け替えに伴う道路関連の議案について、ChatGPTに限らず三つの生成AIを活用。過去の議事録や都県境の道路整備の問題点を学習させ、長期的視点や緊急時の対応責任といった論点漏れのチェックに役立てた。現在、「とにかく生成AIを使い倒す!」を目指して実践計画を立てて、取組みの試行を進めている。

4月に開催した「地方議会を変革する生成AI活用講座」の様子
生成AIは、地方議会にとって強力なツールとなりえる。人口減少や議員数の減少といった社会的課題に対処し、議会活動の質を高めるために、AIを積極的に活用することが求められていくだろう。
今回の特集では、今回以降も「生成AIを使って何ができるのか」「議員活動と生成AI」「地方議会と生成AIの新たな可能性」といったテーマについて、各回で詳細をお伝えしていきたい。
ぜひ読者の地方議員や議会(事務)局職員の皆さまには、生成AIの有効活用を具体的にイメージしていただき、実践を進める中で、今後もAI活用の事例やノウハウが共有され、さらなる議会改革、ひいてはよい政治の競争「善政競争(協創)」が推進されることを願っている。
※この記事は、ChatGPTに情報を入力し記事案を作成した後、筆者がリライトし、最終校正をChatGPTに依頼し修正しました。従来、記事作成にかかっていた時間を40%程度、削減できたと実感しています。