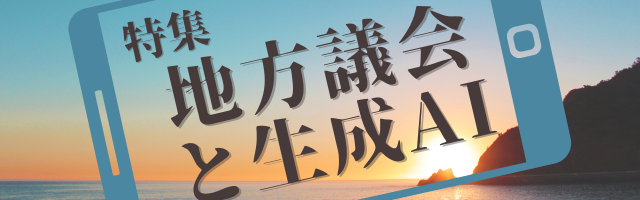ChatGPTとは何か? 生成AI先進自治体として著名な横須賀市にも関わる、UI/UXデザイナーの深津貴之氏の発言を引用すると、ChatGPTとは「手前の文に、確率的にありそうな続きの文字をどんどんつなげていくAI」だという。
例えば、人間がChatGPTに「むかしむかし」と入力する。そうすると、「あるところに」「おじいさんとおばあさんが」「住んでいました」という連続した、確率的に一番高いものが出力される。従来もこうした仕組みはあったが、学習方法に革新があり、さらに蓄積されたデータが天文学的に増えたことで、人間より賢そうな文章を生成できるようになった。昨今であれば「議会で使えるレベルになった」ということで、こうした活用講座や研修に注目が集まっている。
「確率上一番ありえる回答」ということは、「無難な内容」ということでもある。だからこそ、最初に人間が適切な指示をすることが大事であり、求められる回答が出なかったときは、指示を出した自分が悪いと考えるべきである。どうしたら自分の求める回答に近づけていけるかを、複数回会話することでつかむ必要がある。ここではICTスキルというよりは、言語化能力とコミュニケーション能力、言葉を換えると「人にお願いする能力」が重要である。まさに議員にピッタリなツールである。
また、「確率上一番ありえる回答」が絶対に正しいとは限らない。そのため、内容については必ずファクトチェックをし、議員本人が責任を持って議会で発言してもいいかを判断する必要がある。
生成AIを使いこなすほど、「個人の資質・能力」が問われると感じる。一般的な指示では、優秀でそれらしい、無難な回答だけが出てくる。ChatGPTを活用するときも、使う側の個人の考えがまずあり、そこに視察や事例研究で学んだアイデアや経験・知識を入れて、生成AIを使ってとりまとめていく。生成AIの本質的な活用とは、個人の能力を拡張することにほかならない。ただ単に機械を使うというわけではなく、人の考えが入り、人が学んできたものが反映される。それが正しい「ツールの使い方」であろう。
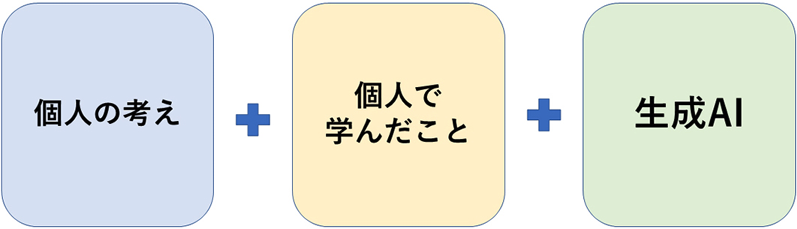
出典:「地方議会を変革する生成AI活用講座」登壇資料(林紀行・日本大学法学部教授作成)
では、こうしたツールを地方議会でどう活用するか? 生成AIの活用のポイントは以下である。
▽「議会質問の項目づくり」「質問の原稿づくり(不明瞭な点等の洗い出し)」
- 議員が質問を作成するとき、自身の関心テーマを提示することで、生成AI側に深掘りすべき内容を例示させる。
- 各種資料や職員のヒアリング等で情報収集しそれを入力、さらに内容を整理・要約、原稿化する。
- 完成した原稿に対して、不足点や不明瞭な点を洗い出しブラッシュアップする。
▽「議会の答弁書の作成、答弁書を想定した質問づくり」「過去の議事録から、質問と回答を予測する、模擬議会の質問の答弁」「首長や執行部の回答、不足している点を明らかにする」
- 質問が完成しても、執行部の反応が薄ければ、住民の負託に応えられているとは言い難い。過去の議事録を入力し、執行部の答弁を予測する。模擬議会で質問の答弁をシミュレーションし追加の質問内容を検討する。
- 首長や執行部の回答で不足点を探って再質問することで、さらなる効果的な答弁を引き出し、執行部側の検討の質の向上や事業実施に資する。