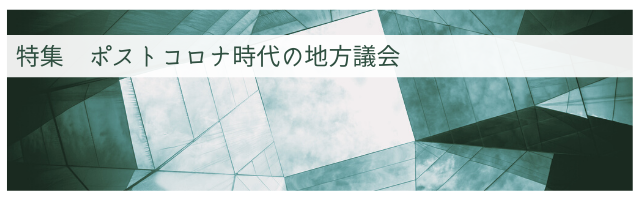4 BCPの策定
執行機関のような指揮命令系統を有する組織体と異なり、議会にとって災害等発生時の迅速な対応は容易ではなく、あらかじめ議会版の業務継続計画(Business Continuity Plan:BCP)の中で整理しておく必要がある。先駆けてオンライン会議を導入した議会でも、そのような例が多く見られるところである。
BCPの策定方法と体裁は議会によって様々であり、有識者を交えて数年がかりで数十頁に及ぶ綿密な計画を策定する例から、議会内部の会議でA4サイズ1枚に収まる条数の規程で定める例まで様々である。各地の例を集めてみると形式的に立派なBCPに目が向きがちであるが、どのような災害が想定され、議会としてどのように対応すべきかは地域によって様々であろうことからすると、BCPのあり方も様々であってむしろ当然である。地域の実情と身の丈に合ったBCPを策定し、定期的に見直し、あるいは、定期的な訓練を行い、いざというときに的確に対応できるよう備えておくことが肝要である。
策定の際に検討すべき点としては、非常時の議会運営の方法のほか、次の事項が挙げられる。
・いかなる事態を想定するのか
自然災害と感染症では対応が異ならざるを得ないので、感染症のほか、地域における具体的な自然災害等を想定して策定する必要がある。
・非常時の協議の体制は
議長と議会事務局を中心とした非常時の体制について定める必要がある。会議体の構成と意思決定の方法はシンプルに、連絡と周知の方法は丁寧に構築すると、非常時の迅速かつ的確な対応に資するであろう。
・執行機関へのアプローチの方法
非常時に執行機関へ過度な負担をかけないよう、議員から執行機関に住民の声を届ける際のルール(いったん議会で取りまとめるなど)を定めておくと、非常時対応の実効性が上がるであろう。
5 コロナ対応のその先へ
本稿で取り上げたもののほか、コロナ禍においては、通年議会制・通年会期制、専決処分(地方自治法179条「時間的余裕がないことが明らか」の意義、同法180条に係る指定事項の見直しなど)、傍聴(席数の制限、オンライン傍聴など)などについても議論がされている。「災い転じて」ではないが、この機会に、より充実した議会運営を実現するため先例や申合せ事項を見直す取組みがされ、地方議会が各地域においてその役割を十二分に果たすことを期待したい。