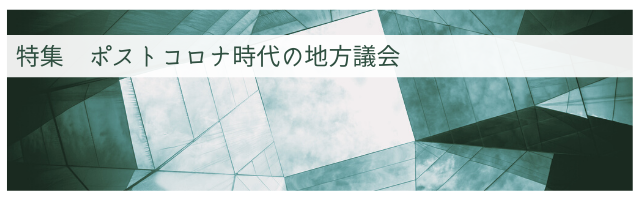3 オンライン会議の導入
(1)委員会への導入について
総務省は、地方議会におけるオンライン会議の導入について、委員会に関しては一定の状況下において開催することは差し支えないとの見解を示している(令和2年4月30日付け総務省自治行政局行政課長通知「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」)。この通知を受け、地方議会1,788団体のうち135団体が委員会のオンライン会議に関する例規改正を行い、35団体が実際にオンライン会議を行ったとされる(令和4年1月1日現在。総務省「地方議会における委員会のオンライン開催の状況」)。
全国市議会議長会から参考条例が示されるなど、委員会のオンライン会議導入の動きは今後も拡大していくと思われるが、その意義はオンライン会議を開催する場面によって一様ではない。常任委員会の議案審査の場合、本会議が開催できない状況下では、オンライン会議の意義は限定的なものにならざるを得ない(そうした状況下ではそもそも付託がされないケースが多いであろうが)。一方、議会運営委員会が会期前に感染状況を踏まえた定例会の運営方法について協議を行う場面では、むしろ積極的にオンライン会議を活用すべきであろう。どのような場面で、いかなる会議体が協議を行い、その結果をどのように生かすのかといった具体的な想定に基づく検討をしておかなければ、いざ開催しても実効性が上がらない結果になりかねないので、注意が必要である。
また、オンライン会議には、ソフト面及びハード面を含めて次のような課題があることが知られている。非公式な協議においてオンライン会議を試行しながら、不具合等への対処法を整備しておく必要がある。
・個人情報、機密情報等に係る情報セキュリティの確保
・通信障害が発生した際の議事の整理及び議員のサポート
・資料等の提出及び配付の方法(ペーパーレス化の手法)
・正確かつ確実な採決の方法
・議員の本人確認の方法 など
(2)本会議への導入について
上述の総務省自治行政局行政課長通知は、地方自治法113条及び116条1項の「出席」の意義は現に議場にいることと解されていることを理由として、本会議へのオンライン会議の導入について否定的な見解を示している。また、続いて発出された令和2年7月16日付け総務省自治行政局行政課長通知「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法に関するQ&Aについて」では、この見解を補強する理由として、「本会議における審議及び議決は、団体意思の決定に直接関わる行為であり、議員の意思表明は疑義が生じる余地のない形で行われる必要がある」とも述べている。
出席に関する同様の規定は、国会議員の出席について定めた憲法56条にもあり、国会においてもオンライン会議の導入に関し同様の議論がされている。令和4年3月3日には、衆議院の憲法審査会において、本会議の開催が必要と認められるときは、例外的にオンラインによる出席も含まれると解釈することができるとの意見が紹介されている(同日の会議資料)。
憲法と地方自治法の異なる規定の文言であるので、必ずしも同様に解さなければならないわけではないが、別違に解する特段の理由がなければ同様に解することが望ましいことはいうまでもなかろう。憲法上の解釈に関する議論が収束する頃、地方自治法上の解釈や改正についても動きが見えてくるものと予想される。その点では、地方自治法の解釈について、地方議会の機能を維持する観点で分析を継続しつつ、憲法の解釈論をも注視していきたい。
仮に、この議論が収束する前に本会議を開催する必要に迫られ、オンライン会議による議決を経て条例を施行し、あるいは、予算を執行した場合に、そのような議決は無効だとして、当該条例や予算を根拠とする支出について住民監査請求、住民訴訟が提起される可能性がある。議論の途上にある事柄を争点とする訴訟対応には困難が予想されるところであって、そのようなリスクを冒して本会議をオンラインで行うという選択肢は、現時点ではないであろう。
(3)オンライン会議の常設化について
オンライン会議に関する議論には、オンライン会議は非常手段ではなく、議会機能の向上に資する新しい手段であるとして評価する意見や、移動弱者等を念頭に、議員のなり手不足の解消に役立つとする意見がある一方、オンライン会議は、意思疎通を図る手段としては「リアル」に対面して行う会議に劣るとして、あくまで補完的な手段であるとする意見も見られるところである。
オンライン会議の常設化が進んだ場合、極端にいえば任期中一度もリアルに会議に出席しない議員も現れるかもしれない。オンライン会議を導入する議会でもそこまでの認識はないであろうが、いずれにしても、オンライン会議が一般的な手法として確立されるには、まだしばらくの時間と試行錯誤が必要である。当面は、オンライン会議については、会議規則等だけでなく、次に述べるBCPにおいて非常時のツールとして整理しておくことが望ましいであろう。