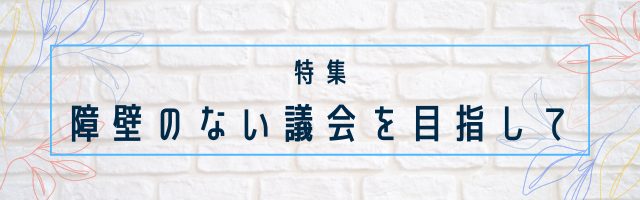新たな視点が入り変わり始めた公園
変わり始めた事例を紹介したい。東京都が管轄する公園が、最近、インクルーシブ公園へ変わっている。
東京都議会の龍円あいり議員はアメリカで障害のある子どもを出産、育児期間中に障害のある子もない子も一緒に遊べるインクルーシブ公園で子どもを遊ばせた。しかし、日本に帰国してインクルーシブ公園がないこと、電車の中で乳幼児を抱えた女性の授乳や子どもが泣き出した際のスペースが確保されていないことなどを経験。誰一人取り残さないSDGsの考え方を実践しようと、それらの課題解決をマニフェストとして掲げ、都議会議員に当選した。彼女はマニフェストの実現のために各方面に働きかけたが抵抗は強かった。やはり子どもの頃からの環境が整っていないと、今あることを当然と思い、何の疑いも持たない大人になってしまう。その現実から変えていかなければと各所を説得し、思いを実現させてきた。
通常のブランコでは誰かに身体を支えてもらわないと乗れないが、イス型のブランコなら支えてもらわなくても乗ることができる。シーソーも形が変われば遊べるようになった。大きな音が苦手な子どもが駆け込めるシェルターを兼ねた遊具など、これまで健常者の子ども向けであった公園が、障害者も健常者も一緒に遊べる公園へと変わった(写真1、2、3参照)。

写真1 通常のブランコ(右)とイス型のブランコ(左)
写真2 誰もが一緒に遊べるシーソー
写真3 大きな音が苦手な子どもが駆け込めるシェルター
障害者の政治参加の扉を開く
地方議会の現状は、多様な主体による構成にはいまだ程遠く、制度や設備面でも課題があることが分かった。障害者が政治へ参加しようとしても、選挙で勝つためにも様々な課題があることだろう。しかし、社会をより成熟させ多くの人にとって暮らしやすい公共空間を実現するためには、従来の視点にとらわれることなく様々な立場に立った視点が必要である。地方議会は現行の街づくりの計画や予算を決定していくだけでなく、未来の街づくりにも関わっている。目の前の課題解決はもちろんのこと、長期的な視野に立ち多様な為政者が生まれやすい風土づくりが必要となり、そのためには多様な主体が活躍できることを考える人材育成に取り組むことが求められる。
「もし自分が視覚障害だったら?」、「もし家族の中に車いす利用者がいたら?」と自らの立ち位置を変えて考えてみると、今とは異なる発想が湧いてくるのではないだろうか。障害者しか分からないことがある。しかし、障害者側の視点や意見を取り入れることで気づくこともある。大事なことは、今の社会が本当に皆にとって暮らしやすい社会になっているかということを考えることである。そのような議論ができる議会の実現をぜひ期待している。