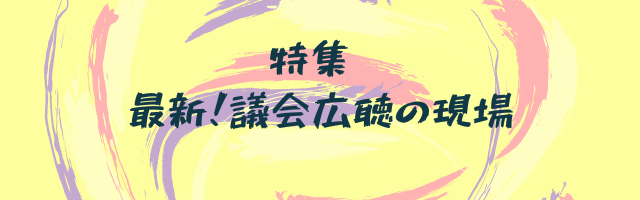3 議会広聴活動の現状
それでは、表で示した議会の広聴手法のなかで議会はどの手法をどの程度活用しているのであろうか。ここでは、全国市議会議長会および町村議会議長会が毎年実施している「市議会の活動に関する実態調査」(以下「市調査」という)、「町村議会実態調査」(以下「町村調査」という)から自治体議会が展開する広聴活動の現状を確認する。
(1)広聴活動の現状
2020年の議会活動を対象とした市調査によると、議会報告会は全市の27.1%、住民アンケートは11.8%、議会モニターは3.8%、パブリックコメントは4.0%となっている。ただし、2020年はコロナ禍の影響により議員と市民との対面で実施される議会報告会を中止した議会も少なくないと思われる。前年の2019年の調査では、報告会を開催する議会が全体の54.6%と半数以上という結果であった。また、町村調査では議会報告会が41.6%、議会モニターは8.6%である(いずれも2019年中の活動を対象)。市議会・町村議会ともに、議会報告会が集団広聴の中心になっていることがわかる。市調査では住民アンケートを行う議会は10%を超える水準となっているが、そのほかの手法については全体の比率からみればほとんど行われていない状況にあるといえる。
このような広聴活動に対して、議会の広報活動の現状はどうであろうか。市調査によると、ほぼすべての市議会が広報紙の発行とウェブサイトの運用を行っている。町村議会にあっても議会広報紙は90%以上、ホームページは88%を超える水準になっている。また、市議会にあってはSNSの活用も35%を超える水準である。これら広報活動と議会報告会や住民アンケートの実施割合を比較すると、議会の広聴活動が十分行われていない状況にあるといえる。
(2)“集めるデータ”の拡充
広聴活動の現状をみる限り、議会が収集するデータは集団広聴から得られた“集まったデータ”が中心であり、調査広聴による“集めるデータ”は相対的に少ないと推測される。もちろん行政が実施する住民アンケートのなかに議会作成の質問を設定して必要なデータを取得している可能性はある。しかし、行政と議会では地域課題に対する視点や取組みは当然異なることから、それだけでは十分とはいえないであろう。“集まったデータ”は議会に関心が高い住民や意見の表明を希望する地域に積極的にかかわる住民のものである。これら住民が積極的に議会に伝えたデータは貴重であり政策立案のために有益なものであることは間違いない。他方、地域住民の価値観、ライフスタイルの多様化、議員定数の削減、自治体規模の拡大などが進むなかで、いわゆる“声なき声”や“沈黙する住民の声”を集め、分析し、政策立案に活かすためには“集めるデータ”も重要である。前述したように調査広聴の実施が難しい状況になってきてはいるが、面接法や留置法のさらなる創意工夫やウェブとの併用などデータを主体的に集める調査広聴の拡充を議会に期待したい。
以上、議会における広聴活動のフレームワークと現状を確認した。次回は議会の広聴活動の中心である議会報告会と今後さらなる工夫が期待される住民アンケートに焦点をあてて、その実施上の留意点などを考えてみたい。