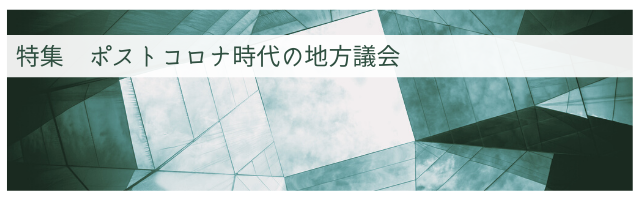大津市議会BCPの改定経緯
しかし、今回のコロナ禍対応では大津市議会BCPは必ずしも十分には機能しなかった。その検証の前提として、大津市役所が直面したコロナ禍の経緯について説明したい。
大津市役所では、4月11日に最初の職員の感染が確認されて以降、建設部と都市計画部で感染が拡大してクラスター発生と認定され、両部のフロアは閉鎖されるとともに、所属職員全員約260人が自宅待機となり、両部の機能は事実上停止した。4月20日には本庁勤務職員約1,200人は隔日交代勤務体制に移行したものの、感染した職員は11人に達し、職員間の感染の連鎖を断ち切り、来庁者への感染を防止するため、4月25日から5月6日まで本庁舎が閉鎖された。
大津市議会では、感染症に関して議会BCPの発動基準が明確ではなかったために、発動の是非について議論された。だが、発動すると、当時、市内で最も感染リスクが高いと想定された本庁に議員を参集させることになる。そのため、当面は5月18日の招集会議を開会するため、議員から感染者を出さないことを最優先してBCP発動は見送られ、全議員に登庁自粛を求めることとした。
一方で、議会局としては、全員が自宅待機となった両部への応援要員の出向や隔日交代勤務導入のため、最低限の議事運営と総務機能にマンパワーを集中させることにした。したがって、議員任期4年間における政策立案と議会改革の実行計画である「大津市議会ミッションロードマップ」は一時執行停止するとともに、感染回避のための議会運営の緊縮案を作成し、4月24日の議会運営委員会で決定された。
このような状況下で、議員にも現状の議会BCPが感染症対策としては十分ではなく、早急に改定することが必要だとの意識が醸成されてきた。議長立候補制度を導入している大津市議会では、議長選候補者の所信表明の場で八田憲児議員が議会BCPのバージョンアップを公約にして、5月18日に議長に就任した。早速、5月26日の議会運営委員会で、議会BCP改定のために政策検討会議の設置が決定された。6月8日の第1回会議から8月20日まで6回の政策検討会議を経て改定原案が作成されたが、改定議論の中で課題と感じた論点は以下のとおりである。
コロナ禍で見えた課題
先に述べたとおり、大津市議会BCPでは感染症に対しては明確な発動基準がなく、結果的に当初は議会災害対策会議の招集は見送られた。だが、議会BCPの意義を考えると、感染症対応においても発動の是非を議長による個別判断に委ねるのではなく、やはり具体的発動要件を明示しておく必要性があっただろう。
2点目は、議員や局職員の行動指針についても、地震や豪雨災害時とは異なるものが求められることである。自然災害時の議会BCP発動後の動きとしては、議会災害対策会議の委員以外の議員には、地域での支援活動への従事を求めている。だが、感染症対応では感染リスクを高める可能性がある活動を求めることは適当ではない。また、委員についても、参集すること自体が、感染リスクを高めることになる。その対策の一つとして、地方自治法100条12項に規定する協議調整の場である議会災害対策会議をオンラインで運営することは有効であり、これからはオンライン会議システムを日常的に使いこなせるスキルと装備が必須となろう。
3点目は、感染拡大の状況に応じた議会運営方法をあらかじめ想定しておくことである。多くの議会でとられた、「密」を避けるための本会議の出席者数の制限や、傍聴者数の制限に伴う議事公開手法の検討、質問時間の短縮などの措置を、あらかじめ状況に応じて想定しておくことが、迅速な対応に資する。特に庁舎や自治体関連施設を使えない状況に備えて、議場の代替施設を民間施設や行政区域外のものも含めて具体的に想定しておく必要性を今回は実感させられた。
4点目は、2点目、3点目とも関連するが、非常時の議会活動としては、議案審議が可能な状態を実現することが最優先で求められるため、オンライン議会実現への将来展望も必要である。
もちろん地方議会では、議員が当該自治体内の住民に限られることに鑑みると、参集過程における感染リスクは低く、ソーシャルディスタンスを確保できる限りにおいてリアル会議がベターであり、オンライン会議は、あくまで次善の策である。その意味からは、オンラインで行うこと自体がパフォーマンス化してはならず、手段と目的が倒錯しないよう自戒することも必要であろう。
また、議案採決する本会議までをオンライン化しなければ、議事機関としての本質的な意義は乏しいということもある。私は本会議のオンライン化には法改正が必要と考えており、これを解釈論で可能とする意見もあるが、議決無効のリスクを抱えてまで、オンライン本会議を強行するメリットは現場では認め難い。オンライン議会は、地方現場に大きな訴訟リスクを負わせる解釈論ではなく、あくまで法改正によって実現すべきものであり、その意味からは、現状では法改正へ向けての運動論についても検討が必要だろう。
5点目は、感染症対応では、都道府県の医療圏単位で具体的な対策がとられるため、基礎自治体としても必然的に広域対応が求められることである。また、議会内でのクラスター発生等の非常事態を想定すれば、議会機能維持のための基礎自治体議会間の連携も必然となる。
だが、法制度は議事機関の広域連携など想定していない。だからこそ、平時から任意に議会間の広域連携関係を築いておく必要性があるだろう。
6点目に、最も重要なことは、部分最適に陥らず、全体最適を目指そうとする意識を忘れないことだ。感染症における一例としては、医療従事者以外はその被害や脅威を目の当たりにする機会は自然災害と比すると乏しく、市民から議員への意見要望が第三者的に強い論調でぶつけられがちとなることに比例して、議員個人としても直接執行部に個別要望したいとの思いも強くなりがちだと感じた。だが、議会活動としての部分最適ではなく、自治体としての全体最適に資するという議会BCPの策定意義からは、議員個人よりも機関として活動することは重要なポイントであり、常に自戒することが求められよう。