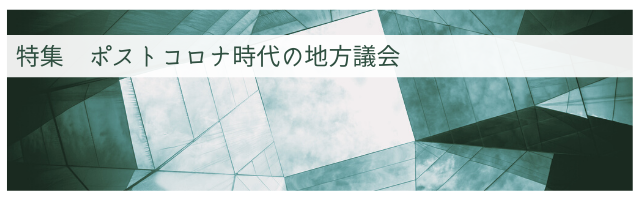大津市議会局長/早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員 清水克士
新型コロナウイルスの感染拡大は「新しい生活様式」を定着させ、「密」とは無関係ではない合議制機関の議会でも、これまでの常識など通用しない「新たな議会様式」が求められている。
そして、非常事態に直面したときに、議会機能を維持していくための羅針盤ともいえる議会BCPへの関心が高まっている。本稿では、議会BCPの策定意義から、クラスター発生による本庁舎閉鎖という前代未聞の事態に直面した大津市議会が、議会BCPを改定するに至るまでを記したい。
議会BCP策定の意義
議会BCPとは議会の業務継続計画であり、同志社大学大学院総合政策科学研究科の新川達郎教授の助言のもと、大津市議会が2014年に地方議会で初めて策定したものである。
2015年にはその設置根拠を大津市議会基本条例にも明記するとともに、実務的根拠としての大津市災害等対策基本条例も議会提案で制定している。
議会BCP策定の動機は、東日本大震災の際に多くの自治体で新年度予算が専決処分されたところにある。しかし、地方議会は憲法93条に設置根拠を置くが、平時だけのものとは規定されていない。つまり憲法は議会が議事機関として常に機能発揮することを求めており、非常時であることをもって、安易に専決処分に委ねることを許す法的根拠はないのである。
だが、実情としては、非常時には合議制機関であるがゆえの議会の弱みが顕在化する。警察、消防などの非常時対応を主任務とする組織は、例外なく迅速な意思決定を可能とする強固な指揮命令系統を有する実力組織である。しかるに議会では、議事運営以外には議長の指揮命令権は法定されておらず、意思決定にも時間を要する合議制であるなど、議会は最も非常時対応に向かない組織ともいえるだろう。
だからこそ、法では想定されていない非常時における議会の体制、運営等の行動指針を独自に定めておくことは、議事機関として常に機能発揮するためにはもちろん、自治体としての災害対応の全体最適化のためにも必須といえるのである。
大津市議会BCPのポイント
先に述べたことからも明らかであるが、議会BCPの第1のポイントは、非常時の指揮命令系統を議会に確立しておくことである。大津市議会では、執行部で災害対策本部が設置されると同時に、「議会災害対策会議」が自動的に設置され、会派代表者に対する議長の指揮命令権を確立するとともに、欠員発生時の権限委譲体制も明示している。
第2のポイントは、議員が得た地域の被災情報や市民要望は議会災害対策会議で集約して、執行機関に伝えることをルール化することである。それは、議員が個々に直接、執行機関に情報伝達すると、結果的に執行機関の非常時対応を混乱させることになりかねないからである。全体優先度が必ずしも高くない個別要望は、飽和状態にある執行部にさらに負荷をかけるだけで、災害対応の全体進捗を阻害してしまうという合成の誤謬(ごびゅう)を生むのである。
第3のポイントは、具体的な行動指針を定めておくことである。例えば地震時には、議会災害対策会議の委員は震度5強以上で即時本庁舎に参集することになるが、それ以外の議員は、初動3日までは地域の構成員として活動し、7日目までの中期に必要に応じて全議員を招集する。中期における議会災害対策会議では本会議、委員会活動の再開に向けての準備を整え、1か月目までは議案審議を暫定的に行えるレベルでの議会活動を、それ以降は平常時レベルでの議会活動に復帰させることを目標としている。