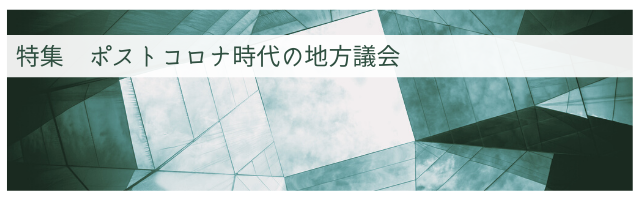3 オンライン本会議の開会──強気に突破する議会は登場しないのか
オンライン本会議の実施に向けて重要なのは、法改正ではなく法の解釈とそれに基づく実行化への意欲と行動力ではなかろうか。
前述の総務省自治行政局行政課長が2020年4月30日に通知した「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」では、各議会議員が委員会に出席することは不要不急の外出には当たらないものとし、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することで委員会を開催することは差し支えないとしている。したがって、予算審査特別委員会に予算案を付託すればオンライン会議は開催可能である。付託を受けた委員会は質疑、討論を経て採決し、年度末までに本会議を開催し採決を諮ればよい。
同通知でオンライン本会議についても補足として、地方自治法113条及び116条1項における本会議への出席について、「現に議場にいることと解される」という記載があったために、オンライン会議を不可としたものである。「解される」程度のレベルであれば明確に「禁じてはいない」と解することもできるのである。つまり法解釈の問題といえる。
同様に地方自治法103条2項の議長任期では、議員任期の4年の下では、平然と申合せ事項としながら1〜2年で議長を選出して対応している議会が国にオンライン本会議を求める意見書を提出するのはアンバランスな感覚であり、首をかしげたくなる。
翻って、オンラインでの本会議の開会と時間短縮や専決処分の乱発を認めることを比較したとき、どちらの選択が議会としての責任を果たしたと住民の前で胸を張っていえるのであろうか。オンラインによる会議を単なるICT推進のツール整備と捉えてはならず、住民のために議会を開くという意思を強く持ち、技術化を図ることが重要なのである。法解釈を超えてオンラインでの本会議を実行化する議会の登場を待ち望む。
加えて、インターネット議会中継・録画システムを未導入の議会には、早期の整備化を求めたい。議場での3密を避けることを理由にし、市民の傍聴を禁止・制限・自粛した議会は、これ以上「議会の密室化」を続けてはならないのである。
4 今後の議会運営と議会改革──議会と住民との交流事業の再開を
早稲田大学マニフェスト研究所の議会改革度調査は、「住民参加度・情報公開度・機能強化度」の3分野をベースにして改革度ランキングを実施しており、極めて的を射たものといえよう。コロナ禍における議会運営と議会改革の進め方についても、この3分野をベースに考えるべきである。つまり、コロナ禍の議会運営を考えることはウィズコロナ、ポストコロナの議会のあり方を考える上でも好機といえるのである。
議場の3密化を避ける方法では、大きく二つの方法が考えられる。
一つは、議会ICT化を進めることである。執行機関側を含めオンラインによる本会議を実行することとインターネット中継を強化することである。
もう一つは、庁舎及び本会議場での徹底した感染対策を行い、3密化を避けた上で通常どおり議場で運営を行うことである。徹底した感染対策については、病院がそうであるように、国立感染症研究所などの情報をもとに議員・事務局職員・住民も一体となって学習し、本会議場の感染予防に当たることも議会改革の一つとなろう。
さらに、コロナ禍で停止した議会報告会・意見交換会をはじめとする議会への住民参加事業をどのように行うかについても注目したい。今後も、何度も襲ってくるであろうコロナの波に対し、住民と議会の交流事業の再開への道筋を立てることが、議会改革を行う上で重要なポイントとなる。
東日本大震災後の一例になるが、宮城県七ヶ浜町議会はいち早く仮設住宅の住民を対象に政策要望を聴く対話集会を始めたという。議員たちは震災直後の虚無感から立ち上がり、消化しきれないほどの悲劇と向き合う日々で淡々と「討論のヒロバ」を復元していったという。危機下だからこそ主権者たる住民を第一義的に考え、議会運営を継続する不断の努力と議会改革を進める強固な意思こそが求められよう。
最後になるが、北海道自治体学会議会技術研究会では140人の会員に向けて「新型コロナにかかる議員向けアンケート調査」を緊急実施した。集計結果が出るのはまだ先のことであるが、質問項目を一読いただき、一考されることを願う。
■参考文献
◇河北新報社編集局編『変えよう地方議会 3.11の自治に向けて』(公人の友社、2011年)
■「新型コロナにかかる議員向けアンケート調査」原文(北海道自治体学会議会技術研究会)