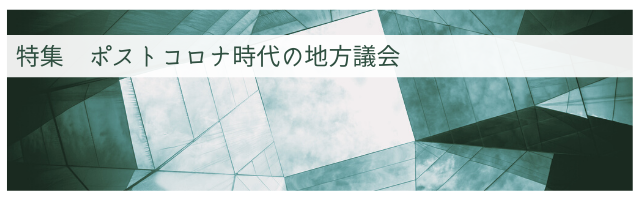北海道自治体学会議会技術研究会共同代表(前北海道芽室町議会事務局長) 西科 純
1 コロナ禍の議会運営──業務継続を念頭に置いたか
現在、私は公立芽室病院の事務長の任務に就いている。
初めての病院勤務から2年を経過し、芽室町議会事務局長として議会改革を担った経験が試されている。病院経営改革の使命に加え、新型コロナウイルス感染症の対応に追われる日々が続いている。緊急時の病院組織にあって、その意思決定には冷静かつ迅速さが求められ、合議制だけではなく、ときに病院長の独任制も求められる。事務長の任に当たって感じたのは、病院経営と議会運営は類似している点が多いということである。例えば院内に設置する委員会である。当院でも29の委員会が構成されているが、これらは議会での常任委員会に似ており、院長会議は議会運営委員会に、経営改革委員会は議会改革特別委員会に、管理職会議は全員協議会に似たイメージがある。
院内には新型コロナウイルス感染症対策委員会も設置している。細部にわたる対応を協議し実行化につなげる重要な役割を担っている。私は議会BCP(業務継続計画)を策定した経験から、災害時に対応する病院BCPを迅速に策定したが、コロナ禍にあってBCPを応用し各フェーズに沿って対応している。病院経営改革と議会改革のキーワードが「対話」である点も興味深い。
コロナ禍における病院経営と議会運営を比較すると、病院はコロナ禍にあっても直ちに休診することはできない。院内クラスターが発生する最高フェーズに至る直前まで外来・入院患者を受け入れて診療、予防接種、手術、人工透析などを続けるのが使命である。自然災害が発生しても、あらゆる手段を講じながら業務継続を最優先し、住民の生命と健康を守るという絶対的な使命を果たすべく粘る。
都道府県庁をはじめ、市役所、役場などの行政機関もまた同様である。有事では行政機能が簡単にストップしてしまうと、住民の生活に支障を来す。災害時には庁舎が存在する以上、あるいは庁舎が消滅してもなお住民に最も身近な役所が業務を継続せざるをえない。
一方、このコロナ禍の自治体議会の運営はどうであったか。感染拡大防止を念頭に置いて、創意を尽くし、住民の福祉向上を目的に自治体の最高意思決定機関としての業務継続化に取り組んだといえるであろうか。北海道において、独自の緊急事態宣言下での3月定例会は、新年度当初予算の審査期であり、また政府の緊急事態宣言が解除された6月定例会は、感染・経済対策上の補正予算案という重要議件の審査期であった。私が報道や様々な情報から知りえた限りでは、全国の議会で運営面において数々の混乱が生じたようである。
定例会開会におけるコロナ対策としては、手指消毒、会議室の消毒、検温、マスク着用、議場の換気、座席間隔の拡幅、傍聴の自粛・制限・禁止、一般質問・質疑の中止・取下げ、会期の短縮・延長から、議員の出席自粛、文書通告・書面報告という対応がなされた。傍聴制限・禁止や自粛を呼びかける議会もあり、住民から批判を受けたとする報道が見られた。冷静に考えると、コロナ禍以前の各議会の議会改革の差が如実に表れたにすぎない。議会BCPを応用する議会がその手法の先見性を取り上げられたりもしたが、本来のBCPは業務停止を念頭に置くものではなく、可能な限り業務継続を果たすためのものでなければならない。
傍聴についても、インターネット中継の視聴を呼びかけることは当然のことであるが、それをできない住民のことを考えれば、議事堂の別室にモニターを設置して視聴してもらうなどの対応をすべきであろう。
一方で、3密化を徹底的に避け、感染対策を講じた上で通常どおりに運営した議会もある。私が議会サポーターを務める北海道内の別海町議会と沼田町議会がそれに当たる。特に別海町議会は「別海町議会新型コロナウイルス感染予防対策に係る会議規程」を定めた対応が光る。両町議会ともに議会改革を精力的に進めている最中であり、一般質問での登壇議員も多く、質疑及び常任委員会での討論も活発に行っている。したがって、創意の上で一般質問やその他の議件を完遂し、ともにコロナ関連議案の専決処分を行ってもいない。別海町議会では、それ以前から質疑の通告制度を取り入れることによって無駄な時間を全く費やしていないことから、新年度予算案についても何ら問題なく審査を行っている。
全国では、議会改革を標ぼうする議会がオンラインによる委員会運営への挑戦を見せたが、総務省からの通知(「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」(2020年4月30日)の前に撃沈し、「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書」の提出(同年6月9日)にとどまったのである。
2 専決処分の乱発──東日本大震災の教訓はどこへ
私が、コロナ禍の議会運営で最も問題視しているのは、専決処分の乱発である。
3月定例会での新型コロナウイルス感染症に関する予算に係る専決処分を行った北海道内の議会は、北海道議会及び市町村議会総数180のうち、109にも上った(道議会政策調査課調)。専決処分はいうまでもなく首長側の権限に委ねたものであるが、議会側が容認したものであり、事前に議会側と調整の上、運用したことが読み取れる。
専決処分の乱発で思い起こすのは、2011年3月11日に発生した東日本大震災後の被災した議会運営である。3月定例会の最中にあって、被災した議会では年度末までの20日間の対処方法が問題となった。このとき、新年度予算未成立を問題提起したのは自治体学会であったが、学会員から大別して二つの提案があった。
一つに、議会招集は困難との前提で、地方自治法179条(議会を招集する時間的余裕がないこと)に基づく首長の専決処分で当面必要な暫定予算の成立を期し、ある程度落ち着いた段階で改めて本格予算を上程する。
二つに、ともかく議会を招集し、突貫ででも当初予算の成立を期し、一方で不都合が生じた部分は後に補正する。
これらの案に対して、震災対応に追われている職員に負担を強いるのはどうかという学会員の指摘もあった。同学会では、「予算の正当性は住民の代表機関による議決によって担保されなければならない」という筋論に立ったが、震災の混乱に放り込まれた自治体のリアリティがせめぎ合い、次のような見解が示された。「議会は議場で開かれなければならないという決まりはない。学校の空き教室でも、青空の下でもいいから、できるだけ速やかに議会を招集して新年度予算を審議し、議決すべきだ。津波がすべてを押し流したとしても『議会があり続ける限り、必ず自治体は蘇る』とのメッセージを被災した住民に発することが重要だ」というものである。
しかしながら、現実には多くの自治体が駆け込みで議会を招集し、拙速に予算を成立させ、震災復旧のリアリティへ戻っていく。震災後の議会招集を「震災からの自治の再興」という視点で取り上げた報道も皆無であり、住民の多くも議会を前述のとおりに捉えることはなかった。震災前には「議会こそが住民自治の根幹である。しかし惰眠をむさぼったままの議会では、住民の信頼を勝ちえることはできず、場合によっては議会不要論さえ台頭しかねない」との警句が盛んに発信されていたものの、震災後も議会に向けられた住民の冷ややかな視線が変わることはなく、震災対応に追われた日々の中で議会の存在は一層希薄となったのである。
壊滅的な被害を受け、議員までもが亡くなり、議場そのものが流失した東日本大地震と今回のコロナ禍との比較には無理があることは承知の上である。しかし、コロナ禍の議会運営は、東日本大震災禍に比べて運営を協議するための時間的な余裕はあったはずである。まして、北海道内の議会は、胆振東部地震(2018年9月6日、最大震度7)で停電及びブラックアウトを経験し、その後の議会運営も課題となった。この際も復旧に当たる執行機関側に遠慮する議会が多くあり、批判を招いたにもかかわらず、今回のコロナ禍で災害時対応の検証がなされていないことが露呈した。早稲田大学マニフェスト研究所が2019年2月に調査した結果によると、議会BCPを策定しているのは全国の約半数、北海道内は2割台と極めて少ないのが何よりの証しである。
3密の回避のために短縮運営し、重要な議件について専決処分を容易に認める議会には、改革や活性化などは程遠い。行政のチェック機能を自ら放棄し、密室化を自ら進めているといえよう。さらに専決処分した重要議件には、市民への徹底した説明責任が残る。コロナ禍で報告会の開催が不可であれば、議会公式ホームページやSNS、臨時議会広報紙の発行によって明確な報告・説明を迅速に行うべきであろう。その点に何ら違和感を覚えないとすれば、議会は機能停止ばかりか思考停止しているといえる。