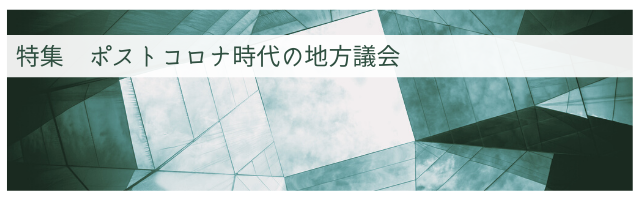3 「最初の1回の壁」を越える
「習うより慣れろ」というが、IT/ICTもその類いだ。技術に強い、機械が好きでなければ分からない技術であった時代は長かったし、今もこれからもずっとその課題は残るとしても、それでもずいぶん分かりやすくなった。現在のいちばんの障壁は、未経験者の抵抗感や苦手意識ではないだろうか。それも、スマートフォンやスマートフォンのコミュニケーションアプリであるLINEの家族間利用などの拡大で、ハードルは下がったと見る。
前掲のZoomは、ウェブ会議の中でもかなり使いやすい。あとは「最初の1回の壁」をどう越えるかだが、「集合して対面で話し合うことができない状況」は、いわば外堀を埋める役割を果たす。埋まった堀を渡って低くなった壁を越えることに手助けが必要な議員には、対面で接触してサポートや共同での試用が可能なうちに、何かの機会をつくってはどうか。実験でも試行でも研修でも、何でもよい。筆者が前掲の市議会有志の勉強会でZoomを使ったときには、初利用の参加者がZoom利用にも関心を持って参加し、同僚のサポートを受けながら「最初の1回の壁」を越えた。その後、委員会での利用が検討されていると聞く。「仕事だから」と圧迫された状況で公式の機会に最初の1回を設定するよりも、練習と思える「使える」機会で試行し、「使える」体感を得ることが、コロナ禍の拡大が落ち着いた時期にも対面での話し合いの補助ツールとしての活用につながりやすく望ましいだろう。
「壁」は、身近な媒体や機械を選ぶことでも下がる。Zoomでいえば、スマートフォンでも接続できる。画面が小さければ、最近のスマートフォンならテレビに出力できる。また、会議を設定する側が有料アカウントであれば、電話回線で音声のやりとりができ、インターネット経由の音よりもむしろよい。資料を手元に置いて電話で参加するのも悪くない。タブレットが1台あれば、Zoomだけ、あるいはごく限られたアプリだけ入れて見えるようにするのはどうか。
また、LINEなら、家族間で利用者も多いだろう。データ通信量はZoomの方が少なくできるが、利用機会が多いだけになじみやすさは高い。LINEのグループ通話では議会の話し合いの媒体としてはやや非力だが、それでも、「集合して対面で話し合うことができない状況」からは抜け出せる。
この記事の読者は、おそらく問題なくZoomを利用しているだろう。そうした読者に「最初の壁」の越え方を語るのは、「全員が(共通の)非対面での対話の共通媒体を持つ」ことが、議会として「集合して対面で話し合うことができない状況」に備える必要があるからだし、この共通媒体を持つことができれば、その先に別の可能性が開けるからだ。
4 IT/ICTは「対面と完全互換」の媒体ではない
筆者はIT/ICT機器が使えるかどうかで議員の資質の優劣が分けられると考える立場には立たない。また、IT/ICTは対面にそっくり置き換えられるとも思わない。
ただ、「集合して対面で話し合うことができない状況」に、議会としての機能を止めないための基盤は整備しておく必要があることは間違いない。専決処分にすべてを委ねて追認すればよいなら、議会は不要だ。むしろ、これからも状況が変動する現在進行中のコロナウイルス感染症という災害に対して政策的にどう対応するか、議会にはヒロバとして果たすべき役割が増しているといえる。
IT/ICTは対面とまるごと互換できるものではないが、一部の機能の代替はできる。ウェブ会議の中にブレイクアウトルームという個室のような分科会の場を設けることもできるが、この機能は対話の促進に有効である。さらに、IT/ICTによって、対面ではできない機能も発揮させることができる。距離という限界を超えて話し合うことができるツールを議会の共通媒体とすることができると考えてみればよい。委員会や打ち合わせを開催する時間設定に選択肢が増え柔軟に組むことができる。市民との交流や対面調査や専門家知見の活用も、「直接対面で」という機会との互換には届かなくとも、直接対面で設定するよりはよほど柔軟に、遠方のあるいは多忙な対象者とつながることができるだろう。議会内だけでなく、Zoomという言葉がこれだけ認知されたということは、これに代表されるウェブ会議の経験が増大し、社会の中で共通媒体として現れつつあるといってよい。より優れたツールはこれからも登場するだろうが、ウェブ会議という手法をIT/ICT利用の遅れが指摘されていた日本社会でこれだけ広げたことは大きい。この機会に「壁」を越え、距離と移動の制約を超えて話し合うことができる共通媒体を得ておくことは、議会にとっても議員にとっても必要であり有益ではないだろうか。
もちろん、ツールを利用してみただけでは十分ではない。規定や規則、条例などの見直し、制度上の対応は不可欠である。総務省の見解(3)も出された。より利便性のある、話し合いにとって効果のある制度設計と運用をそれぞれの議会の模索と先駆例の共有で進める必要がある。