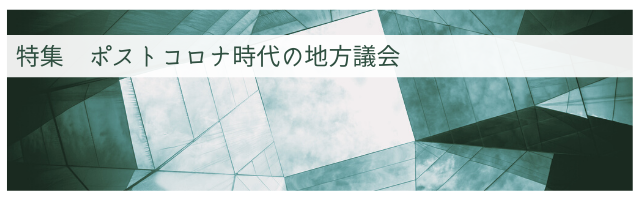龍谷大学政策学部教授 土山希美枝
1 新型コロナウイルス感染症と自治体議会
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、1.5波なのか2波なのか分からないが再び感染者数を上昇させている。個人として社会としてその病にどう備えるかということは大きな問題だが、本稿にとっては、ワクチンや予防薬が開発されて世界的に安定して安価で供給されるようになって、心配な症状があれば検査を受けられるようになって、悪化した場合の医療資源も確保されて、インフルエンザと同じような存在になるまで「集合して対面で話し合うことができない状況」がいつでも現れえるのだ、ということを指摘しておきたい。1年か、2年か、少なくともそうした時間感覚で。
この間、その状況によって、議会日程の短縮や傍聴の停止を行った議会もあるという。しかし、「集合して対面で話し合うことができない状況」のたびに議会がそうした対応をするなら、それは議会での議論や対話自体が「不要不急」で、執行機関の裁量に預けていれば事足りるということの証明にほかならない。
「集合して対面で話し合うことができない状況」に「議会として」どう対応していくかを、「次の波」までに備えるのが目前の課題だろう。
2 安直だが安易になったIT/ICT
そこで、安直な、ということは以前からいわれていた手段だが、IT/ICTである。茨城県取手市議会のZoom(1)(ウェブ会議)による開催はすでに先駆例として大きな注目を集めているが、筆者も、3月末に滋賀県のある市議会の有志とZoomで研修を行った。この間、利用した議会も増えているのではないか。
議会におけるIT/ICTの活用は、議会改革を評価する項目でもあり、議会単位の活用は早くはないが進んできた。全国市議会議長会の調査によれば(2)、2018年に本会議を生中継・あるいは録画で提供している市議会は全体の8割となる。おそらく議会事務局職員の熱意と努力が求められるSNSでは、Facebookで約1割にとどまるが、ホームページは、情報の充実度や更新頻度はともかく、ほぼ標準装備だといえるだろう。
一方、議員のIT/ICT利用状況や議会での利用環境を見れば、前掲の調査では、議員が希望すれば本会議場にパソコンを持ち込める議会が11.0%、タブレットは14.0%だ。委員会室だともう少し割合が上がるが、2割にも届かない。議員の多くが日常的に利用していれば、このような数字ではないだろう。使っていない道具を活用しようとはなかなか思わないし、便利を実感していない道具を使おうとは思わないのが自然だ。利用、活用の壁は制度ではなく、その利用がどれほど有益なのかという理解の問題でもある。通信環境や機材の整備は、この機にこそ進めよう。「必要」なのだと自信と覚悟をもって議会として言おう。そうなのだから。
ところが、今回の「集合して対面で話し合うことができない状況」への対応を考えれば、どうしても、IT/ICTを利用せざるをえない。多くの議員が、議会が、その責務を果たそうとすれば、IT/ICTを経験することになるだろう。この時期、これまでIT/ICT利用の少なかった議員が多く触れるツールの一つがウェブ会議、はっきりいえばZoomではないだろうか。なぜならば、比較的安易、たやす(易)くて安いからだ。
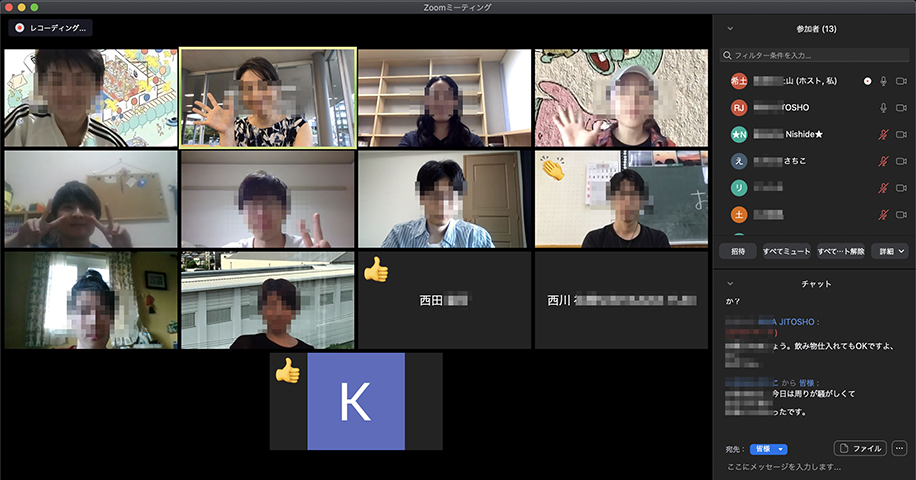
Zoomによるウェブ会議の画面例(筆者担当講義)