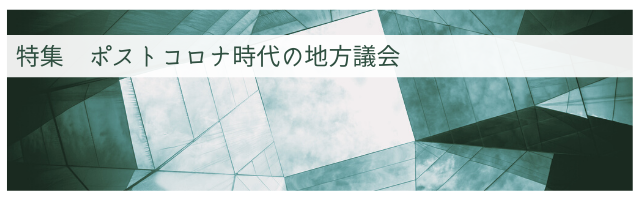3 東日本大震災を契機に
くしくも2011年に起きた東日本大震災も3月定例議会中であった。当時の被災地議会でも、会期や議事日程を短縮し、議会活動の自粛を図った。新型コロナ同様に、非常時対応に急務であった首長側に配慮した面もあるが、当時の状況下では、人命捜索、がれき撤去など救助活動、復旧活動が最優先事項であり、また議員の中には消防団に所属して地域活動を行っているものも多く、議会側としても議会どころではなかったという側面がある。
なお、当時は岩手県陸前高田市をはじめ、庁舎が被災・全壊し、議事堂ではなく仮設庁舎の会議室に参集した議会も少なくない。その意味では、有事の際に議事堂以外に参集して会議を行うことはこれまでも行われてきたことではあるが、詳しいことは後述することとしたい。
東日本大震災を教訓に、さらに遡れば阪神・淡路大震災を教訓に、全国では非常時の議会・議員の行動指針を策定する動きが出てきた。議会災害対応指針・マニュアルを策定する議会、また滋賀県大津市議会をはじめ、東日本大震災後に国が自治体に策定要請した行政版BCPを議会へ輸入し、議会版BCPを策定する議会もある。
これによって、非常時には議会として災害対策会議を設置し、情報共有や対応方針協議を行うなど主体的な活動を行おうとする議会が増えた。
特に、議会による非常時のICT活用が有効とされ、観測史上初、東北直接上陸となった2016年の台風10号災害では、岩手県久慈市議会がタブレット端末を通じて議員の安否確認や被災情報の共有を議会内や行政間で図る等、ペーパーレス(紙削減効果)の観点だけでなく、タブレット端末によるICT活用の可能性が議会で高まった。
4 取手市議会が切り開いた議会の可能性
茨城県取手市議会は、コロナ禍の4月7日、取手市議会災害対応規程に基づいて「取手市議会災害対策会議」を設置し、翌8日に対策会議をオンライン会議サービス「Zoom」を利用して行い、議会に集まることなく話し合いを進めた。
取手市議会の特筆すべき点は、規程上、地震や津波、気象災害等以外にウイルス感染症は想定・明記していなかったにもかかわらず、柔軟な判断で災害対策会議の設置を図った点。さらに、規程上、参集場所が議事堂という物理的空間であったにもかかわらず、オンライン空間での開催を図った点。付け加えて、タブレット端末を全議員が所有していなかったにもかかわらず、スマートフォンやパソコンなどあらゆるツールを模索して行った点である。
この3点は、「ルールにないからやらない、ルールと違うからやれない、環境が整わないからやれない」、「だから、やらない」といった行政的体質とは異なり、まさにルールメーカーである議会が、ルール・オリエンテッド(事実前提)ではなくミッション・オリエンテッド(価値前提)で、「だけど、やろう」と動いたことによって、ICT活用による議会の可能性をさらに切り開いたといえる。
その後、取手市議会はオンラインを使って同会議を重ねたほか、議員の体調確認も兼ねて全議員による協議の場での活用も図った。さらに、差し迫った6月定例議会の運営協議を行うため議会運営委員会への導入も試みようと、議会運営委員会協議会としてオンライン開催したのである。