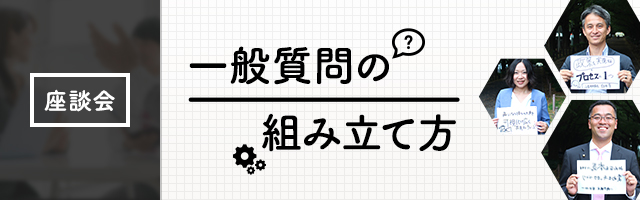自治体議会の一般質問は、議会の役割・権能の中でも重要なものの1つです。質疑が議案に対するものに限られているのに対して、一般質問は行政運営全般に対して行うことができるからです。しかし、重要な権能とはいえ、行政を動かすような効果的な一般質問を組み立てるのは容易ではないようです。一般質問を組み立てるにあたって、議員は様々なステップを乗り越えていく必要があります。質問のテーマ探しから始まり、質問を根拠づける調査、質問の構成、答弁の引き出すための調整、そして一般質問の本番、その後のフォロー…。
本座談会では白井亨さん(東京都小金井市議会・2期目(写真左))、近藤美保さん(千葉県流山市議会・1期目(写真中央))、金子壮一さん(埼玉県八潮市議会・2期目(写真右))にお越し頂き、それぞれの一般質問に対する考え方や取り組み方についてお話を頂きました。3名とも、若手として真摯に取り組みを続け、着実に一般質問の実績を重ねてきた方々です。
2018年11月26日公開の(上)編に引き続き、今回は(下)編をお届けします。

――それでは、次はいわゆる答弁調整についてお聞かせいただけますか
金子:執行部は、基本的に調整しないというスタンスを取っていますが、自分の中では調整は大事な時間だと思っています。「これとこれを聞きます」と調整の場で10くらい出しておいて、実際に議会の場で聞くのはそのうちの2、3とするくらいがうまくいくように思います。
白井:私は議員になった頃は、ほとんど調整はしませんでした。それで問題提起ができたこともあれば、まったくうまくいかないこともあって。復帰して今、通算4年経つのですけれど、最近はかなり丁寧に調整をするようにしています。行政執行権は向こうにあるのですから、最終的に執行部に動いてもらえないとうまくいきません。言いたいことが10あったとしても、実際に実現が難しそうだから聞いても仕方ないことは聞かないとか、丁寧にやっています。メリハリをつけ、ここと決めたことは徹底的にやらせてもらいます。
あと、実は「調整」という言葉はあまり好きではなくて、お互いの「ヒアリング」だと考えています。自分が聞きたいことを相手に伝えて、できることを最大限引き出す。聞きたいことを通告でつまびらかにします。時々は調整してないことを織り交ぜて聞いたりします。
近藤:私は、議員になって1年位は、調整ということがわからなくて、結果的に一発勝負みたいになってしまっていました。先輩に「お前調整しないのか?」みたいなことを言われて「えっそれはどういうことですか?」みたいなやりとりをしながら分かっていって……(笑)。それからは丁寧にやっています。
一発勝負で一般質問をつくると、政策が成熟している介護の分野などはまだいいのですが、まだ成熟していない子育ての分野などでは、そもそも執行部も計画を作っていなかったり、トンチンカンな方向性のものが出てきてしまったりして、困ることもあります。こちらから課題を出して調査を依頼して時間をかけてやってもらっても、数字的に間違った変なガイドラインができてしまったり…。それは申し訳ないから、それからは、原稿も想定答弁もこちらの意図も事前資料も出して、「ここが課題で、ここが足りないから、これをやってほしい」と具体的に伝えるようにしています。いろんな議員さんにプレゼンしたり、市民にもプレゼンしたり、もちろん市役所の職員の方にもプレゼンするなど、あらゆる場面をとらえて説明します。
一般質問は、背景のレクが30分くらいで、実際の質問は10分くらいで組み立てています。「国はこう動いていて、市の課題はこれで、こうすれば成果がでると思う」と意図を丁寧に言わないと伝わらないと感じています。
――「一般質問のテーマ設定はどうすべきか」という悩みをもたれる方もいらっしゃると聞きます。アドバイスをお願いします。
白井:私自身の一般質問の設定の仕方をご紹介すると、緊急度、重要度が高いものから優先的に取り上げるという流れになります。選挙の時に掲げたマニフェスト・政策であったり、日々住民から相談を受けたり自分で課題発見したりする中で、特に重要なものや短期的には重要でないけれどタイミング的に今やっておかなければならないもの、そのあたりをピックアップして優先順位をつけていきます。また、タイミングのことをいえば、次年度の予算編成につなげたいのであれば、6月か、遅くとも9月にやっておかないといけないなど、様々な要素を組み合わせながら決めています。
もちろん、突然降ってわき出る市政課題もありますから、そちらに時間が取られてやりたいことができないこともあります。また、通告前からそのテーマについて職員と話をして、現状を聞いた上で取り上げるかどうかを決めているので、その話の中で、タイミング的にずらした方がいいと感じるものは次に送ることもあります。そのようにして空いてしまった時には、若干準備不足のものを取り入れるということもあったりはします。
質問数は、大きく2問か3問ですね。3問にすると、だいたい最後に時間切れになります。原稿もたくさん作ってしまうし、原稿にないことや、答弁に対しても色々言いたくなっちゃうので。
小金井市は、一問一答でも複数まとめて聞いて返してもらう形でも、やり方は自由ですが、僕は基本的に一問一答の方式でやっています。聞いている方もわかりやすいので。
近藤:もし一般質問のテーマが見つからないということでしたら、なにかひとつ、「専門性を持つ」ということを心がけたらいいのかなと思います。せっかく公平に与えられている機会ですから、ただ数字を聞いて終わりとならないよう、ひとつ「これは本当に興味がある」ということについて、誰にも負けない、エッジの立った質問ができるように専門性を磨いていくことです。
白井:得意分野を持つのはいいですよね。ほぼ毎回その分野で切り口を変えてやり続ける議員さんがいます。聞いていて、またかと思うこともあるけれども、突き詰めるということは、物事を動かしていくことに繋がると思います。
金子:うちは一問一答で、制限時間60分。答弁も途中で切られます。今回4問やりましたが、いつも時間との戦いです。
私はいつも多くのストックの中から絞れずに、だいたい通告の当日の朝に決めています。決め方としては、まず、一般質問は「議会だより」に後日掲載されることも考慮し、行政として市民に知らせなければならないことは何なのか、市の各部署の話も聞いて知らせたいことを考えて質問を設定しています。次に、市民から託された政務活動費をもらって活動している以上、必ず一般質問の半分以上は、現地を見たものについて取り上げることにしています。そして、市民からの切実な声、目をつぶってはいけないというものがあれば組み込む、これらの3本立てで考えると、決め方が楽になると思います。
――2019年4月には統一地方選挙があります。多くの新人議員さんが当選されてこられるかと思いますが、座談会の最後に、これから初めて一般質問に立つ新人議員さんに向けて、メッセージをお願いします。
金子:一般質問で大事なのは、行政職員を「本気にさせる」ということでしょうか。我々は、課題意識があって議員になっているわけで、どうしても行政職員との温度差を感じる時はあります。職員を本気にさせるのは、ときに市民の声であったり、ときに近隣の頑張っている自治体の姿であったりします。それらを一般質問の場を通して職員と共有して、火をつけていくことです。自分自身が本気になって調べ、その熱を皆に伝えていくのが議員の役目だと思います。

一般質問は「みんなを本気にさせる変わるキッカケづくり」
近藤:私は、失敗を恐れないで思いっきりやったらいいと思います。むしろ、空気は読まなくていいのではないかなと。私自身、野次られながら一般質問を行ったこともあるのはいい経験になりましたし、若い人、外から来た人というのは、異質なものを議会に入れていく役割があります。とんでもない方向から来た質問でも、新しい気づきを議会にもたらしてくれることがあります。
ただ、プレゼンテーションの方法は勉強した方がいいです。せっかく質問をしていても何を伝えたいのか分からないのはもったいない。「レーザートーク」、つまり短く、わかりやすい言葉で詰めていくことが重要です。

一般質問は「声になり得なかった声を可視化して広く共有するチャンス」
白井:僕も同じで、失敗していいと思うんですね。早いうちに失敗した方がいいので、思いっきりやった方がいい。失敗したほうが成長も早いというのが僕のモットーで、最初に議員になったとき、新人同期5人の中で、何をするにしても最初にしようと決心し、一般質問でも定例会での質問も、何か失敗するならそれも自分が先に、と考えてやっていました。もちろん懲罰を受けるような失敗はだめなので常識の範囲内で。また、議会の雰囲気、多様性を認め合う文化ができているかどうかというのはそれぞれの自治体にもよるので、一概には言えないのですが、怖がらずに、やりたいことをやるのがいいと思います。
――一般質問を行うこと自体を目的とするのでなく、一般質問を課題提起のきっかけ、行政職員や他の議員と共有する場としてとらえ、長期的な視座で課題解決に取り組んでいく姿勢が、お三方共通して言えることかと思いました。課題に納得感を持って共有してもらえるためにも、根拠となる数値や背景を入念に調査・準備し、執行部との事前の調整やプレゼンテーションの方法にも気を配ることが大事という重要な指摘も頂きました。この度は座談会にお集まりいただき、ありがとうございました!
※本座談会の(上)(2018年11月26日『議員NAVI』掲載)はこちらからお読みいただけます。(編集部)