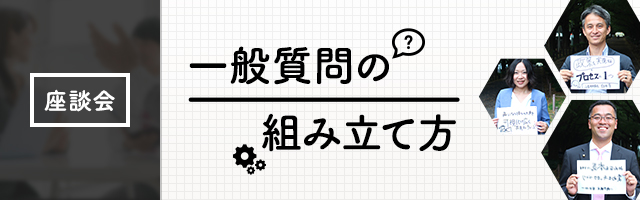自治体議会の一般質問は、議会の役割・権能の中でも重要なものの1つです。質疑が議案に対するものに限られているのに対して、一般質問は行政運営全般に対して行うことができるからです。しかし、重要な権能とはいえ、行政を動かすような効果的な一般質問を組み立てるのは容易ではないようです。一般質問を組み立てるにあたって、議員は様々なステップを乗り越えていく必要があります。質問のテーマ探しから始まり、質問を根拠づける調査、質問の構成、答弁の引き出すための調整、そして一般質問の本番、その後のフォロー…。
本座談会では白井亨さん(東京都小金井市議会・2期目(写真左))、近藤美保さん(千葉県流山市議会・1期目(写真中央))、金子壮一さん(埼玉県八潮市議会・2期目(写真右))にお越し頂き、それぞれの一般質問に対する考え方や取り組み方についてお話を頂きました。3名とも、若手として真摯に取り組みを続け、着実に一般質問の実績を重ねてきた方々です。

――本日は座談会にお集まりいただき、ありがとうございます。座談会の進行は『議員NAVI』編集部が務めさせて頂きます。まずは、皆さんの自己紹介、そして皆さんの議会のご紹介をお願いします。あわせて一般質問に対する考え方も簡単にお話ください。
近藤:流山市議会議員の近藤美保です。流山市議会の女性議員は全28名中7名で、およそ25パーセント。全国平均より若干多いくらいです。子育て世帯が多い流山市ですが、議会内で現役子育て世代の女性議員は私のみです。子育て施策については、日々環境が激変する中、現役の当事者でなければ見えないことも多いと思っているので、現役代表として責任があると感じています。私自身は完全無所属ですが、保守系の最大会派に所属しています。
流山市議会では、一般質問は全28議員中、大体20人前後が行なっています。私の一般質問のスタンスですが、初当選後右も左もわからない状況でも、とにかく一般質問を行い、それを通して執行部等からも情報を引き出し、を繰り返す中で、発言力を積み上げていきたいという思いでやってきました。

「一般質問を通して発言力を増していきたい」と語る流山市議会議員の近藤美保さん
金子:八潮市議会議員の金子壮一です。八潮市議会は定数21名で、その中で保守系の9名の会派に属しています。市政に関与していくためには数の原理をうまく利用することも必要だといった考えもあり、現在の会派に所属することを決めました。比較的最近八潮市に引っ越してきたということもあり、外からの視点で市政を変えていこうということを自分自身のテーマとして活動しています。
一般質問についてですが、八潮市議会では全21議員中、大体16人前後が行っています。余談ですが当市議会はインターネット中継などがないので、毎回傍聴席を満席にすることを目標に取り組んでいます。
議員になった当初は、「市政を変えたい」という思いが強いあまりに、首長や執行部と強くやりあったこともありました。しかし、そういう姿勢だと、どうしても議論が平行線になってしまいました。そのため現在のやり方としては、「会派を代表する」ような形で、一般質問を行っています。質問をするにあたっては、半年から1年をかけて準備を行います。例えば会派の議員を連れて視察をしたりして、質問テーマに関する問題意識や先進事例などを共有したうえで実施するようにこころがけています。
 「一般質問のために半年から一年かけて準備する」と語る八潮市議会議員の金子壮一さん
「一般質問のために半年から一年かけて準備する」と語る八潮市議会議員の金子壮一さん
白井:小金井市議会議員の白井亨です。当市議会は定数24名、女性比率は約41パーセントと全国トップレベルです。当市議会は良く言えば活発な質疑を保障する議会でして、必要とあれば夕食休憩を挟んで夜遅くまで徹底的に質疑します。そのため、年に何回か深夜議会に至ることもあります(それはそれで問題もありますが…)。私は1人会派ですが、当市議会は1人会派でも交渉権を持っており、代表者会議にも出席できるなど、その活動が保証されています。定数24名に対して会派が12あり、うち1人会派が8つという、かなり特徴的な議会かと思います。
議員になったきっかけを話せばきりがありませんが、一市民の立場から議会を見ていた頃のイメージから言えば、「何をやっているかわからない、伝えるすべも上手ではない」と思っておりまして、そういうところをテコ入れしたいと考えて、現在も活動しています。
小金井市議会では、一般質問は毎回ほぼ全員がやります。概ね1時間で、使い方は自由です。一般質問は、担当部局の管理職や職員あるいは市長に対して、質問で掲げるテーマについて質疑を通して答えを引き出す、ということがもちろん第一義です。ただ、それだけでなく、席を並べて聞いている他の部署の部長さんや他の議員とも“問題意識を共有できる場”とも考えています。
 「一般質問は“問題意識を共有できる場”」とする小金井市議会議員の白井亨さん
「一般質問は“問題意識を共有できる場”」とする小金井市議会議員の白井亨さん
――それぞれの議会によって、一般質問のありようが異なることがよく分かりますね。それでは、ここから核心に入っていければと思うのですが、ずばり成功した一般質問、失敗した一般質問というのはありますか。また、皆さんが普段一般質問をどのように組み立てて、当日まで準備を進めていくかなどをお聞かせください。
白井:何をもって成功したといえるかは、一概には言えないとは思いますが、執行部から「最大限の答弁を引き出すこと」とは言えるかと思います。
個人的に、最近の一般質問の中で成功したといえるものを取り上げるならば昨年(2017年)6月に行った、市の保育施策に関する一般質問です。小金井市は、どういう保育を行うべきかという長期的かつ全体的なビジョンを持っていません。ですので、まずそれをつくるということを、一般質問で投げかけました。昨今、どこの自治体でも、待機児童対策という「量」の観点からの保育施策は取り組んでいますが、やはり、今後クローズアップしていくべきは「質」の観点からの保育施策です。住民からも、保育の質に関する問題が起きているという訴えを聞いていたこともあり、保育に関するビジョンと基本的なガイドラインを市としてつくり、市が運営する公的施設だけでなく市内の全施設を対象に、保育の質の維持・向上に努めていく仕組みをつくるべきではないか、という提案をしました。
実は、この一般質問の段階では、市側の反応も鈍く、かみ合わずに終わったのですが、その後1年経った今年(2018年)の9月の定例会で、保育ビジョンおよびガイドライン策定を検討するという表明がありました。このことから、長期的に成功した一般質問であったと考えます。
この一般質問がその後の良い流れをつくることができたのは、質問後も取り組みを継続した ことにあると思います。一般質問の準備にあたって一人で世田谷区へ視察に行きましたが、質問後、保育を所管する厚生文教委員会の有志視察を実施し、委員会のメンバーに意識を共有することができました。私だけではなく複数の議員がその世田谷区の事例も参照しながら、ビジョンや保育の質に関するガイドライン策定についての主張を行うようになりました。また、ビジョンがないまま民営化を進めるのはおかしいという意見が父母側にもあり、それも執行部が方針を変更する一因になりました。自分だけが頑張ったという話ではなく、私の一般質問が契機になって、議会内そして父母からの後押しもあり成果につながったと考えています。
――一般質問を行って終わり、ではなく、むしろ取り組みのスタートであったと、とらえているのですね。この課題を一般質問で取り上げたきっかけはなんだったのですか。
白井:お子さんを民間保育園に通わせている保護者から複数の相談を受けていました。中には深刻な事案もありましたが、色々なケースをもとに調べていくと、市は民間保育園の運営や保育の中身について全く実態を把握していないということや、福祉オンブズマンは調査対象外で相談できず、第三者評価もほぼ機能していないという問題がわかりました。「いい保育をしていただいている」という性善説で完全にお任せ状態です(民間運営の素晴らしい保育園があることも知っていますので、民間だからといって十把一絡げに否定するわけではありませんし、公立園が最も良いとも思っていません)。市は、補助金交付等の施策を民間園に対しても行っているため、その関わり方について考え、先進事例を調査する中で世田谷区の事例に至り、参考にしました。運営主体を超えた保育の「質」に関する取組み事例はあまりなく、当市としても今後どこまで踏み込めるかは難しいところですが、やり方次第で先進事例の一つになり得ると思います。
――ありがとうございます。それでは、次は近藤さんにお話を聞ければと思います。近藤さんは一般質問に際してどのようなスタンスで取り組んでいますか。
近藤:白井さんは以前から注目していた議員さんの1人です。そのプレゼンテーションの手法も魅力的です。実は、私が議員となって初めて一般質問を見たときに、これはプレゼンテーション大会だと思いました。
(全員うなずく)
近藤:私にとって、一般質問は、公平に与えられている機会であり、そこでどうやって「確かにそうだね、近藤さんは面白いこと言うね」と、議員や職員の方々に思ってもらえるか、ということを考えて、今まで取り組んできました。
先ほどの話にあった「質」と「量」については、私も、保育や教育を含め様々な行政分野において、「まずは量の確保」といった職員の意識に直面することが多くありました。そうではなく、「質」に対する意識を欠落させてはいけないと、議員として主張しつづける必要性をいつも感じています。
また、白井さんもお話されていたように、ひとつの重篤ケースを客観的に分析すると、課題が見えてきます。私は、当事者が何に対して困っているかという現場感をもって分析することを心がけています。しかし、いわゆる「ワンオペ育児が大変」といっても、経験したことがなければ分かりません。そこで、客観的に分析して、論理的に訴えていくことが、一般質問において大事なスキルとなります。
例えば、子育てに関して主に年配の方から「女性が誰にも頼らず子育てするのは当たり前」といった反応が寄せられることもあります。その時は例えば、1世帯当たりの家族数の違い――1950年代ならおよそ7人だったものが今はおよそ2人で1人の子どもに接する大人の人数がそもそも少ない――など、数字をあげて客観的に説明することになります。
そう考えると、一般質問とは、「そもそも、そこから?」といった小さな課題を拾い上げる場であり、私の役割はそこにあるのかなと感じています。皆が「そこが課題だ」と認識できたら政策は進むんです。しかし住民のバックグラウンドが多様化している時代、原体験を共有できていないと、解決に向かおうというエネルギーが生まれません。こういう世代がこういう課題を抱えているということを、一般質問において具体的に共有することが必要になると思います。
金子:課題に関するデータをしっかり見せ、根拠をちゃんと積み上げれば行政も認めざるを得ないということはありますね。
近藤:「課題設定の力」は大切です。最近全国的にも話題になった「ランドセルの重さ」に関する一般質問もそうでした。子育て世代が皆何となく疑問を感じているものでも、それをすくい上げられるかどうかが問われます。実は反省もあります。自分の子どもが1年生のころから「重い」と言っていたのを、私が受け止められたのは3年生になってからでした。それまで「重いなんて甘えだ」「自分の頃はちゃんと背負っていた」と思ってしまっていました。それくらい、原体験に基づいた意識は動かすことが難しいです。
その後、実際に荷物の重さを量り、体重の3割を超えていることがわかり、何等かの形で取り上げなければと考えたちょうどその頃、他の議員からも同じような話がありました。そこで、WEB調査を行い、主張の根拠となるデータを揃えました。
そうやって、一般質問を積み重ねるうちに、徐々に発言力が高まり、政策が通るようになりました。具体的には、訴えてきた「学童保育」の政策の優先度が上がり、予算・審査の要望項目として全会一致で通るようになりました。一般質問で課題を提示し、実績を積み上げて、討論、統括質疑を通して全会一致の指摘・要望事項に上げられるかが大切であると私は考えています。自分が思っている課題意識を政策として実現するためには他の議員の方にも賛同頂けるようにしないといけないし、そのためには議員同士の熟議も必要です。熟議を経た提言は、その後安定して行政で取り組んでもらえるものになります。
議会は多様性があるべきところであり、私の意見や常識がすべて正しいわけではもちろんありません。だからこそ、議会内で合意を形成、折り合っていくために論点を提示すべきであり、そのためにはロジカルに発信していくことが必要になります。また、市民との勉強会やフェイスブックなどを活用し、市民を巻き込んで議論することを心がけています。
――ありがとうございます。次は金子さんにお話を聞ければと思います。金子さんが最近取り上げた一般質問はどのようなものでしたか。
金子:実は、近藤さんが提起されたランドセルに関する課題を、私も9月定例会の一般質問で取り上げたのですが、文科省から通知が出るなど逆にタイミングが良すぎてしまって、「個々の学校で対応します」という答弁となりました。それはある意味成功を引き出したともいえるのですが、自分としては残念なものだったと思っています。
僕の中で一般質問とは「変化するきっかけ」です。昨年の選挙の際、自分のマニフェストを検証してみたところ、項目全てにおいて何らかの進展があり、一般質問をきっかけに実現しているものも多くありました。ただ、実現までの時間はすごくかかっています。議員のマニフェストは目標設定です。それを首長のマニフェストと比較して、双方の目標が合致するものに関してゴールが早まるような後押しをしてあげるのが一般質問の役目ではないかと思っています。
冒頭、「傍聴席を満席にする」と言いましたが、僕は年齢も一番若く、チャレンジャーというスタンスでいます。傍聴者の数を、執行部の数よりも多くすることを心がけています。執行部に対して「なんで取り組まないの」という後押しする空気を傍聴席からつくるのです。
ただし、思いが強すぎると空回りする場合があります。執行部に対してあまり真正面から向き合ってしまうと、妥協点が見つからず、いいスタートになりません。まずは問題提起をして「やらなきゃいけないよね」といった雰囲気をつくるところで終えた方が、その後はスムーズに進むと思います。
私の一般質問の作り方として一番多いパターンとしては、以下のようなものです。例えば、自分は総務文教委員会に所属しているんですが、その関連でプログラミング教育など、やらなければならないことがわかっている課題について、先進自治体に視察に行き、次の日には必ず担当部署に「こういうのを見てきたよ、うちでもやらなくちゃいけないね」といった感じで資料を提示します。そして、総務文教委員会でも自分の一般質問の内容について相談します。予算もありますし、できる部分とできない部分があることは分かっているので、まず見てきたことを話し、お互いがどこまでできるかを詰めていくやり方で進めるのが、一番スピード感があると思います。
あとは、一般質問の内容に重みや論拠をもたせるため、根拠となるデータを用意します。自分でも聞き込みをしますし、同時に、執行部にも必ず別に調査を依頼します。実は先ほど挙げたランドセルの答弁では、教育委員会にも、質問の前にすべての学校にヒアリングに行ってもらっていたのですが、そこでは課題が1校くらいしか抽出できなかったのです。本当に困っている声が教育委員会には届いていなかった。執行部からは、自分で踏み込むと面倒だと思ってしまうのか、どうしたらやらなくて済むかという雰囲気を感じます。しかし、そういった状況でも、市民から直接上がった声を伝えるのが議員の役割だと思いますので、自分が保護者を回って吸い上げた様々な意見を一般質問などで共有します。
市民から寄せてもらう課題は、その場で解決できそうなものはすぐ対応しますけれど、時間がかかりそうなものは、その方を議場に来ていただき、その方のテーマを一般質問として取り上げます。その場に当事者がいた方が良い答弁が引き出せるし、解決に近づくのではと思っています。
近藤:金子さんが声かけをして、市民の方が実際に議場まで傍聴に来てくれるというのがすごいですね。
白井:普通は中々来てくれないですよね。
金子:お願いすると、住民は結構応じてくれますよ。あとはやっぱり議員が頑張っている姿は見えづらいので、議場に見に来てほしいというのはあります。
白井:そうか、八潮市は議会中継を行っていないというのも大きいかもしれませんね。小金井市は、一般質問の中継の視聴は結構多いようです。それが、直接傍聴に行かなくていいってことになっているのかもしれない。
近藤:議場で見るのは、中継視聴とは違いますよね。議場をいっぱいにするのはなかなか難しいことだと思いますよ。
金子:八潮市議会の傍聴席は42席ですが、だいたい毎回満席近く…30名くらいはいつも傍聴者がいらっしゃいます。傍聴の呼びかけとしては通告書と傍聴案内を近所に配ったりしてますよ。
近藤:金子さんの強みの1つはフットワークの軽さですね。
金子:あと、一般質問の組み立てとして最近意識的にやっているのは、あらかじめ見直しがあることがわかっている計画や施策について、1年位前から一般質問で取り上げて、きちんと自分の意思を入れていくこと。それは成果につながると思います。予算が組まれる前から一般質問でとりあげていくことが大切です。
白井:案が出てからでは遅いですものね。
近藤:先読みは絶対必要です。蓋を開けてみたら遅かった、とならないように。
金子:あとは、議事録は絶対5年分くらいは遡って見ます。同じことを聞いても仕方ないですし、やはり少しでも前進させることが仕事なので。時限があるもの、例えばインフラなどがそうですが、何月何日までにやりますとなっているものが、本当にできているか、「こういう答弁がありましたけど今どうなっていますか」と建設的に聞いていくことが大事だと思っています。
白井:他人の一般質問についての話をじっくり聞くことってなかなかないから面白いですね。
金子:他の議会の一般質問を見に行くのも面白いですよ。僕は結構行きます。近藤さんのところも行ったし。
近藤:来てくれてすごく嬉しかったです。私も行きたいと思いながらもなかなか……。私の世界はフェイスブックの中で広がっている……。
金子:それはそれで発信量がすごいと思います。傍聴に行くときには、知り合いの議員のところに行くというのではなく、気になる議会で気になるテーマがあったらぱっと行って、初めまして、みたいなことも多いです。
近藤:みんなで傍聴しにいこうキャンペーンとかできそうですね!傍聴ツアーとか、やりますか今度?
金子:そうですね。自治体の議員って、孤独な側面もある仕事だから、仲間を作りに行く感じだと思います。自分の議会内だけだと相談できる機会って限られちゃうので。
〔つづく〕
※(下)は12月10日配信予定です。お楽しみに!(編集部)