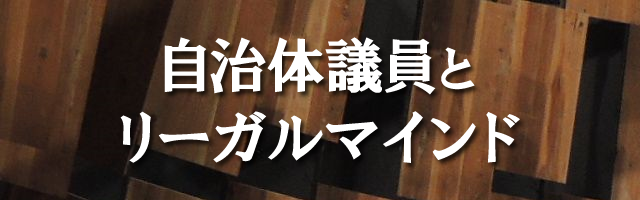(4)他の自治体の情報を押さえる
ここまでブレインストーミングした上で、他の自治体の同種の条例を集めて調査するといいでしょう。規定の意味などをより深く理解することができるはずです。
このときに注意しなければならないのが、自治体の権限などです。例えば、飲酒運転撲滅のためには、警察との協力や情報交換は欠かすことができません。「県は」という場合には、警察(公安委員会)も含めて表現することができますが、「市(町村)は」というときには、警察(公安委員会)は外部の行政機関になります。別に「警察との連携」を規定しなければなりません。
また、「飲酒運転の怖さ」を市立の中学校などで考える時間を持ちたいと思っても、「市長は、飲酒運転について、学校での学習機会の充実に努めなければならない」とは書けません。一義的には教育委員会の権限に属することだからです。主語は「市長は」ではなく「市は」とするなど工夫が必要です。よく、「同規模の自治体を参考にするといい」といわれます。「うちと同じような規模の◯◯市(町村)さんも行っていることですから……」と説得しやすい面もあるでしょうが、権限の面で誤りを犯さない知恵でもあるからかもしれません。
(5)立法事実の確認こそ命
議員の弱点は法制に関するスキルといわれますが、議員立法を補佐してきた経験からすると、案外、弱点となるのが立法事実の確認です。規制手段をとるには、そうした規制が必要な理由が不可欠ですし、予算措置を講ずることであっても、住民のお金なのですから、その使い道が有意義なものでなければなりません。
例えば、先ほどの飲酒運転撲滅について条例化しようとするなら、飲酒が原因と思われる事故がどれくらいあり、その飲酒場所として、飲食店がどの程度の割合を占めるのかのデータが欲しいところです。また、飲食店において「お店の人が飲酒運転を止めようとしたけれども、聞き入れてくれなかった」事例がどの程度一般的なのか、アンケートの結果があるといいでしょう。
つまり、条例を施行したことで、どの程度の事故が防げることになるのか、そのことを明らかにすることが提案に当たって求められるのです。「飲酒運転防止にプラスになることは確かなので、いいのではないか」。そうした反論を受けることもありますが、権利制限を伴う政策条例を制定するためには、こうした感覚は必須です。乾杯条例は定められても、さらなる政策条例を立案するには、立法事実に対する厳しい姿勢とそれを支える調査能力が求められるのです。
(6)定めっぱなしにしない
議会からの条例で気になることがもうひとつあります。それは条例制定後のフォローです。議会として特に関心があるからこそ、条例を定めたのです。条例を定めたことで本当に問題が解決されたのか、そのことにも議会として関心を持ち続けてほしいものです。新規の条例の場合には、「議会への報告」といった規定を入れて、恒常的に議会の監視を働かせることもいいかもしれません。
住民の声を踏まえて政策条例を作成することは難しいと思うかもしれません。しかし、一度、正面から向き合う機会を得れば、案外「コツ」がつかめるものです。案件があれば、チャレンジをしてみることをお勧めします。
(1) 吉田利宏「議会からの条例入門 第1回 議員提案条例の今」地方議会人2018年8月号40・41頁に詳しくデータを紹介している。
(2) 茅野千江子『議員立法の実際』(第一法規、2017年)参考資料別表2を基に作成。
(3) 政策条例ばかりでなく、議会に関する事項に係る条例も区別せず含まれている。