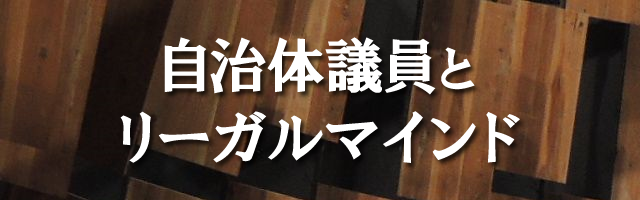5 議員のリーガルマインドをブラッシュアップする
議員がリーガルマインドを身につけ、高めていくには、どのようにすればよいのでしょうか。議会の議案の多くは法的根拠を有する場合が多く、自治体の施策も多くは法令の根拠があります。議員が、日常活動の中で法令の仕組みを学習することは十分可能であり、意識の持ち方でリーガルマインドを身につけることができます。
具体的には、議会審議のための議案調査、議会基本条例等に基づく議会報告会での地域課題に関わる法令の運用状況調査、法100条の2の規定による専門的知見活用制度、法115条の2による公聴会開催や参考人招致を活用した研究者等の専門家からの意見聴取、政務活動費を活用した専門家や大学からの支援、会派や議員有志による各種政策勉強会の開催など、多くの機会があります。
そして、最も大切なのは、議会事務局の調査機能の活用です。議会事務局には、議事担当と調査担当の職員がいます。このうち調査担当の職員は、議員の依頼に基づき、政策情報の調査や議員提案条例の立案支援などの業務を行うこととなっています。議会事務局の人的体制は様々ですが、まずは、これら事務局職員をパートナーとしてともに学ぶことが大切です。
6 むすびに──望ましいロー・メイカーを目指して
英語で「議員」という意味を示す単語に“Lawmaker”という単語があります。これは、文字どおり「法を創る人=立法者」を意味しています。つまり、本来、議員は法(条例)を創るのが使命であったわけです。当然、法を創るためには、その基本となるリーガルマインドが要求されます。これは、自治体の意思決定、行政監視の場合でも同様です。
議員は、一定の法技術的な知識もさることながら、政策を法的スキームで解析できるようになることが要求されます。
今後、全国約3万3,000人(8)の地方議員が、望ましいロー・メイカーとして、それぞれリーガルマインドを身につけることにより、我が国の地方自治の質が高まっていくことを期待したいと思います。
(1) 吉田利宏『法律を読む技術・学ぶ技術〈改訂第3版〉』(ダイヤモンド社、2016年)24頁。
(2) 北村喜宣『リーガルマインドが身につく自治体行政法入門』(ぎょうせい、2018年)はしがき。
(3) 例えば、宮城県の公社等外郭団体への関わり方の基本的事項を定める条例(平成16年宮城県条例54号)など。
(4) 齋藤俊明「議会および議員に関する調査報告書」(岩手県立大学、2003年3月)、津軽石昭彦「議員提案条例のつくり方」自治体議員実践研究会編『議員実践ハンドブック』(第一法規、加除式)。
(5) 上乗せ条例とは、法令と同じ規制対象に対して、法令以上の規制レベルを設ける条例をいい、横出し条例とは、法令より広い範囲を規制対象とする条例をいいます。
(6) 罰則を伴う場合は、立案段階で警察や検察庁と協議するのが実務上の通例です。
(7) 参照:法112条1項ただし書。
(8) 総務省の「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(平成29年12月31日現在)」によると、都道府県議会議員2,614人、市区町村議会議員3万101人であった。