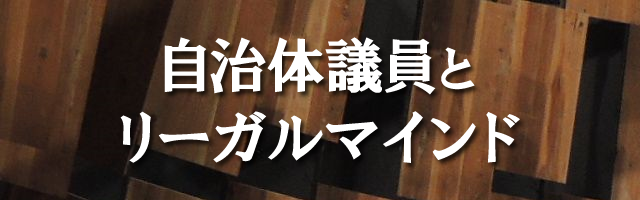関東学院大学法学部教授 津軽石昭彦
1 リーガルマインドとは
(1)リーガルマインドとはどんな意味か
「リーガルマインド」とは、どのような意味でしょうか。仕事として法律を日常的に扱い、運用する法曹、公務員、ビジネスマン以外では聞き慣れない方も多いと思います。直訳すると「法的なものの考え方」ということになるでしょうか。
専門家によると、法律を扱う行政やビジネスの現場での「物事の正義や公平の感覚」(1)、自治体職員が「違法な行政をしない仕組みをつくるためのいわば基礎体力として求められるもの」(2)との説明もあります。
これらを総合すると、「リーガルマインド」とは、法令を解釈・運用するに当たって、バックグラウンドとして必要となる「法的思考」ということができます。ここでは、「リーガルマインド」を「法的思考」とほぼ同義として扱います。
(2)リーガルマインドは議員に必要か
議員には、リーガルマインドが必要とされるのでしょうか。議員は、行政マンや弁護士等と違い、法律を直接的に解釈運用する機会は少ないので、不要と思われるかもしれません。
しかし、結論的には、議会のすべての活動においてリーガルマインドが必要です。
議会には、「意思決定機能」、「監視機能」、「立法機能」が権能として与えられています。自治体が多くの法令に基づく業務をしている以上、議会の権能行使に当たって、議員一人ひとりも当然、基本となるリーガルマインドが常に要求されるのです。
それでは、議員が議会に与えられた権能を行使する際に、リーガルマインドがどのように要求されるのか、考えてみましょう。
2 議会の意思決定とリーガルマインド
(1)議会議決の性質
自治体の議会は、議員で構成された機関であり、議会としての行為は必ず議決を経て行われます。議決は、自治体の「団体としての意思決定」の性格を持つもの(団体意思の決定としての議決)と、自治体の「機関としての意思決定」の性格を持つもの(機関意思の決定としての議決)に大別されます。例えば、自治体の予算や条例を議決するのは前者であり、議会としての意見書の議決や議会運営に関する決定は後者に該当します。特に、団体意思の決定に当たっては、議会としての責任は重大です。
(2)団体意思の決定としての議決
団体意思の決定としての議決には、法的思考はどのように求められるのでしょうか。議決は、法令に基づくものがほとんどです。例えば、地方自治法(以下「法」といいます)96条1項には、議会の議決事件として、議会の議決に付すべき事項が列挙されています。
条例の制定・改廃(1号)、予算の議決(2号)、決算の認定(3号)、地方税等の賦課徴収(4号)、重要な契約の締結(5号)や財産の処分(6号)等々、14件の議決事件が掲げられており、さらに、その他法令に定めるもの(15号)が多数あります。
また、法96条2項では、国の安全に関わるものなどを除き、議決事項を追加することができます。この条項を活用して、総合計画等の策定に当たって議会の議決を要することとしている自治体も多く見られます。
このように、団体意思の決定としての議決は、自治体としての意思決定であり、法令の適用そのものです。正しい法的思考の下での責任が伴う決定ということができます。
(3)機関意思の決定としての議決
機関意思の決定としての議決の場合はどうでしょうか。議会は、本来、首長等の執行機関とは独立した機関として、自主的・自立的に運営されるべきであり、自治体の機関である議会がどのような意思決定をするかは、議会を構成する議員相互が自立的に決定すべきものです。しかし、その議会の議決も法令が認めた裁量権の範囲内で認められるものであり、法令が認める裁量権を逸脱した意思決定は違法であり、訴訟の対象となります。
判例では、典型的な議会の機関意思の決定としての議員に対する懲罰権の行使に関して、一定の場合に処分性を認め、取消訴訟の対象としています。すなわち、議員の除名決議による処分については、「執行機関の処分をまたず直にその議員をして議員たる地位を失わしめる法律効果を生ぜしめる行為」とし、処分性を認めています(最判昭和27年12月4日行裁例集3巻11号2335頁、磯部力=小幡純子=斎藤誠編『地方自治判例百選〈第3版〉』(有斐閣、2003年)57事件)。
このように、機関意思の決定としての議決であっても、司法の対象となることから、決議案の作成に当たっては、法令との整合性をとり、告知・弁解・防御の機会を付与するなど適正な手続が必要となります。