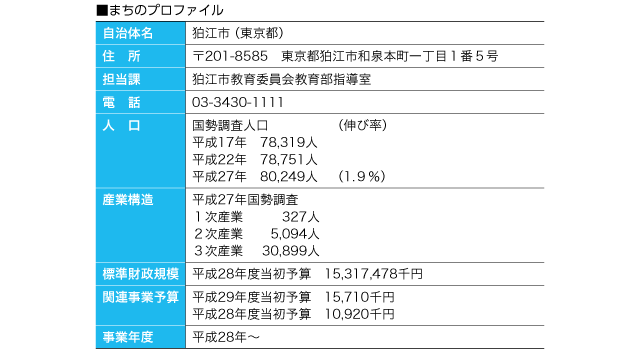イ 不登校対策――教育支援センター等の促進
本市では、教育支援センターの不登校対策の機能として、適応指導教室として不登校の児童・生徒が通級するゆうゆう教室と、通級できない児童・生徒のために家庭への訪問指導を行うゆうあいフレンド派遣事業を展開している。ゆうあいフレンド派遣事業は、適応を促すための学校訪問指導やゆうゆう教室へ訪問し、指導・援助を行う機能も持ち合わせている。
①ゆうゆう教室の取組みと成果
ゆうゆう教室では、ヨガやリズムダンス、バドミントンなどの運動や教科指導を行うとともに、音楽鑑賞や美術観賞、職場体験、そして園芸やものづくり等に取り組んだ。また、エゴグラムに基づくアサーショントレーニングを行い、表現する力を育んだ。さらに、体験活動の拡充として、本市の住民交流友好都市である小菅村への短期山村宿泊体験では、4人の中学生が参加することができた。現地では、フィールドアスレチック体験、沢歩きなどの様々な体験活動を行った。昼夜逆転していた生徒は、初日から21時30分には就寝し、翌朝6時前には起床することができた。また、小学4年生から不登校傾向にあった生徒は、数学の授業で夢中になって問を解き始め、解を導き出した。そして、中学校になり3年間ほとんど通学できなかった生徒は、現地の中学校での授業体験で、堂々と自己紹介ができ、後に次のような作文を書いた。「小菅中学校の見学はとてもわくわくした。校舎と体育館がきれいで正直かなり羨ましかった。少人数なところもあってか、学校の生徒たちがとても生き生きしているように見えた。給食もおいしくて通ってみたいと少し思ってしまった。」
また、短期山村宿泊体験の1か月後、宿泊に参加できなかった生徒をリードして、日帰りで、フィールドアスレチック体験行事を生徒が企画し、実施することもできた。
② ゆうあいフレンド派遣事業の取組みと成果
ゆうあいフレンド派遣事業では、週に1日、比較的年齢の若い心理士を派遣している。家庭から出られなかった生徒に寄り添い、3か月かけて外出できるように支援し、高校進学につなげることができた。また、学校に派遣し、自分の気持ちを相手に伝えたり、怒りをコントロールするスキルを生徒に指導したりすることで、人と円滑に関わるための支援を実施した。
③ フリースクールで学ぶ不登校児童・生徒への支援
フリースクールへは、ゆうゆう教室に通級するまでのステップとして、また、公的機関である適応指導教室とは異なった機能を生かして、不登校対策への幅広い支援を拡充させていくこととした。また、体験活動の合同実施を試みた。異なる組織が合同で活動を行う課題はあるものの、互いの特性を理解し、尊重するスタイルを探ることで、双方の機能拡充につなげることができた。
④ 経済的に困窮した家庭の不登校児童・生徒への支援
ゆうゆう教室の子どもたちは、不登校状態にあるため、学校で実施されている修学旅行等の宿泊行事には参加することができなかった。しかし、ゆうゆう教室で宿泊行事の企画を試みた結果、生徒4人が参加でき、また、フリースクールの生徒1人も、日帰りではあるが参加することができた。参加者の中には、経済的支援を必要としている生徒がいたが、国からの支援により、経済的な心配をすることなく体験的な活動に参加することができた。
5 これから求められる不登校の方策
今後、教育行政が不登校対策を拡充する可能性として、複雑多様化する不登校要因と一人ひとりが持つそれぞれの背景を理解した上で、一人ひとりの良さを引き出し、不登校状態を克服し社会的に自立できるよう、オーダーメードの支援プログラムが求められる。 また、家庭に引きこもり、社会と関わりを持つことができない状態の児童・生徒に対して、家族以外の人と接する機会を設けることにより、社会適応のための人間関係の構築が期待できる。成人になって社会に適応できるようにするためには、学校という社会で適応につまずいた子に対して、社会自立ができるように義務教育後も行政として支援していくことが求められる。