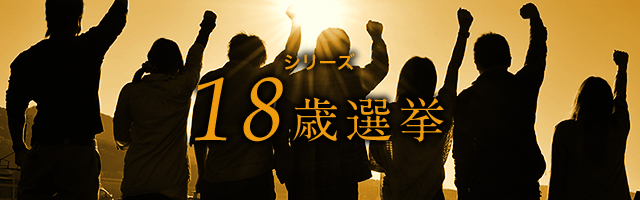(3)投票所に入ることができる子供の範囲の拡大
改正前の公職選挙法58条ただし書においては「選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者」については投票所に入ることができると規定されているところであったが、選挙権年齢の引下げに伴い、主権者教育の必要性が高まっていく中で、現実の投票を子供に見せることは、将来の有権者への有効な啓発となりうるものであり、また、有権者にとって投票しやすい環境の整備が求められている中で、子供を投票所に連れて入れるということは投票所への行きやすさにもつながるものと考えられる。
そのため、改正法において、公職選挙法58条に新たに第2項を設けて、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者)は、原則、投票所に入ることができることとされた。
ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、子供の入場を認めないことができることとされている。
子供の入場に当たっての年齢の確認については、仮に年齢満18年以上の者が選挙人に同伴して入場したとしても、ただ入場していたというだけでは選挙の効力に影響はないものと考えられ、そうしたことからも、一見して明らかに年齢満18年未満に見えない者でない限り、個別に年齢確認を行うことは想定されていないと解する。
また、「混雑」から投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがある場合とは、例えば、同伴者の人数があまりに多い場合や、多数の選挙人で投票所の中が既に混み合っており、当該子供を入場させると円滑な投票の管理執行が妨げられるおそれがある場合等が考えられ、「けん騒」から投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがある場合とは、例えば、投票所への入場を待つ列において、子供が大声を出したり、同伴する選挙人から離れて走り回っているにもかかわらず、同伴する選挙人が注意や制止をせず放置している場合など、投票所内の静穏が保持されないことが受付時の選挙人や子供の言動から明らかに予見される場合等が考えられる。
総務省では、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大に関して、執務上の参考とするため、「投票所に入ることができる子供の範囲の拡大に関する質疑応答集」を各選挙管理委員会に示しているところである。
3 地方自治体の対応等
総務省では、改正法の成立後、改正法等に伴う投票環境の向上のための施策(共通投票所の設置、期日前投票所の開閉時刻繰上げ・繰下げ等)について、この夏の参院選に向けての取組状況を調査した。
5月に公表した調査結果(4月25日現在)では、共通投票所の設置については、この夏の参院選で設置すべく準備中又は検討中と回答したのは、北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、長崎県島原市の4団体であった。
その後、函館市、平川市、高森町では、この夏の参院選で共通投票所を設置することを決定し、島原市では設置を断念したところである。また、熊本地震で被災した熊本県南阿蘇村では、施設の被災により投票所を統合し、有権者がいずれの投票所でも投票できるようにするため、共通投票所を活用することを決定した(6月8日現在)。
また、この夏の参院選での設置予定はないが、その後の選挙で設置すべく検討中と回答したのは、206団体であった。
期日前投票の投票時間の弾力的な設定については、この夏の参院選で投票時間の閉鎖時刻の繰下げの実施を予定している期日前投票所数は8か所(6団体)であった。また、開始時刻の繰上げ又は閉鎖時刻の繰下げの実施を行う予定であるが検討中とした期日前投票所の数は143か所(53団体)であった。
このうち、共通投票所の設置に当たっては、二重投票を防止する観点から、共通投票所と投票区の投票所の間で投票済み情報を共有する必要があり、特に、従来の投票区の投票所との間でオンラインシステムを構築するには、その数も多く、また施設への電気通信回線の整備状況も様々であることなどから、多額の費用と期間を要することが想定され、慎重に検討している団体も多いものと考えられる。
総務省では、この夏の参院選で共通投票所を設置したり、期日前投票の投票時間の弾力化を実施したりする団体の取組事例を各選挙管理委員会に紹介するとともに、再度十分に検討し、積極的な対応を行うよう、6月2日に改めて要請を行ったところである。
今般の改正法の趣旨は、市町村の選挙管理委員会が、地域の実情に応じて、投票環境の向上のための方策を講じやすくするためのものであり、この夏の参院選での取組はあくまでもその端緒である。
総務省としては、今後も、市町村の選挙管理委員会の検討に資するよう、他団体の取組を紹介するとともに、個別の団体からの相談にも応じ、有権者一人ひとりに着目した更なる投票機会の創出や利便性の向上に向けた市町村の選挙管理委員会の取組を支援してまいりたい。