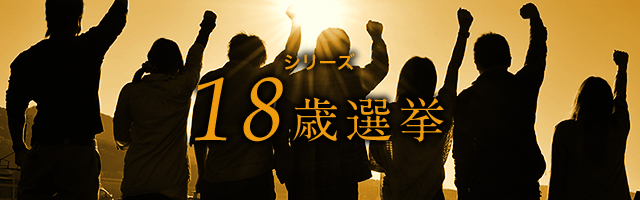早稲田大学マニフェスト研究所事務局次長 青木佑一
未来の有権者に社会や政治と触れ合う機会を
2016年の参院選から18歳選挙権が実現する。文部科学省と総務省が主権者教育のための副教材を作成し高校へ配布、政府が商業施設や駅への投票所設置や「共通投票所」設置に向けた公職選挙法の改正といった投票環境の向上を狙った施策を打つなど、次の参院選を機に、政治参加意識や投票率向上に向けた取組が各主体で行われるだろう。
前回の拙稿(2015年9月10日掲載)で、15〜19歳を対象とした「未来有権者調査」の結果として、「政治不信や政治離れは、若年層が持つ政治への距離感や無力感が根本にある」と指摘した。また、読売新聞の18歳成人に関する世論調査(2015年10月3日付)でも、若い世代の方が成人年齢を18歳に引き下げることに「反対」の割合が多い傾向があるなど、社会の意識がついていっていない現状があることは否めない。
そうした中で、未来の有権者たちには、家庭での教育や学校教育を通じて本物の社会や政治に触れ、「生きた政治」を考え、政策を比較し、地域の未来を選び取る経験が必要だ。今回は、副教材の公開後に初めて全国で実践した、実際の選挙を題材にした「模擬選挙」の事例を紹介したい。
教員が模擬選挙をしやすい環境整備
きっかけは2015年2月に模擬選挙推進ネットワークが開催した「模擬選挙研究会」で教員からお伺いした課題だった。模擬選挙の実践に躊躇(ちゅうちょ)していた中学校の教員から「やってみたら、やれるものだ」、「模擬選挙を実施して生徒が変わった」という感想が聞かれた中で、模擬選挙の実施に必要な政策検討資料の政治的中立性・公平性への懸念、そして資料集め作業(具体的には新聞の紙面探しとコピー作業)に多くの労力を費やしていることを知った。
当時、早稲田大学マニフェスト研究所では、候補者へ共通フォーマットのアンケート回答を依頼し、政策比較のためのウェブサイトで公開するなどして利活用を推進する「マニフェストスイッチプロジェクト」を同年4月の統一地方選挙から進めようとしており、このプロジェクトを活用することで「教員が安心し、そして負担が少ない形で模擬選挙を実施するお手伝いができないか」と考えた。そして、当研究所と各地の青年会議所などが協力し、第三者的に候補者の政策情報を集めた。情報は機会の平等を担保し、かつ同じフォーマットに150字という生徒にも分かりやすく読みやすい分量で書いていただいた。候補者の比較のための「政策検討資料」として5項目にわたる候補者の政策を当研究所が整理し、模擬選挙を実践したい教員に配布する。そうした環境整備を実現できたのは、同年7月の埼玉県知事選でのことだった。
環境整備を進めながらプロジェクトを活用して模擬選挙を実践してくれる学校を探したところ、2014年の衆院選で模擬選挙を実施した「クラーク記念国際高校さいたまキャンパス」の中川教諭と出会った。「埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワーク」の原口和徳氏が「公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会」と協力し、候補者4名の政策検討資料を収集。原口氏はさらに、授業に必要な埼玉県政の学習資料を作成し、中川教諭と授業モデルを作成するなど、模擬選挙の実施に備えた。2015年7月14日に実施した模擬選挙では、26名の生徒が実際の候補者の情報をもとにした投票を体験し、投票後のアンケートでは模擬選挙前と比べて選挙や政治に対する意識・関心が「高まった」と答えた生徒は8割を超えた。授業の最後に生徒たちの感想を聞いたが、「政策が分かりづらく、自分たちに関係のないものが多かった」、「仕方なく消去法で選んだが、それは『消極的な支持』にしかならない」といった意見をもらった。模擬選挙の結果は、実際の選挙で当選した現職が「落選」した。国政選挙と違い、争点が身近な地方選挙だと、実際の選挙結果と模擬選挙結果が違うこともあるという。そういう意味では、地方選挙らしい模擬選挙となったといえる。