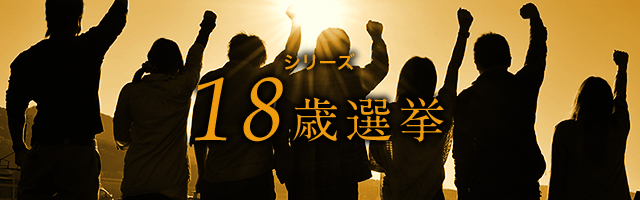当たり前のことをしっかりやるのが若者対策
では、彼らのような新しい有権者層を取り込むために、具体的にどのような対策が効果的なのか。ここまで分析しておいてがっかりされるかもしれませんが、18歳などの若い世代だけをターゲットにするのは、非常に効率も悪く効果も低いと考えています。
ネット選挙は解禁されましたが、有権者のネット活用度自体はまだまだ高いとはいえません。2015年の埼玉県議会議員選挙に対する調査(4)では、「県議会議員選挙の期間において、あなたが見たインターネット上の情報はどのようなものですか」という設問の答えとして、「該当なし」が56.8%でした。
東京都選挙管理委員会が発表している、2014年2月9日東京都知事選挙に関する世論調査の報告書(5)でも、選挙においてインターネットには「触れていない、見ていない」という回答が59.2%で最も高くなっています。
こうした状況の中、「18歳のインターネット活用度が高いから」という理由だけで、闇雲(やみくも)にネットツールにリソースをつぎ込んでもから回りする可能性があります。
そのことを念頭に、ネット選挙での戦い方について考えてみましょう。ネット選挙では、各種ツールの使い方が大変重要なポイントになります。近頃ではネットでの情報発信の手段が多様化しすぎていて、どれをどのように使えばいいのか分からない、という意見もよく聞きますが、だいたいこのようなイメージを持っていただければと思います。
ネット選挙対策5つのポイント
☆ブログを書く=ネットでの駅立ち
ブログは日々の活動や自分の思いを継続的に伝える場として効果的ですが、ただ書き続けることだけが目的化すると意味がなくなってしまいます。「どこどこへ行きました」というただの活動報告ではなく、地域や市政の課題や自分の政策を伝えるなど、読んでもらうための工夫が必要です。現在は、様々なニュースサイトが個人のブログの転載を行っているため、うまく活用できればブログひとつでも高い拡散力を持ち得ます。
☆ホームページ=ネット上の事務所
活動の拠点となる場です。有権者が気軽に訪れる場所ではないともいえます。その人の名前を知り、興味を持って初めて目を向ける場所ですので、関心を持ってやってきた人が正しく情報を持ち帰れるよう整えられていることが求められます。特に政治家サイトでは「プロフィール」ページへのアクセス数が多いという傾向があります。有権者は「何を言っているか」よりも「誰が、どんな人が言っているか」を気にする傾向がありますので、プロフィールページの充実は必須です。
☆Twitter=ネット上での辻立ち・交差点立ち
ファン、アンチ、無関心層など、あらゆる人たちから眺められる場で、政治意識の高い人も多く含まれているのが特徴です。良くも悪くも、発信の気軽さ・情報の拡散の速さがあらゆるSNSの中でも群を抜いているため、プライベート感覚で情報発信をするのはお勧めできません。政治家のTwitterでの問題発言がしばしば炎上しているのは皆様もご存じかと思います。誤解を招かないよう、コンプライアンスや人権意識をしっかり考慮した上で使うべきツールです。
☆Facebook=ネット上の後援会
その人への好意的な関心があって初めてフォロー(友達に追加)をする場合がほとんどです。実名登録者が多いこともあり、Twitterよりは「炎上しにくい」ツールで、コメントによるコミュニケーションも活発です。政治意識の高くない人もよく使っているツールですから、駅立ちの写真ばかりアップせず、プライベートな情報を交えた人間味のある情報発信が効果を高めます。
☆メルマガ=ネットで送る会報誌
政治への関心の高い人たちが、自分の意思で購読していることがほとんどです。毎回書き下ろすのは大変ですから、上記したブログやSNSでの発信内容をまとめ、定期的な発行を継続することが大切です。メルマガ読者に対しては、選挙期間中も選挙運動用メールを送信することができますので、平時から読者数を増やすための働きかけが有効になります。
このように考えれば、それぞれのツールに特性があり、ターゲットや発信の内容に工夫が必要であることはご理解いただけるかと思います。情報発信においては「分かりやすさ」を重視し、難解な専門用語ばかりを使うようなことは控えましょう。使う場合は注釈を入れるなど、若者をはじめとした、政治知識の豊富でない層に配慮した情報発信を心がけるべきです。
ネット選挙にしても、若い世代の有権者へのアピールにしても、「誰でも手軽にできて、票がすぐに増える」そんな魔法のような方法は存在しません。まずは、押さえるべき「当たり前」のポイントをきちんと押さえること。言い方を換えれば、実はどの世代相手であっても、当たり前のことを丁寧にやる、というのが基本であり効果的なのです。
当たり前のこととは何か。それは、自分の考えを、誠意を持って分かりやすく伝えること。相手の質問にきちんと答えること。忙しくても面倒でも、相手の立場を考えた対応に努めることなどです。当たり前すぎる、とあきれる前に、それがきちんとできているかをもう一度確認してみてください。
それにはまず何より、「問合せに的確に応答する」ことです。問合せのメール、SNSのダイレクトメッセージやメンションが来たときには、できるだけ早く、丁寧に返信してください。これだけでも、有権者にとっては受ける印象が全く違います。ネット選挙運動の解禁によって、有権者が政治家にコンタクトをとるための労力は確実に小さくなりましたし、今後はFAXや電話での問合せよりもネット経由の問合せが多くなるでしょう。
これは私の実体験ですが、ある政治家のホームページに掲載されている政策の中に誤字を見つけたので、問合せフォームからそれを指摘したところ、反応が「ご意見ありがとうございました。すべてのご意見に候補者は目を通しておりますが、返信はできません。ご容赦ください」という旨の自動返信のみでがっかりしました。「いちいち丁寧に返信していられないよ」と思われるのであれば、そういった感覚は有権者に確実に伝わっています。コンタクトをとる、という行為は、あなたへの関心が高いからこそ行われています。小さなものでも的確にすくっていくことが、世代を超えて、政治家への信頼と支持を集め、票を獲得する最短ルートだと私は考えています。
(1) 衆議院議員総選挙年代別投票率の推移
http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/
(2) 平成26年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査
http://www.soumu.go.jp/main_content/000357568.pdf
(3) ニールセンのデータ
http://www.jmra-net.or.jp/pdf/document/membership/release/nielsen20150127.pdf
(4) 第71回簡易アンケート「第18回統一地方選挙における投票行動及び選挙啓発に関する意識調査について」埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/supporter/kani71.html
(5) 選挙に関する世論調査
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/data/pdf/h26tochiji_yoron.pdf