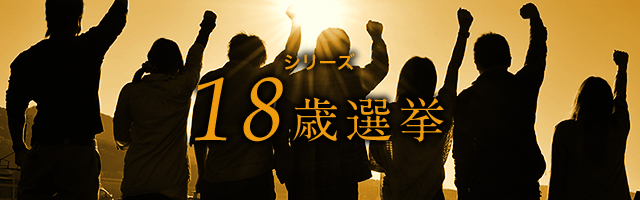Ⅳ 地方自治体の事務への影響~今後の運用の課題を中心に
1 主権者教育の充実
選挙権年齢が18歳以上となるに当たり、現在の高校生に対する「主権者教育」、つまり民主主義社会における政治参加意識を高めるため国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく主権者としての素養を身につけさせる指導を充実させることが喫緊の課題となる。
現在、学習指導要領に基づき、小学校、中学校及び高等学校の各段階の社会科及び公民科において、日本国憲法の基本的な考え方や我が国の民主政治や議会の仕組み、政治参加の重要性や選挙の意義等について指導されている。今後は、学習指導要領の改訂に際し主権者教育を位置づけていくことのほか、高校生について、①主権者教育の充実を図るための副教材を全ての高校生に配布することや、②公民や総合的な学習の時間において模擬選挙等の実践的・体験的方法も含めた指導を徹底すること、といった「実を伴った内容の主権者教育」を進める必要がある。また、小中学生について、主権者教育における中立性の確保を前提としつつ、各学校段階に応じて主権者教育の充実を図るための施策を推進することも重要である。今後、その具体的内容について、関係各位による精力的な検討がなされると考える(今般の法案審議において、文部科学省は、総務省と連携して、政治や選挙に関する高校生向けの副教材を作成中である旨答弁している)。
2 高校等における選挙運動の在り方
選挙権年齢が18歳以上となるに当たり、高校等における政治活動や選挙運動について、何ができて何ができないのかを明確にしておくことは、教育の場としての学校を円滑に機能させる観点からも必要である。
ところで、選挙運動は選挙人に対して何人を選挙すべきかの判断の基礎を与えるものであり、選挙運動は可能な限り自由にすべきであることから、現行の公職選挙法においては、「学校(及びその周辺)において」という場所に着目して選挙運動を規制するような規定は存在せず、また、児童・生徒・学生という身分に着目して選挙運動を規制する規定も存在しない。
今般の法改正により高校生の一部に選挙権が付与されることや現在の学校現場を取り巻く環境を考えた場合、具体的には、「選挙運動は可能な限り自由にすべきという要請」と「学校が『教育の場』であることの趣旨や学校に対する政治的中立性の要請」とをいかに均衡させるかが改めて問題となる。この点、直ちに法律による規制を課すことは選挙における選挙運動の意義等に照らして妥当ではないと考えられ、まずは、学校が、校則等を通じて自主的規制に取り組むべきであり、国や都道府県の教育委員会等においても、学校に対して、ガイドラインの提示を含め、適切な指導助言がなされることが望ましく、そのための検討が、本法施行までの1年の周知期間内に関係機関において行われることが期待される。
なお、高校生の政治的活動については、学校において適切に制限・規制すべき旨の文部省通達がある。しかし、当該通達は高校生の中に有権者がいないことを前提としたものであり、また、学生運動が盛んであった当時の時代背景を前提としたものでもあると思われることから、適切な見直しの実施が期待される(今般の法案審議において、文部科学省は、当該通達を見直す方針である旨答弁している)。
※文中、意見にわたる記述は、筆者の個人的な見解である。
■参考資料
◇第189回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号~第5号
◇第189回国会参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会会議録第2号~第4号
◇橘幸信=高森雅樹「法令解説・憲法改正国民投票法の制定」時の法令1799号(2007年)
◇橘幸信=氏家正喜「法令解説・憲法改正国民投票法が実施可能な土俵の整備」時の法令1962号(2014年)
◇国立国会図書館調査及び立法考査局「選挙権年齢を巡る議論及び諸外国の選挙権年齢」『国政の論点』(平成26年2月)
◇法務省法制審議会「民法の成年年齢の引下げについての意見」(平成21年10月)
◇総務省常時啓発事業のあり方等研究会最終報告書(平成23年12月)
◇文部省初等中等教育局長通達「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(昭和44年10月31日文初高第483号)