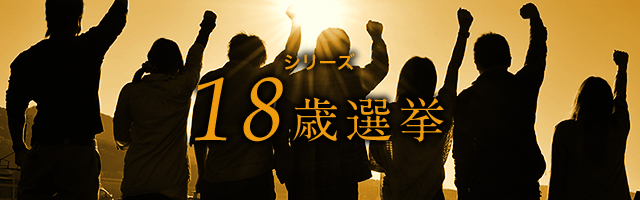2つの顔を持つ地方議員
議員の皆さんは2つの顔を持っています。ひとつは、民意を代表する代議員として、地域社会の利益、地域の普遍的な利益を代表するという顔です。本当はそれだけが議員の役割といえますが、現実は違います。実際、皆さんは後援会あるいは支持団体の支援により当選されていることが多い。場合によっては特定利益の代表という顔を示さないといけない。だから皆さんの顔は普遍的な顔と特定の顔、全体の代表か、特定の利益代表か、こういう2つの顔を持つことになります。
議員の皆さんは、普遍代表の顔であるべきですが、それができないのが現実です。それは、選挙制度に原因があります。現在、我が国の地方選挙は、大選挙区制をとっています。大選挙区制というのは、普遍的利益を考えていたのでは勝てない。自分の地盤を固めないことには勝てない制度です。候補者全員が政敵になる制度、それが大選挙区制です。どうしても、後援会をつくり、それを基盤にする。また、選挙地盤を大事にする。議員の皆さんが最初に考えるのは、支援組織、つまり後援会とか、あるいは自分の地盤、それから最後に全体の利益を考えるということになります。
ところが住民は違います。大多数の住民は、議員に対して普遍的な利益を代表することを期待します。議員の皆さんが特定の後援会とか特定の地元利益を優先することに反発します。そのため、議員としての大切にする優先順位と、住民が議員に望む行動様式との間に相当なギャップが生まれます。
また、同じ後援会や支援団体の中でも、意見が離反することの多いのが最近の著しい傾向です。例えば、保育所や特別養護老人ホーム、これらは以前は問題なく地域に建設されてきました。ところが、最近は住民の間で反対運動が起こります。こういう問題を、NIMBY(Not in My Backyard)と呼びます。つまり総論は賛成、しかし自分の家のそばにつくることには反対と叫びます。議員の皆さんの後援会内でも保育所建設をめぐって内部対立が起こる、墓地開設をめぐって利益相反が発生する。議員の地盤は、もはや一枚岩ではなくなってきています。議員がどちらかに肩入れをすると、後援会は瓦解します。支援団体は崩壊します。最近の地方政治で際立った傾向になってきています。
広報・広聴を通じて住民との格差を埋めよう
このような住民の期待と現実との格差をどう埋めればいいでしょうか。
私はぜひ、議会だよりや議会報告会のような広報・広聴を通じてこうした格差を埋めてほしいと思います。地方議会が議会だよりを定期的に出している国は、日本しかありません。議会だよりをより工夫し、住民の関心を引くものにしていただきたいと思います。また、議会報告会も大事にしていただきたいと思います。人数がなかなか集まらなくて廃止しているところも出てきました。しかし、議会報告会は将来を考え、10年、20年単位で見ていく必要があります。
最後に、議会基本条例です。これは、理想を描き、住民に夢を与える中身でなければなりません。条例は、理想を語るものでなければ意味がないと思います。皆さん、ぜひ議会基本条例に理想を書く、それをアクションプランで裏書きをする。そういう広報・広聴がこれから必要とされます。
(1) 2015年5月28日「朝日新聞」朝刊5面。
(2) 大阪市「特別区設置住民投票」2015年5月17日投開票。