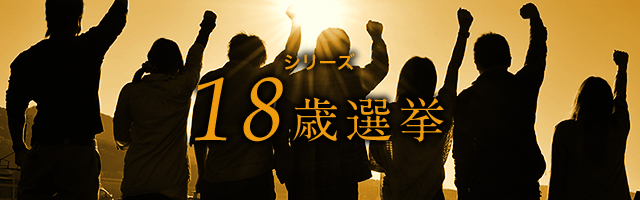選挙運動の規制緩和
ほかにも投票率を上げる方法は考えられます。日本の選挙は法律でがんじがらめになっています。これほど選挙を厳しく規制する国はほかにはありません。問題はなぜ選挙についての規制が厳しく、多いかですが、選挙を規制すればするだけ、制度は現職に有利に働きます。そこで、現在禁止されている戸別訪問を解禁したらと思います。中には戸別訪問は、買収のほか、様々な問題を生み出すという意見もあります。戸別訪問はイギリスやアメリカでは認められた制度です。それらの国の選挙で、買収や腐敗が起こるという事例は、聞いたことがありません。日本の有権者を信用しなければなりません。個別訪問を解禁すると、ヒョッとすると数は少ないにしろ事件が起こるかもしれません。しかし、それも例外で、日本の有権者は一般的には合理的な政治判断を下せると信じています。今のような戸別訪問の禁止は、そろそろ考え直す時期に来ているという印象を受けます。
また、現在の市議会選挙や町議会選挙は、選挙の期間が短すぎると思います。選挙期間が長ければ長いほど、議員の皆さんにとってはコストがかかります。だから戦後、これを縮め選挙運動の資金を少なくしようとしてきました。戦後、選挙の期間を短くするという声は、現職議員の間から持ち上がりました。選挙期間が長くなると、新人が当選する可能性が高まるからです。ただ、常識で考えて、選挙期間が5日間とか1週間というのは、いくら何でも短すぎると思います。選挙の運動期間を延長し、有権者が議員の政治公約に触れる機会を増やすことが必要と感じています。
投票率を上げる方法として、郵送投票も考えるべきでしょう。残念ながら私ももう高齢者ですが、寝たきりの方もおられるし、あるいは体の不自由な方もおられる。私はそういう人々のために郵送による投票制度が必要と感じています。すでに試験的に行われているところもありますが、大学のキャンパスに投票所を設置することも一案です。今はだいたい小学校が投票所に使われることが、一番多いと思いますが、投票所の設置について、もう少し知恵を出す必要があるのではないかと思います。
マークシートの導入という方法もあります。日本は投票用紙に候補者の名前を書くシステムをとっています。こういう制度をとっている国はあまりありません。なぜかというと、他の国では識字率が低いからです。日本では識字率は100%に近い、みんなが字を書けることを念頭に置いた選挙制度です。しかし、高齢になると字が書きにくくなります。投票方法をもう少し簡便化するためICT化を進め、選挙管理委員会の職員の手間暇を節約する方法を検討すべきでしょう。そうすることが、おそらく長期的には投票率を上げることに貢献すると思います。
最後に、投票率を上げる方策として選挙回数の削減があります。参議院選挙、衆議院選挙、それから知事選挙、都道府県議会選挙、市長選挙、市議会選挙……、選挙が多すぎます。従来は統一地方選挙でしたが、今は不統一地方選挙といってもいいくらいです。やはりどこかで1回仕切り直しをして、投票所、あるいは選挙の数を減らすということを考えないと、投票率は上がらないと私は思います。今までの調査を見ても、選挙回数が増えれば増えるだけ、有権者の関心は下がっています。現状の不統一を、統一する方法を考えるべきではないでしょうか。
投票率の高さと政治成熟度は必ずしも関係しない
投票率が高いと政治の成熟度は上がるのでしょうか。この相関関係には複雑な要因が絡んでいます。
戦後、市区町村選挙は都合、17回行われてきました。その市区町村選挙の投票率が、今回(2015年4月)は50%を切りました。切ったけれども、過去の17回の平均を見ると、70.25%になります。依然として投票率は高いということになります。これは、過去の投票率が高く、それが平均を押し上げる効果を持ってきたためです。以前、特に町村選挙では投票率は92、93%に達する事例もありました。なぜそんなに高いかというと、そのことは、民主的な成熟度とは関係はほとんどないように思います。昔は町の選挙になると、地域のボスから「あの人に投票してくれ」と頼まれたから投票所に行くという事例が多かったのです。いざ投票所に行くと、町とか村の規模になりますと、知っている人が選挙の立会人を務めています。有権者が頼まれたとおりに投票しないときは、立会人と目を合わせないそうです。これで、投票したかどうかは分かってしまうといわれてきました。投票率が高いのは、政治的成熟度とは関係なく、地域社会のプレッシャーなどによることが普通だったのです。
もうひとつは、投票行動の研究という分野があります。日本の投票行動の研究は、他の国にない「DKグループ」と呼ばれる概念を案出してきました。これは、「Don’t Know」の略語です。日本では主婦の皆さんに「あなたは誰に投票しますか」と聞くと、大抵の場合、「私は分からない(Don’t Know)、お父ちゃんに聞いて」という反応が多いのです。主体的に投票するのではなく、誰かの意見や指示に従って投票を行う、そうした他律的な投票形式をDKグループと呼んだのです。それが、日本の伝統的社会、とりわけ農村部に多く、町村選挙の投票率を上げてきた原因と考えられてきました。
ごく大ざっぱにいうと、投票率が上がることや下がることと基礎自治体の民主制の質とは、それほど一直線に関連する問題ではないということです。投票率で一喜一憂するというのは、あまり意味がないように思われます。