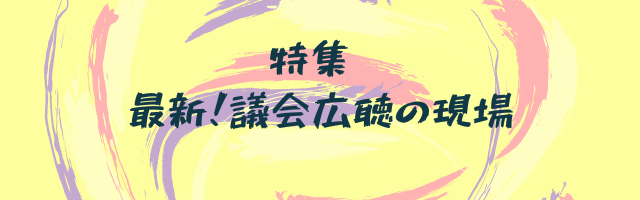一般社団法人自治体広報広聴研究所代表理事/広報アドバイザー/専門統計調査士
金井茂樹
1 はじめに
少子高齢化・人口減少など急速に変化する地域社会のなかで人々の価値観やライフスタイルの多様化が進んでいる。より良い地域社会実現のためには、これまで以上に住民の意見・要望をきめ細かく反映した政策の立案・執行が重要になってくる。
本稿は、前回の「『開かれた議会』のための広聴とは」の後半として、議会報告会と住民アンケートに焦点をあてて議会の広聴活動と政策立案・行政監視機能について考えてみたい。
2 議会報告会の現状と意義
最初に、昨今の議会報告会の取組みとその意義について確認する。
(1)議会報告会の取組み
市議会議長会の調査(「市議会の活動に関する実態調査」)によると、議会報告会は全市議会の54.6%で開催されている。また、その内容は報告のみ(1.6%)、意見交換のみ(15.1%)、報告及び意見交換(80.4%)となっている(2019年中の活動を対象とした調査)。議会報告会を実施する議会の9割超が“意見交換の場”として実施していることになる。これは多くの議会が住民の意見・要望を反映した政策立案への取組みを始めていることの表れだといえる。
昨今、この取組みにさまざまな創意工夫が重ねられてきている。いくつかの議会では “議会報告会”という硬い印象を与える名称から“ミーティング”や“サロン”といった柔らかい名称へ変更したり、子育て世代や平日勤務の就業者も参加可能な土・日曜日に開催するなど、参加者の固定化や世代の偏りという議会報告会が抱える課題解決のための取組みを行っている。また、参加者から意見・要望を聴く方法についても、ワークショップやワールドカフェといった手法の導入、BGM、会場レイアウトの工夫、ファシリテーターによる対話の活性化など、参加者の発言を促進する環境づくりも行われるようになってきている。
(2)議会報告会を実施する意義
自治体議会が住民との意見交換の場として実施する議会報告会には二つの意義がある。ひとつは“住民の声を起点とした政策立案”に結びつく可能性を有していることである。議会報告会で得られた住民の声は偶然的に“集まったデータ”であり、全住民を代表するものではない。参加は任意であり、それらは議会に関心が高い住民や意見表明を望む住民の声である。しかし、それらは個人的な体験や判断に基づくいわゆる“現場の知”や“市民の知”を含むものである可能性があり、地域課題の発見や政策立案の手がかりとなり得ることは十分考えられる。議会報告会によって必ずしも政策立案に活用可能なデータを得ることができるわけではないが、その実施は議会の政策立案機能の向上につながっていくのである。
もうひとつは議会の行政監視機能の向上に結びつくことである。議会報告会においては議員一人ひとりが事前に調査研究を行ったうえで住民と対話する。この調査研究、対話を継続することによって議員は住民が抱える悩みや要望をより深く理解することが可能となる。これは議員のコミュニケーション能力の向上にも寄与するものである。たとえ議会報告会から得られたデータが課題発見や政策立案に結びつかなかったとしても、住民との対話、データの収集と分析、その結果を踏まえた議員間討議によって一定の知見が議員のなかに着実に蓄積され、議会力を高めるはずである。住民の意見・要望を理解することで議会独自の視点は強化され、それは行政への監視機能の向上につながっていくのである。
このように議会報告会を実施する意義は、これからの自治体議会に期待される政策立案・行政監視の両機能向上に寄与する点にあるといえる。