2024.03.25 まちづくり・地域づくり
第5回 パネルディスカッション 住民自治を実現するシビックプライドの可能性(後編)
本村 相模原市には約72万人の市民がいます。相模原市に住んだ理由は様々あります。例えば、先祖代々、相模原市に土地があるから住み続けている人もいれば、子育てしやすそうな、田舎過ぎず都会過ぎないまちとして相模原を選んで来た人、東京や横浜へのアクセスがいいから相模原に来た人、様々な人がいると思います。
私は53年住んできて、自分のふるさとであるし、このまちから引っ越すという気は全くありません。本当にいいまちだし、誇れるまちだと思っています。まさに都市と自然のベストミックスで、いいまちだと思います。
市民一人ひとりの住む理由は様々ですが、何で自分は相模原で生活しているのか、何で自分は相模原にいるのか、ということを振り返っていただくことが、私はシビックプライド政策を成功させる一つの秘訣(ひけつ)だと思っています。これを明らかにするために、市民との対話を引き続き進めていきたいと思います。
シビックプライド条例を制定し、今度はシビックプライド向上計画を策定しましたから、もっと多くの市民に、まずはシビックプライドという言葉が耳に入るように、どんどん発信していきたいと思います。待つ行政ではなくて、出向く行政にしていこうと、チャレンジする相模原に変えていこうと、職員にも伝えています。
神奈川県には、相模原市よりも大変大きな横浜市、川崎市という自治体があります。仲間であるし、またよきライバルでもあります。さらに相模原市の近隣には、町田市、八王子市があります。都市間競争の中で勝ち抜かなくてはいけません。選ばれるまちになるように、しっかり頑張っていこうと職員にいっています。
そういった意味では、いろいろなことにチャレンジして、職員自らがチャレンジする、そして出向いていく。待つ行政ではなくて、出向いていく行政に変えていけば、より市民と対話ができますから、対話を重視して、これからもわくわくする相模原をつくっていきたいと思います。
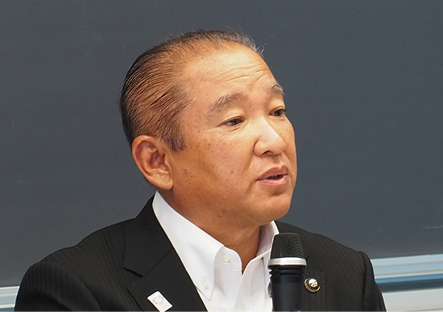
本村賢太郎(相模原市長)
牧瀬 最後に、私から質問したいと思います。先ほど水本さんから、シビックプライド政策を成功させるためには、市民のため、forではなくて、市民と一緒にやっていく、withという話がありました。私も、そのとおりだと思います。
また、大谷さんからは、「この指とまれ」という方式で進めてもいいのではないかという話もありました。ところが、多くの市民は一緒にやってくれない可能性があります。なので、どうすれば一緒にやってくれるのか、という問題提起です。このことについて、端的に見解をいただければと思います。この点について、木村さんと大谷さんにご意見をいただければと思います。
木村 「面白いこと」が大事だと思います。とにかく面白いこと、楽しめること、遊びながらでいいと思います。そういうことをずっと続けていければ、誘い合うという幅は広がっていくと思います。
大谷 人の行動をまちの都合に合わせるということはできませんので、基本的にはこの指にとまらないなら仕方がないと思います。けれども、いろいろなこの指があれば、どこかに引っかかってくるはずです。生活をしていて、人と関わることって面白いよね、というふうに思う瞬間は結構あると考えます。
また、自分が主体的に関わらなくても、誘われて嫌々ながら行ったけれども、今日は一日面白かったという体験もあります。なので、動機は何だっていいと思います。多様な活動があることによって、どこかで引っかかっていく、そして広がっていく。このような取組みを地道にやっていくことが大事だと思います。さらにいうと、面白さを、いろいろな形で、いろいろな人から発信してもらうことで、自分もちょっとやってみよう、となる気がします。
牧瀬 楽しいこと、面白いことをたくさん増やしていくことの重要性についての指摘がありました。いろいろなチャンネルをつくって増やしていくというのがポイントだと思いました。
以上でシンポジウム「住民自治を実現するシビックプライドの可能性」を終了いたします。ありがとうございました。








