2024.03.25 政策研究
第8回 民主主義と議会③─中間団体とSNS、投票率、不信、議員・議会に求められるもの、政党(会派)、権力分立
政府(議会・行政)への不信は「負のスパイラル」を生み出しやすい
ところで、「政府(議会・行政)への不信は負のスパイラルを生み出しやすい」ことも知られています。曽我謙悟はこのことに関して、政府を信用しない人々は政府がリソース(税や社会保険料などの政策資源)〔( )内は筆者補〕を調達することに同意せず、そのことは政府のアウトプット(産出〈出来高〉)〔( )内は筆者補〕を減少させるとし、十分な政策を生み出せていないことを見て、再び人々は政府への不信を強めるとしています(曽我 2022:442)。このようにして、「人々の政府への不信」と「政府の失敗」の間には負のスパイラルが生じるのです。
例えば、曽我は2000年代半ば、とりわけ第1次安倍政権を揺るがした年金問題が、その例であるとしています。そして、これ以外にも様々な分野で、現在の日本の行政はそうした状態に陥っているとしています。公務員数は人口比で見て世界最少となり、人々の情報を持たないことから、必要なときに働きかけを行うこともできません。新型コロナウイルス感染症への対応において、給付金・助成金の給付やワクチン接種対象者の把握や予約などに時間がかかり、混乱が生じたことも、その例であるとしています(曽我 2022:442-443)。
このような負のスパイラルは、曽我がいうように、これはこれで一つの均衡であるだけに、そこから抜け出すことは容易ではありません。このことは、前節で見た「認識の欠如からの脱出」には、個別具体の課題をアジェンダの上位に押し上げる要因が、今起きているのだということを強く認識することが求められます。
そして曽我は、負のスパイラルは唯一の均衡ではなく、人々は行政を信頼し、行政はそれに応えるといった(正のスパイラル)均衡も存在するとしています(曽我 2022:443)。そこでは、人々の行政に対する期待と信頼を、いかにして高めていけるかがポイントとなります。もちろん、このことは議会にも当てはまります。
議員・議会に求められるもの:広く人に役立つ・アウトリーチ・市民の立場に立って真摯に受け止め対応策を模索し行動する
では、前節で見た「負のスパイラル」から脱出し、現代社会の目標を達成するため、政治家(議員・首長)には何が求められるのでしょうか。かつて、医師の心がまえとして「恐れるのは、(医療)訴訟ではなく、救える人を救えないことである」「怖いことは恥ずかしくない。恥ずかしいのは、そこから逃げること」という旨のセリフがあるテレビドラマを見たことがありました。このような医師の心がまえは、市民一般にも求められ、特に社会のリーダーである政治家にとっては大切なことなのではないでしょうか。
また、あなたが医者になるのは、「人を救うためか、もうけるためか」と問われたときに、患者の期待に応えることができるのは、「人を救うため」という答えであるはずです。同様に、あなたが政治家になったのは(なるのは)、「自分でもうけるためか、支援者・関係者の便宜を図るためか、広く人に役立つためか」と3択で問われたとき、政治家であるあなたは「広く人に役立つため」と何人に対しても明確に答えることが求められます。しかしながら、個々の政策で見ると、新型コロナ対策や災害支援対応のように、本当にそうであったのか、総論賛成でも各論(個別)ではどうだったかという厳しい評価が見られる事象もあった(ある)ように思われます(表6参照)。もちろん、政策能力や政策資源の問題もあったでしょうが。
さて、市民の信頼を失わず、信頼を維持し続けるためには、まずはコミュニケーションを図ることが肝要です。議員・議会には、自ら市民に向けたアウトリーチをすることや、市民から声がかかれば市民の立場に立って真摯に受け止め、対応策を模索し行動することが求められます。
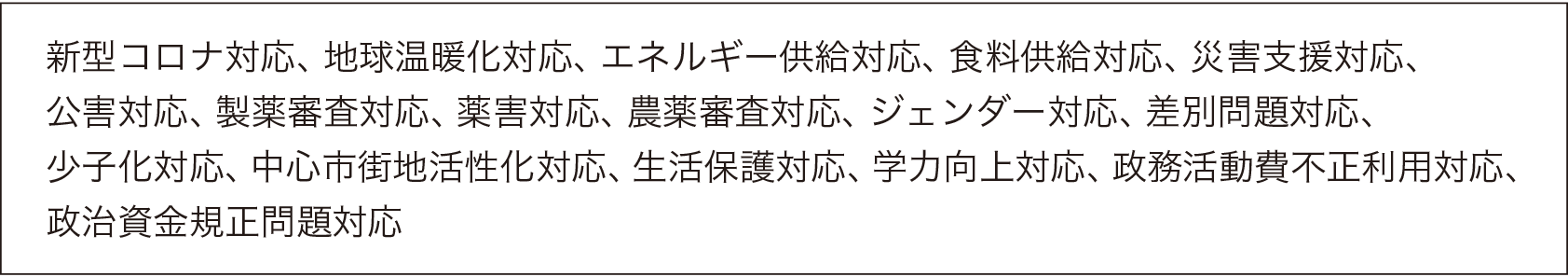
出典:筆者作成
表6 政府(自治体・国)にとって厳しい評価となった政府政策の分野(例)








