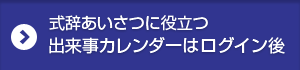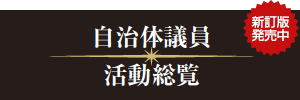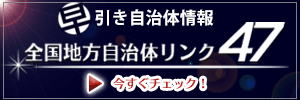2022.07.25 政策研究
第28回 多数性(その2):ミクロ自治論とマクロ自治論
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之
自治の動向?
漫然と自治について論じるとき、一体、何を論じているのかは自明ではない。前回から触れているように、自治体の特徴の一つは、「類的存在」としての多数性である。自治体は多数存在するからである。それゆえ、ある特定の一つの自治体で見られた現象を取り上げて、自治体一般を論じることは、直接的には容易ではない。
例えば、新潟県巻町で原子力発電所の立地(正確には電力会社に対する町有地の売却)の是非をめぐって、1996年8月4日に、条例に基づく諮問型住民投票が行われたという歴史的事実がある。条例に基づく諮問型住民投票が実施されたのは、日本で最初といわれている。この事実を受けて、現代日本の自治体では条例に基づいて住民投票が行われたことはある、とはいえる。が、その先に、自治体一般として、住民投票は当たり前のものになった、とか、住民投票は意思決定方式の一つになった、と直ちに論じることは容易ではない。そのように論じるためには、論者の理論的な位置付けが必要である。反対に、条例に基づく拘束型住民投票は存在しない、住民投票は大多数の自治体にとってみれば異例である、などと論じることもできるが、このときも理論的な位置付けを必要とする。あるいは、1990年代から2000年代という、分権改革や平成の大合併などがなされた、特定の時期に特有の現象と、理論的に位置付けることもできよう。
一つの事象から、将来の方向性の予兆を、予測的・予見的に、あるいは、運動論的・規範的に提示することもできよう。あるいは、一つの事象は逸脱した例外にすぎないと、無視することもできよう。さらには、実例が一つでもあれば、類的存在としての自治体がなし得る潜在的選択肢集合(capability)の範囲は拡大したとして、地方自治一般を規定する事象とみることもできる。反対に、あくまで特殊な自治体のみが実現可能な事象にすぎず、多くの自治体にとっての潜在的選択肢集合の範囲は拡大していないと反対に位置付けることもできる(1)。コップの水は半分もあるのか、半分しかないのか、という具合である。特定の自治体の事象から、いかなる一般論を導くのかは、理論構成次第である。