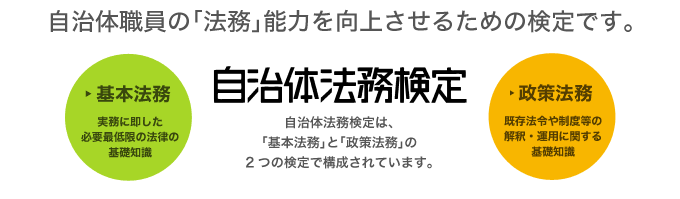2022.06.10 議員活動
自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その46)
正解及び解説
■基本法務
〔正解〕②
〔解説〕この問題は、行政法の行政救済法分野からの出題である。抗告訴訟とは、公権力の行使に関する不服の訴訟であり(行政事件訴訟法3条1項)、当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する訴え(行政事件訴訟法4 条)であるから、①④は妥当でない。当事者間の具体的な権利義務の紛争であって、法令の適用によって解決可能なもの、という二つの要素は、法律上の争訟の要素である(最判昭29・2 ・11民集8 巻2 号419頁)。民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう(行政事件訴訟法5 条)。よって③も妥当でない。②は機関訴訟を定めた行政事件訴訟法6 条からの引用である。(基本法務テキスト128~129,149頁)
■政策法務
〔正解〕③
〔解説〕①は妥当でない。並行条例は法律とは独立しているが、同一事項について「並行」して要件と効果を定めるため、法律上の制度と条例上の制度が競合・重複するので、法律との抵触関係が生じ得、適法性も問われる。②は妥当でない。排水基準条例は個別委任型条例であり、屋外広告物条例は包括委任型条例に分類される。③は妥当である。書き換え条例は、委任なしに法律の基準等を変更するため、「法律の範囲内」(日本国憲法94条)に収まらず違法・違憲の疑いが生じかねないことから、ほとんど事例がない。これに対し、具体化条例は、法令の具体的内容を条例によって定めるものであり、基本的には「法律の範囲内」なので、事例も少なからず存在する。④は妥当でない。条例については、条例で定めることが必要な事項について定めている「必要的事項」条例と、必ずしも条例で定めることが必要ではない事項でも自治体が重要と考えて条例に定めている「任意的事項」条例に区分でき、どちらも存在する。(政策法務テキスト39~42頁)