2021.05.25 政策研究
第14回 地方性(その5)
民俗学
柳田はその中でも、民俗行事や巫女(みこ)・山民など民俗信仰への研究志向が強く、また、農村生活に傾斜していく。これは、柳田が主宰した『郷土研究』の編集方針に現れており、名称は似ているが、郷土会の郷土研究とは、やや分岐していたのである。
この点を指摘したのが、これも民俗学者に位置付けられることの多い、南方熊楠であったという(7)。南方は、『郷土研究』は柳田が「ルーラル・エコノミー」を標榜(ひょうぼう)している以上、もっと地方経済・地方制度を取り上げるべきことと主張した。さらには、地方の研究ならば、地方経済にとどまらず、地方政治の研究も必要とした。現状の郷土研究では、せいぜい、「俳人の紀行にして俳句を抜き去りたるがごときもの」にとどまっている、と批判した。つまり、地方学の系譜を引く郷土研究は、政治経済を抜きにとどまるべきではないことを主張していた。
しかし、柳田は、「ルーラル・エコノミー」を研究すると自称していたが、それを南方が「地方経済」と和訳したことに異を唱え、むしろ、「農村生活誌」と表現してほしいと表明した。その意味では、新渡戸のような「ルリオロジー」や「ルリオグラフィ-」といっておいた方がよかったかもしれないともいう。
柳田に限らず、柳田らが郷土研究を経て開拓していった民俗学は、ある意味で極めて実践的な指向性を持つとともに、同時に、国策に奉仕する国策の手段としての「官の学」に吸収されない「野の学」としての魂を持った。それは、ときに、自治体という国ではない政策主体の持つ二面性の求める知識である、自治体行政学にも、相通じるところがあろう。「官の学」、「与の学」ではないが「野の学」でもない。「統治の学」ではないが「自己啓発の学」、「アナーキーの学」、「脱(反・非)政治の学」、「私生活の学」でもないのである。
とはいえ、民俗学が、政治経済の側面への関心をそぎ落としていくならば、自治体の持つ地方性に関する研究からは、遠ざかっていく。それは、地方自治研究や自治体行政学から見れば、地方性を探究するかに見えた地方学は、不熟のままで解体・分化してしまったのである。
(1) そして、新渡戸の論理的には、植民政策学のためにも、同様である。
(2) この意味で、地方=田舎(ruris)であって、都会と対比される概念である。
(3) ロバート・A・ダール著、河村望=高橋和宏訳『統治するのはだれか』(行人社、1988年)。
(4) 並松信久「新渡戸稲造における地方(ぢかた)学の構想と展開─農政学から郷土研究へ」京都産業大学論集社会科学系列28号(2011年)66~68頁。新渡戸稲造「郷土を如何に観るか」郷土創刊号(1930年)。なお、郷土会に関わり、また、新渡戸と柳田國男を架橋した、人文地理学者の小田内通敏によれば、ドイツの「Heimatkunde(郷土学)」に相当するという。地方学ないし郷土研究は、その後、小田内流の集落(人文)地理学と柳田流の民俗学に分岐していったと見ることもできる。なお、ドイツ語のHeimatは、「生まれ故郷」、「郷土」のほかに「祖国」という意味がある。小田内の「郷土」概念も、時代情勢に適合して、「地域性」から「民族性」を経て「観念性」に変化していったという。石井清輝「戦前期日本における国民国家と『郷土』」三田社会学10号(2005年)81〜95頁。
(5) 宮田登「郷土会と郷土教育」児玉幸多=林英夫=芳賀登編『地方史マニュアル1 地方史の思想と視点』(柏書房、1976年)。
(6) このようなスタンスの変化は、当時の国策である地方改良運動への、やや両義的な思いを反映しているのかもしれない。
(7) 粘菌研究でも著名であり、生物学者・生態学者(植物棲態学ecology)とも博物学者とも位置付けられることもある。
* * *
〈筆者近刊書籍〉
(タイトルクリックで詳細ページに遷移します)
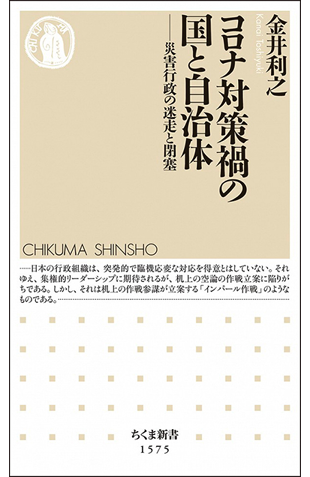
『コロナ対策禍の国と自治体─災害行政の迷走と閉塞』ちくま新書(2021年5月発刊)








