2021.05.12 議員活動
第8回 評価と議会
5 業績測定
政策の実施状況が検証されると、評価の焦点は政策がもたらした結果に移る。行政が社会に対して実施した政策の活動内容と、それによる成果(結果)の状態が計測される。これが「業績測定」である。行政による活動から「産出(アウトプット)」が生じる。産出をもとに社会に対して「成果(アウトカム)」が現れる。「業績測定」は、この産出と成果を「業績(パフォーマンス)」とし、それを計測するのである(秋吉 2017: 169-170)。
業績測定では、まず、業績に関する指標(業績指標)が設定される。その政策において何が産出であり、何が成果であるかが指標として示される。業績指標には、二つの特徴がある。第1の特徴は、産出と成果の状況が数量的に測定可能な指標として設定されるということである。第2の特徴は、指標ごとに目標値(数値目標)が与えられることである。目標値が設定されると、次は「当該目標値が達成されたか」に関心が移る。業績測定で測定結果が出ると、経年での数値の比較とともに、他の自治体政府との比較が行われる。優秀な取組みのプロセスを比較・観察していれば、自分たちの組織で何を改善すればよいかが明確になる(秋吉 2017:171-174)(表2参照)。このことは「評価における相互参照」、そして「評価における政策波及」といえる。自らの「議会活動の評価」を「行政活動の評価」と比較する「相互参照」(二元代表機関(議会・行政)における相互参照)も期待される。

出典:筆者作成
表2 業績測定の例
なお、業績測定とアウトカムとの関係について、南島和久は、①単年度予算主義とアウトカム(特に、中間アウトカムや最終アウトカム)発現時間の乖離(かいり)、②政策主体・部局の多元化とアウトカムの断片化、③欠陥業績指標の増加(無理にアウトカムを示そうとし、無意味な業績指標ばかりができてしまうこと)、という問題の存在を指摘している(南島 2018:190-191)。議会・議員には、これらの点にも留意した行政に対する評価が求められる。
6 インパクト評価
政策が適切なものであったかを検討(評価)する上で最終的に重視されるのが、「政策が当初の目的を達成したか」ということである(秋吉 2017:178)。政策が社会に課題解決のインパクト(効果)を与えたかを検討するのが「インパクト評価」である。
インパクト評価は、グループA(介入群)とグループB(対象群)をつくり、グループA(介入群)には政策を行い(=政策の実施)、グループB(対象群)には政策を行わず(=政策の未実施)、両グループの比較を行い、政策の効果を見極めようとする。その際に求められるのが「制御」である。「制御」とは、政策の「実施」、「未実施」以外の条件を等質なものとすることである。そのためには、グループA(介入群)とグループB(対象群)を無作為に抽出することが肝要である。これを無作為化と呼ぶ(伊藤 2015:234-235)。そうすることにより、政策の効果を確認することができる。
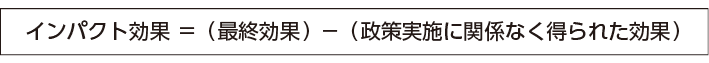
出典:筆者作成
図4 インパクト効果








